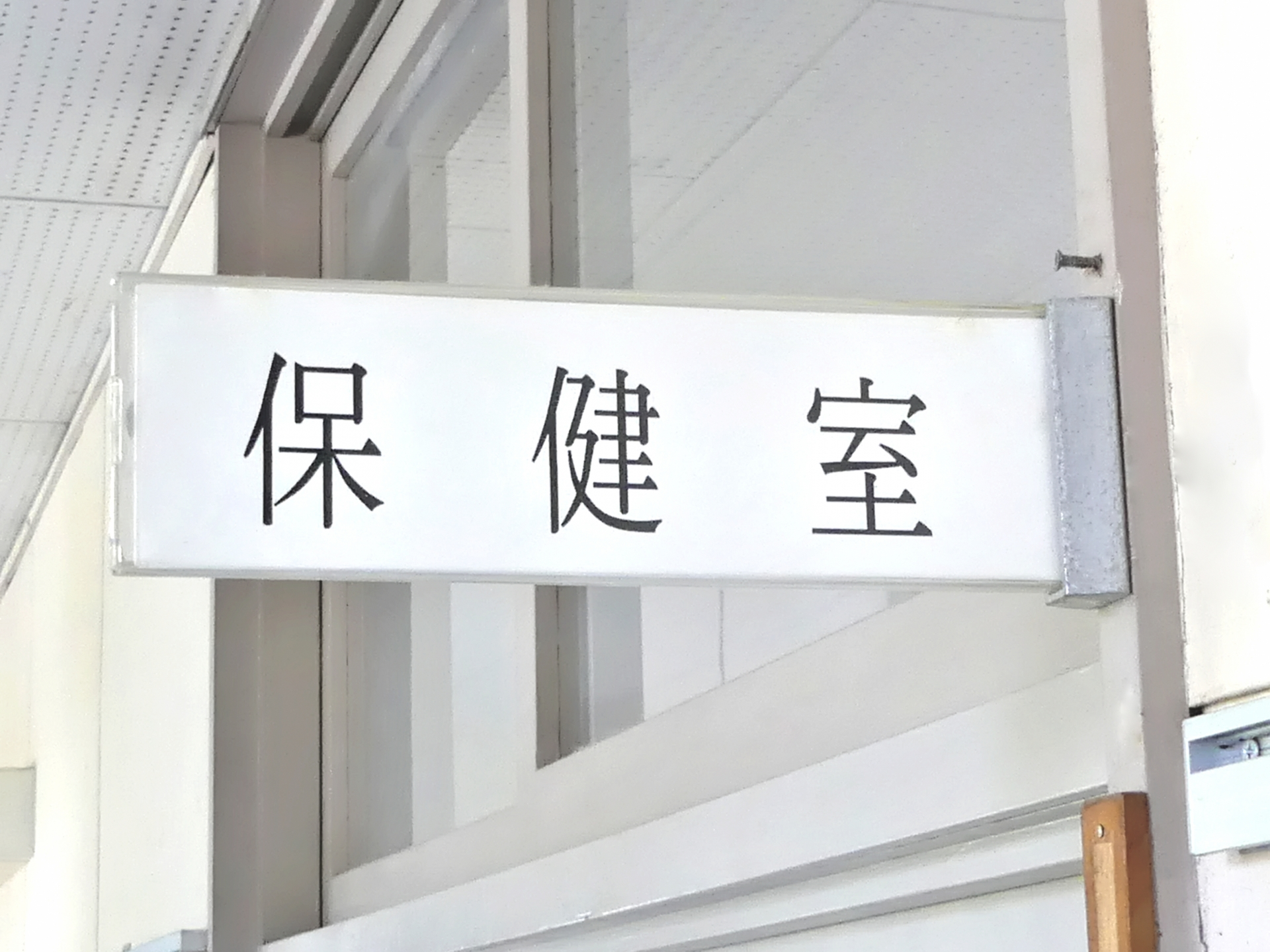目次
学校が怖いと感じる子どもの背景

「学校が怖い」と感じるお子さまが増えている背景には、社会や学校現場の変化が影響していると考えられます。
文部科学省の調査によると、小中学生の不登校は年々増加傾向にあり、「不安」や「無気力」など心理的な要因が大きな割合を占めています。
また、いじめの認知件数も高止まりしており、学校が安心できる場所とは言いきれないケースが多々見られるのが現状です。
こうした環境の中で、お子さまが「学校=怖い場所」と感じてしまうのは、特別なことではありません。
周囲は、まずその背景を理解し、安心できる関わり方を考えていくことが大切です。
(参考:文部科学省 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)
学校が怖いと感じる理由

お子さまが学校に対して「怖い」と感じる理由は、多くの場合、一つではありません。
心身にストレスがかかったとき、その苦しさが「怖い」「行きたくない」といった形で表れることがあります。
原因は複雑に絡み合っていることも多く、本人も明確に言語化できない場合もあります。
ここでは、お子さまが学校を怖いと感じる、主な理由を解説します。
いじめや人間関係の不安
お子さまが学校を怖がる理由の中で、最も多く見られるのが、いじめや人間関係の不安です。
いじめを受けている、あるいは受けていると感じている場合、教室という空間そのものが脅威となります。
明確ないじめ行為が確認されていなくても、「話しかけても無視される」「一緒に行動する相手がいない」などの経験が続くと、対人関係への警戒心が強まってしまうでしょう。
お子さまは、人との関わりに安心を見出せない状況では、学校に身を置くこと自体に強いストレスを感じるようになります。
学習のつまずきや授業への不安
学習面でのつまずきも、お子さまが学校に不安を覚える大きな要因です。
授業の内容が理解できない状態が続いたり、周囲のペースについていけなかったりすると、自信を失い、登校への抵抗感が生まれます。
特に発表や指名の場面では、緊張感が積み重なり、教室での時間を苦痛に感じることがあるかもしれません。
このような不安が強まると、お子さまは学校そのものを避けたくなってしまうかもしれません。
先生との関係のストレス
お子さまが担任や教科の先生との関係に不安を抱いている場合、それが学校への恐怖につながることがあります。
先生の言葉づかいや表情、態度などを敏感に察知し、威圧的だと感じている可能性も否定できません。
また、叱責や注意が繰り返される中で、「先生に嫌われている」「自分だけが目をつけられている」と感じるようになると、心の緊張はさらに強まります。
このような状況が続くと、教室内で安心して過ごすことが難しくなり、登校への抵抗感につながることがあります。
学校そのものへの苦手意識
お子さまによっては、学校という場全体に対して漠然とした苦手意識を抱いていることもあります。
集団行動や時間の管理、教室内の音やにおいなど、日常的な刺激が負担になるケースもあるのです。
特に、発達特性によって感覚過敏や環境の変化に敏感なお子さまは、教室のざわつきやスケジュールの詰まり具合などにストレスを感じやすい傾向にあります。
新学期や学年の切り替わりなど、環境の変化が大きい時期には、こうした傾向が顕著に表れることがあるため、注意が必要です。
家庭環境や生活の変化による心理的影響
学校に対する不安は、家庭環境や日常生活が影響している場合もあります。
たとえば、保護者様の仕事の変化や転居、家族構成の変化など、日常の安定感が揺らぐ出来事があると、お子さまは学校でも不安定になりやすくなってしまうのです。
一見学校とは関係のないように思える環境の変化が、学校への恐怖感につながることもあります。
学校が怖い理由がわからないときの対応

お子さまが「学校が怖い」と話しても、実際はその理由がはっきりとわからないことの方が多いかもしれません。
問いかけても黙り込んだり、「なんとなく」と答えたりすることもあるでしょう。
お子さまの年齢によっては、自分でも理由がわかっていないケースもあります。
しかし、理由が明確ではないからといって、無理に探ろうとすることは好ましくありません。
ここでは、学校が怖い理由がわからないときに意識したい、対応のポイントを解説します。
無理に理由を聞き出さない
お子さまが学校に対して恐怖を感じているときに、無理に理由を聞き出すのは好ましくありません。
本人が言葉にできる状態でない場合、繰り返し尋ねられることで心理的な負担が強まり、不安定な状態が長引く可能性もあります。
特に、お子さま自身も感情が整理できていない段階では、状況を説明すること自体が難しいため、理由を聞き出すよりも、落ち着いた状態で過ごすことが優先です。
時間の経過や日常の中で、少しずつ気持ちが整理されるのを待つことが適切な対応となる場合もあります。
怖いという感情を受け止める
お子さまが「学校が怖い」と感じている場合、その感情自体を否定せずに受け止めることが大切です。
理由がわからなくても、不安や恐怖といった感情は確かに存在しています。
まずは、それを尊重する姿勢を持つことが親子の信頼関係につながります。
保護者様が共感することで、お子さまの中に安心感が生まれ、結果的に心を開いてくれることがあります。
一方で、感情を軽視する言葉や反応は、お子さまの自信や安心感を損ない、対話のきっかけを遠ざけてしまいかねません。
学校が怖い理由ではなく、「今どう感じているのか」に注目して対応することが重要です。
日常の言動からヒントを探る
お子さまが言葉で理由を語らなくても、行動や反応の中に手がかりが隠れていることがあります。
特定の曜日や時間帯に気分が乗らなくなる、学校の話題になると反応が鈍くなるといった変化は、心理的ストレスのサインだと考えられます。
特に年齢が低いお子さまの場合、会話だけでなく遊びや絵、身体的な反応などにも感情が表れることがあります。
観察を重ねることで得られた気づきは、学校や支援機関との連携にも役立つでしょう。
学校が怖い子どもへの対応・サポート

学校を怖がるお子さまに対しては、気持ちを尊重しながら、少しずつ安心感を育てていく関わりが求められます。
頭ごなしに「行かないとダメ」と言ってしまうと、恐怖心が強まり、親子の信頼関係が損なわれてしまうこともあります。
ここでは、学校が怖い理由の有無や内容に関わらず、お子さまにできる対応やサポートについて紹介します。
問いかけ方を工夫する
お子さまが学校を怖がるとき、気持ちを理解するためには問いかけ方に工夫が必要です。
ストレートに「なぜ怖いの?」と聞いても、お子さまはうまく言葉にできないかもしれません。
お子さまの気持ちを引き出すには、答えやすい質問をすることが大切です。
たとえば「朝の時間がつらい?」「教室でどんな気持ちになる?」など、場面を想像しながら問いかけると、少しずつ反応が見られる場合があります。
また、お子さまの様子に合わせて、選択肢を示すような聞き方も有効です。
答えが返ってこないときも焦らず、無理に話を引き出そうとしないことが信頼関係の維持につながります。
共感の言葉を意識する
お子さまの話を聞く際には、共感的な言葉をかけることが重要です。
恐怖やつらさといった感情に対して適切に共感を示すことで、お子さまは自分の気持ちを理解してもらえたという安心感を得られます。
感情を受け止めてもらえる経験は、自己表現のハードルを下げ、心の安定にもつながります。
「問題ない」「みんな同じ」などの言葉は、比較や否定と受け取られる可能性があり、お子さまが本音を言いにくくなる原因になりかねません。
まずは評価や助言を急がず、感情そのものに丁寧に寄り添う姿勢が大切です。
安心できる環境を作る
家庭の中が安心できる場所であることは、外の世界に対する不安を和らげる上で大きな意味を持ちます。
お子さまが「ここにいれば大丈夫」と感じられる環境が整っていれば、不安や緊張を抱えながらも外に目を向ける力が育っていきます。
学校に対して距離をとりたがるお子さまでも、家庭が安全基地として機能していれば、少しずつ自分のペースで環境に慣れていける可能性があります。
反対に、家庭内に緊張感が続いているとお子さまの不安が強まることもあるため、保護者様自身がリラックスできる時間を意識的に持つことも重要です。
また、食事や睡眠などの基本的な生活習慣が整っていると、心にも余裕が生まれやすくなります。
家庭という居場所の安定は、お子さまの心の安定に直結しているのです。
無理に登校させない
学校に行けない状態のお子さまに対して、「無理にでも行かせよう」とする対応は逆効果になりやすいものです。
不安や恐怖を抱えたまま登校すると、かえって体調不良や精神的な不調を引き起こすこともあります。
登校をゴールにするのではなく、まずは気持ちを整える時間を尊重しましょう。
「行けない理由が分からない」と感じる場面でも、お子さま自身が苦しんでいることに変わりはありません。
休むこと自体に罪悪感を持たせず、安心して気持ちを話せる雰囲気作りを心がけることが大切です。
学校と連携する
学校との連携は、お子さまの状況に応じた柔軟な対応を検討していく上で欠かせません。
担任や学年の先生に、現在の様子やお子さまの気持ちを丁寧に共有できるとよいでしょう。
学校側と話し合うことで、登校時間の調整や教室以外での過ごし方など、個別の配慮を受けられる可能性があります。
スクールカウンセラーが在籍していれば、保護者様の相談にも応じてくれるため、心の負担を軽くすることが期待できます。
なお、学校へお子さまの様子を伝える際は、事前に「こういうことを先生に伝えてもいいかな?」と声をかけ、同意を得ることが大切です。
お子さまの意に反した対応は、大人への不信感につながってしまうことがあります。
お子さまのことで悩んだときは、すべてを家庭だけで抱えこまず、学校との連携を心がけましょう。
外部サポートを活用する
学校や家庭だけで対応が難しいと感じたときは、外部のサポートを取り入れることも一つの方法です。
たとえば、自治体の教育支援センター(適応指導教室)では、学校以外の場所で安心して過ごせる環境を提供しています。
また、医療機関では発達や心理の面からの支援を受けられる場合があります。
専門的な知識を持つスタッフが対応するため、保護者様の不安にも寄り添ってもらえるでしょう。
近年では、自宅で相談できる「不登校こころの相談室」のようなオンラインカウンセリングも、多くのご家庭に利用されています。
信頼できる第三者のサポートを受けることで、問題の整理が進み、親子ともに前向きな気持ちを取り戻せることがあります。
学校が怖いことに関するよくある質問(Q&A)

学校が「怖い」と感じているお子さまに接していると、保護者様自身も不安や疑問を抱くことがあるかもしれません。
最後に、学校が怖いことに関してよくある質問をもとに、学校への不安や不登校との関係について分かりやすく解説します。
学校が怖いのは不登校のはじまり?
お子さまが学校を「怖い」と感じている状況が続くと、「このまま休みがちになって不登校になるのでは」と心配になることもあるでしょう。
実際、学校への不安や恐怖が蓄積し、登校が難しくなるケースも少なくありません。
ただし、「怖い」という気持ちがすぐに不登校を意味するわけではありません。
大切なのは、今のお子さまの様子を受け止めて、親子で話しやすい空気を作ることです。
状況に応じて学校や外部の支援を受けながら、焦らず向き合っていくことが安心につながります。
学校を何日休むと不登校になる?
文部科学省によると、不登校は「病気や経済的理由以外で、年間30日以上欠席した場合」と定義されています。
ただし、数字だけで判断するのではなく、欠席の背景にある気持ちや体調を見極めることが重要です。
たとえ欠席日数が少なくても、強い不安が続いている場合には、適切なサポートが必要になることもあります。
「何日休んだら不登校」といった点を重視するよりも、お子さまの日々の様子や反応が重要です。
(参考:文部科学省 不登校の現状に関する認識)
学校が怖いと感じるお子さまに、どんな一歩を踏み出せばいい?

学校を「怖い」と感じる気持ちは、お子さまにとってとても切実なものです。
人間関係や学習の不安、生活の変化など背景はさまざまで、ときには理由がはっきりしないまま「行けない」と訴えることもあります。
保護者様としては、どう対応すればよいのか戸惑い、心配でいっぱいになるのは自然なことです。
「不登校こころの相談室」では、臨床心理士や公認心理師といった専門カウンセラーが、お子さまや保護者様の気持ちに寄り添いながら、安心できる形でサポートを行っています。
保護者様の心のケアを大切にしつつ、必要に応じて学校との連携も含め、無理のない方法で一歩ずつ支援を進めていきます。
さらに、最初の一歩としてAI診断をご用意しています。
数分で答えられるチェック形式で、お子さまの状態や保護者様の不安を整理するきっかけとなり、その結果をもとに最適なカウンセラーをご案内することも可能です。
「このまま一人で抱えて大丈夫だろうか」と感じた今こそ、まずはAI診断から始めてみてください。