目次
高校生の不登校はやばい?現状は?

高校生の不登校は決して珍しいことではなく、近年は増加傾向にあります。
文部科学省の調査によると、高等学校における不登校生徒は 約69,000人にのぼり、前年に比べると約8,000人以上増加しています。
また、不登校生徒のうち、約12,000人(17%程度)が中途退学に至っていることも明らかとなっています。
これらの数字は、中学生の不登校率(約6%)と比べると低い水準です。
高校生の不登校率が低い背景には、高校生は進学や就職に直結する年代であるため、不登校が「やばい」と感じられやすい傾向があると推察されます。
授業の遅れや単位不足が進級や卒業に影響する可能性があることも、不安を強める一因です。
とはいえ、このデータからは「同じように悩んでいる高校生が多い」という事実も読み取ることができますよね。
不登校は特別なことではなく、社会全体で支援が求められている問題です。
「自分だけがやばい状況にあるわけではない」と知ることが、安心感につながるでしょう。
(参考:文部科学省 令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 概要)
高校生の不登校がやばいとされる理由

高校生の不登校が「やばい」と言われるのは、学校生活や将来に直接影響する点が多いためです。
ここでは高校生の不登校がやばいとされる理由を、具体的に解説します。
授業についていけなくなる
不登校によって欠席が続くと、授業を理解することが難しくなります。
特に、数学や英語などの積み上げ型の科目は、一度学習が抜けると次の単元に進んだときに理解が追いつきにくい傾向があります。
勉強面での遅れが重なることで焦りが強まり、不登校を「やばい」と感じやすくなります。
留年や進級できない可能性が出てくる
高校では、出席日数や単位の修得が進級・卒業の条件となっています。
基準に届かなければ留年や退学につながる恐れがあり、その制度上の厳しさが不登校中の心理的な重荷となるケースは少なくありません。
周囲の友人が予定通りに進級していく中で、自分だけが取り残されるような感覚を抱くこともあるでしょう。
小・中学校とは違う、こうした現実味のあるリスクは、不登校を「やばい」と感じさせる大きな理由の一つです。
部活や行事に参加できなくなる
学校生活の楽しみは授業だけではありません。
部活動や文化祭、修学旅行といった行事は、仲間との絆を深める大切な機会です。
しかし、不登校が続くとそれらに参加できなくなり、学校が居場所であると感じにくくなってしまいます。
思い出づくりの機会を逃すことが孤独感を強め、学校からさらに距離を取るきっかけとなってしまうこともあります。
友人と疎遠になる
不登校になると、友人と顔を合わせる機会も少なくなります。
最初はSNSやメッセージでつながっていても、やり取りの頻度が落ちるにつれて関係が希薄になりがちです。
会話のきっかけを見失い、返信自体が負担に感じられる場合もあるでしょう。
その結果、友人関係への不安が強まり、教室に戻る勇気が出なくなることもあるのです。
友人関係の変化は、高校生活の中で大きなダメージになりやすいと言えます。
進学や就職の選択肢が狭まることがある
不登校は、進路に影響することがあります。
特に推薦入試では、出席状況や評定が重要視されるため、欠席が多いと受験資格を得られないこともあります。
就職活動においても、学校での出席状況をどう説明するかに悩み、自信を失ってしまうことがあります。
もちろん、不登校だからといって進路が完全に閉ざされるわけではありません。
通信制高校や高卒認定試験といった別の選択肢も存在します。
しかし、現状が整理できていない段階では「自分の将来が狭まってしまうのでは」と不安に駆られるお子さまが多数です。
家族や先生との関係がぎくしゃくすることがある
学校に行けない日が増えると、家庭や学校での関係にも影響が出てくることがあります。
保護者様の心配から出る言葉によって、口論に発展することも少なくありません。
また、先生とのやり取りでも、欠席連絡や課題の遅れを伝えるたびに気持ちが重くなり、やがて関係自体を避けようとするケースも見られます。
本来なら支えになるはずの存在が負担に変わると、不登校の長期化を招く恐れがあるため、注意が必要です。
生活リズムの乱れが定着する
不登校が続くと、夜更かしや昼夜逆転など、生活リズムが乱れやすくなります。
一度崩れた生活習慣を元に戻すのは簡単ではなく、体調の不安定さや気分の落ち込みにもつながってしまいます。
登校が難しい間も、できるだけ朝起きる時間や食事のタイミングを整えておくことが大切です。
生活リズムを守れなくなると、復学や社会参加のハードルがさらに高くなり、不登校が長期化してしまう恐れがあります。
精神面の悪化(うつ・不安障害のリスク)
不登校になると、「行かなければならないのに行けない」という葛藤や罪悪感から、強いストレスを抱えることがあります。
このような状態が続くと、うつ病や不安障害などの心の不調につながるケースも少なくありません。
精神的に追い込まれることで、日常生活に支障をきたしたり、将来への意欲を失ったりする危険があります。
心の健康を守るためにも、早めに周囲の大人や専門機関に相談することが重要です。
SNS・ネット依存のリスク
学校に行かなくなると、友人とのつながりがSNSやネットに偏りがちになります。
最初は気軽な交流でも、やり取りが増えるにつれて依存的になり、昼夜逆転や生活習慣の悪化につながることがあります。
また、SNS上でのトラブルや誹謗中傷が新たなストレスになるケースも見られます。
ネットの世界だけに居場所を求めてしまうと、現実での人間関係や学びの機会を失いやすくなるため、注意が必要です。
自己肯定感の低下
不登校が続くことで「自分は周りと違う」「何もできていない」と感じ、自己肯定感が下がってしまうことがあります。
この気持ちが強まると「どうせ頑張っても無駄」と将来に対して消極的になり、新しい挑戦を避けるようになることもあります。
一度下がった自己肯定感は回復に時間がかかるため、小さな成功体験を積み重ねるサポートが必要です。
周囲の理解や声かけによって「自分にもできることがある」と感じられる環境をつくることが大切です。
不登校に悩む高校生にできること

不登校の状況が続くと、「もう自分にはどうすることもできない」と思い込んでしまうことがあるかもしれませんね。
しかし、日常の中で小さな工夫を積み重ねるだけでも、気持ちや生活は少しずつ変化していきます。
ここでは、不登校になった高校生のお子さま本人が取り組みやすい対応を紹介します。
生活リズムや体調を整える
生活リズムを大きく崩さないことは、不登校の時期こそ気を付けたいことです。
夜更かしや昼夜逆転が続くと体調が不安定になり、気分の落ち込みが強くなります。
朝はできるだけ決まった時間に起きて朝食をとる、日中に軽く体を動かすなど、無理のない範囲で習慣を守りましょう。
体調が安定すると心も落ち着き、登校への不安と向き合うエネルギーを取り戻しやすくなります。
自分の気持ちを書き出してみる
悩みを抱え続けると、不安が膨らみやすくなります。
そのようなときは、ノートやスマートフォンに思ったことを書き出すことで、自分の感情を客観的に整理できます。
「今日は体が重かった」「友達に会いたいと思った」など、小さなことでも文字にしてみると気持ちが軽くなるものです。
たとえ表現が不十分でも、自分の心を外に出すこと自体が安心につながります。
趣味や好きなことを続ける
学校に行けていないときでも、好きなことを続けることは大切です。
音楽を聴く、絵を描く、読書をするなど、自分なりに楽しめることを持つと気分の切り替えにつながります。
また、趣味を通じて新しい知識やスキルを得られることもあり、それが自信を取り戻すきっかけになることもあります。
「何もしていない」と思い込まず、好きなことを大切にする時間を持ち続けましょう。
信頼できる大人に相談する
一人で悩みを抱え込むことは、やがて大きな負担となります。
悩んだときは、保護者様や先生、スクールカウンセラーなど、信頼できる大人に相談することも重要な対応法です。
直接話すのが難しければ、手紙やメッセージで伝えても構いません。
うまく言葉にできなくても、受け止めてもらえるだけで気持ちが軽くなります。
学校以外での学びの場や学び方を探す
学びの方法は「学校に通うこと」だけではありません。
現在では、通信制高校やフリースクール、オンライン学習など、多様な選択肢があります。
自分に合った学び方を見つけることができれば、「学びを止めていない」という自信につながることでしょう。
どのようなスタイルであっても、学びを継続することは、将来を考える上でも大切なものとなります。
「学校に戻れるかどうか」だけにとらわれず、幅広い学びの形を検討することが、不安をやわらげるきっかけとなるはずです。
なお、こちらの記事では、高校生の不登校の原因や回復までのプロセスについてさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

高校生の不登校について|6つの主な原因と親が知っておきたい接し方
高校生になって、お子さまが「学校に行きたくない」と言い出したとき、多くの保護者様は戸惑いや不安を感じるのではないでしょうか。「何が原因なんだろう?」といった疑問を持ちながらどう対応すべきか悩んでいる方...
続きを見る
不登校の高校生の親にできる対応

不登校は、お子さま本人だけでなく、保護者様にとっても大きな問題となるものです。
どう接してよいか分からず、つい叱ったり焦ったりしてしまうこともあるでしょう。
ここでは、高校生のお子さまが不登校になったときに、保護者様にできる対応を紹介します。
気持ちを否定せず受け止める
まず意識したいのは、お子さまの気持ちを否定しないことです。
「どうして行けないの?」といった言葉は、本人を追い込んでしまう原因になります。
保護者様には、不登校の原因がはっきり分からなくても、お子さまごと受け止める姿勢が求められます。
お子さまは、保護者様に理解してもらえていると感じることで、安心感を得ることができます。
環境を整える
不登校問題では、登校再開だけに焦点を当てるのではなく、まずは家庭が安心して過ごせる場所になることが大切です。
たとえば、生活リズムを一緒に整えたり、学びの方法を柔軟に探したりすることも有効でしょう。
家族にとって負担となることをする必要はなく、部屋を落ち着ける空間に整える、食事や睡眠をサポートするなど、小さな工夫がお子さまの安心につながります。
家庭が安全な居場所だと感じられることは、心の回復に向けた大きな力になります。
焦らず見守る
不登校からの回復には、時間がかかるものです。
保護者様としては「早く学校に戻ってほしい」と焦る気持ちが自然に湧いてくるかもしれませんが、その思いを強く伝えすぎると、かえってお子さまを追い込んでしまうことがあります。
お子さまの小さな変化を認めながら、焦らず見守る姿勢が必要です。
日常の些細な声かけや雑談が、お子さまの安心感と自信を少しずつ育んでいきます。
不登校は、長期的な視点で支えることが大切です。
学校や外部機関と協力する
お子さまの不登校問題は、保護者様だけで抱え込む必要はありません。
担任の先生やスクールカウンセラー、地域の相談機関など、利用できる支援先は数多くあります。
また、学校に相談するのが難しいと感じる場合、「不登校こころの相談室」のような外部サポートを受けることで、お子さまの状況を客観的に整理できたり、新たな対応法に出会えたりすることがあります。
なお、こちらの記事では、不登校の高校に有効なカウンセリングについて詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

不登校の高校生に必要なカウンセリングとは?|親が知っておきたいポイント
「最近、子どもが学校に行きたがらない」「何を考えているのかわからなくて不安」といった悩みを抱えていませんか?思春期特有の繊細な心の動きに、どう寄り添えばいいのか迷う保護者様も多いのではないでしょうか。...
続きを見る
高校生が不登校になったときの将来の選択肢
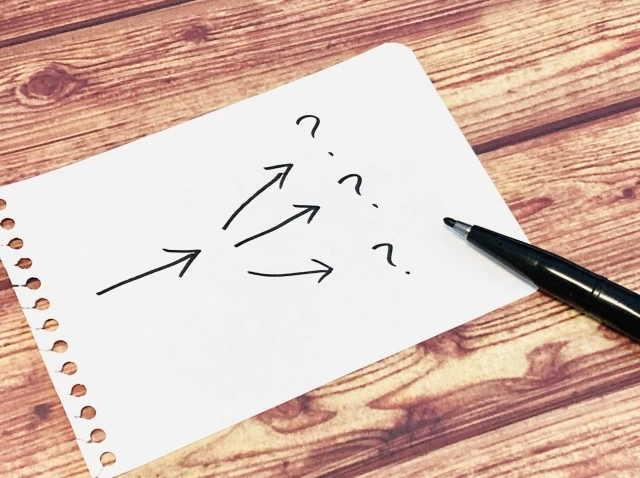
高校生で不登校になったからといって、将来の可能性が閉ざされるわけではありません。
近年は学び方や進路の幅が広がっており、学校に通い続けることが難しい場合でも新しい道を選ぶことができます。
ここでは、高校生が不登校になったときの具体的な将来の選択肢を紹介します。
通信制高校・定時制高校に編入する
現在の高校に通うのが難しいときは、通信制高校や定時制高校に編入するという方法があります。
通信制高校は、レポートやスクーリングを中心に、自分のペースで学びを進められるのが特徴です。
また定時制高校では、夜間や昼間のコースがあり、生活スタイルや体調に合わせて通いやすい環境を選ぶことができます。
どちらも高校卒業資格を得られるため、大学や専門学校への進学、就職につなげることが可能です。
高卒認定試験を受けて進学する
高校に在籍し続けることが難しくても、高卒認定試験に合格すれば大学や専門学校への進学資格を得ることができます。
合格に向けて、独学や通信講座、予備校など、勉強の方法を自由に選べるのも特徴です。
不登校に悩むお子さまにとって、高校を卒業する以外にも道があると知ることは、前向きに人生を歩んでいくためのきっかけとなるでしょう。
社会復帰を目指す
不登校になったからといって、必ずしも高校卒業にこだわる必要はありません。
アルバイトや就労支援を通じて社会とつながる経験も、将来を考える上では大きな財産となります。
働く中で新しい人間関係や役割を持つことで自信が芽生え、「もう一度学びたい」と思うこともあるかもしれません。
不登校の経験を経ても、社会との関わりを通して自分の可能性を広げていくことは、十分可能です。
高校生の不登校がやばいと感じるときは「不登校こころの相談室」へ

高校生の不登校は「やばい」と言われがちですが、その背景には学習の遅れや友人関係の変化、進路の心配など、いくつもの要素が重なっていることがあります。
高校生で不登校になると、義務教育期間ではないからこそ、将来に不安を抱きやすいかもしれません。
しかし、不登校そのものが将来を閉ざすわけではありません。
学び方や進路は多様に存在するため、家庭での関わり方や相談先の活用によって状況を変えていくことができるでしょう。
高校生の不登校の悩みは、安心して話せる場があることで気持ちを整理しやすくなります。「不登校こころの相談室」では、高校生や保護者様の気持ちに寄り添い、専門的なカウンセリングを提供しています。
まずは無料のAI診断から、自分に合ったサポートの方向性を知ることも可能です。
不登校は「やばい」と一人で抱え込む必要はありません。
お子さまの希望に沿った対応を、一緒に探していきましょう。

















