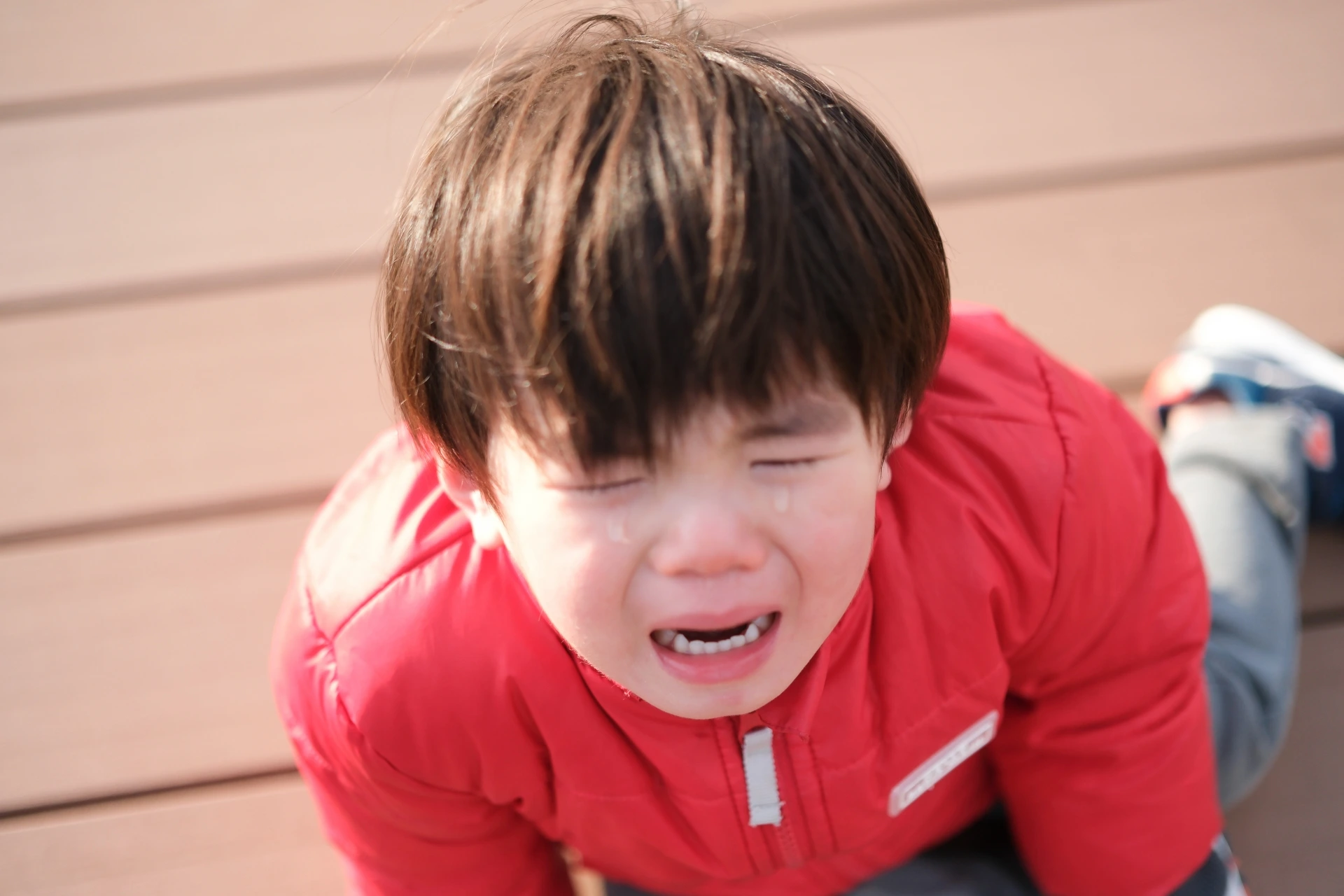目次
自己肯定感が低い子どもの特徴

自己肯定感が低いお子さまには、行動や言葉に共通する特徴が見られます。
これらを早めに捉えることで、適切なサポートにつなげやすくなります。
以下の特徴に当てはまる場合は、注意深く見守りながら関わり方を工夫していきましょう。
挑戦を避ける
自己肯定感が低いお子さまは、新しいことに取り組むとき、失敗への不安から最初の一歩を踏み出せないことがあります。
授業での発表や運動会の競技など、本来なら楽しめる場面でも「やらないほうが安心」と考えて挑戦を避けてしまうのです。
こうした行動が続くと、「自分にはできない」という思い込みが強まり、さらに自信を失いやすくなります。
人と比べてすぐに諦める
多くのお子さまは努力の過程で自分の成長を実感しますが、自己肯定感が低い場合、周囲との比較が中心になってしまいます。
友達や兄弟姉妹に劣っていると感じると「どうせ無理だ」と早々に諦める傾向があり、努力を積み重ねる機会を自ら手放してしまうことがあります。
自分を否定する
否定的な言葉が口癖になるのも、自己肯定感が低いお子さまに見られがちな特徴です。
「自分なんてダメだ」「どうせできない」と繰り返すうちに、その思い込みが強まり、自己評価をさらに下げる悪循環に陥ります。
保護者様が声をかけても前向きに受け取れないこともあり、関わり方に工夫が必要です。
失敗や間違いを過度に恐れる
一部のお子さまは、失敗や間違いを「自分の価値が下がること」と結びつけて考えます。
テストや発表を前に過度の緊張を訴えたり、体調を崩したりするケースもあります。
失敗を経験の一部として受け止められないと、挑戦のハードルはますます高くなり、自己肯定感の低下につながってしまいます。
周囲の評価や反応を気にしすぎる
周囲の目を過剰に気にするのも、自己肯定感が低いお子さまに多い傾向です。
「笑われないか」「注意されないか」と心配するあまり、自分の意見や気持ちを抑えてしまうのです。
人からの評価を行動基準にし続けると、「認められない自分には意味がない」という思い込みにつながり、自由に自己表現する力が弱まります。
自己肯定感が低い子どものリスク

自己肯定感が低い状態を放置すると、日常生活だけでなく将来にも影響が及ぶ恐れがあります。
ここでは、自己肯定感が低いお子さまに想定される、代表的なリスクを解説します。
不登校につながりやすい
自己肯定感が低いお子さまは、「学校に行っても自分には価値がない」と感じやすく、登校への意欲を失うことがあります。
小さな失敗や友人とのすれ違いをきっかけに「どうせ自分には無理だ」と思い込み、学校生活そのものを避けるようになるケースも少なくありません。
文部科学省が行った調査でも、不登校の背景には「無気力・不安」といった心理的要因が多く挙げられており、自己肯定感の低さと深く関わる可能性が示されています。
放置すれば学習の遅れや孤立感の増加につながり、長期的な不登校へ発展する恐れがあるため、注意が必要です。
(参考:公益社団法人 子どもの発達科学研究所 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター 文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究報告書)
友人関係に悩みやすい
友達とのやり取りにおいても、自己肯定感が低いお子さまは「嫌われるのではないか」と過度に不安を抱く傾向があります。
その結果、相手に合わせすぎて自分を出せなくなったり、反対に関わりを避けたりすることがあります。
こうした行動が続くと孤立やトラブルにつながり、友人関係に悩みやすくなります。
健全な人間関係を築く力が弱まることは、将来的な社会生活にも影響を及ぼすでしょう。
将来の選択肢が狭まる
自己肯定感が低いお子さまは、「自分にはできない」と思い込むあまり、進学や進路の選択で本来の力を発揮できる道を選ばないことがあります。
たとえば挑戦的な進学先や希望する職業を避け、安全策ばかりを選ぶケースもあります。
選択肢を自ら狭めることは、その後の人生の満足度を下げる要因になりかねません。
自分の可能性を信じられない状態が続けば、将来の展望そのものが閉ざされる恐れがあるといえるでしょう。
子どもの自己肯定感が低い理由

自己肯定感が低くなる背景には、家庭や学校など日常生活のさまざまな要素が関わっています。
ここでは、お子さまの自己肯定感が低くなる代表的な理由を見ていきましょう。
家庭で否定的な言葉をかけられている
自己肯定感が低いお子さまは、家庭での声かけに大きな影響を受けています。
「どうしてできないの」といった否定的な言葉が繰り返されると、「自分は認められていない」と感じやすくなります。
保護者様としては励ましのつもりでも、受け止め方次第では否定のメッセージになってしまうのです。
こうしたやりとりが続くと、自己肯定感の低下につながる恐れがあります。
ちょっとした言葉の選び方が、お子さまの心に大きく影響を与えることもあるのです。
学校や友人関係でつまずいている
学校生活や友人との関わりも、自己肯定感に直結する大きな要因です。
授業でうまく発表できなかった経験や、友達から仲間外れにされた出来事が心に残り、「自分には価値がない」という思い込みにつながることがあります。
学校は生活の大半を占める場であるため、そこでのつまずきは影響が大きく、自己評価を下げる原因となる場合があります。
気質や発達特性に影響を受けている
自己肯定感が低くなりやすいのは、環境だけが原因ではありません。
生まれ持った気質や発達特性によって、不安が強い、慎重すぎるといった特徴が表れやすいお子さまもいます。
こうした特性があると「やっぱり自分には無理だ」と考えやすくなり、挑戦する前に諦めてしまうことがあります。
気質そのものは変えられませんが、特性を理解したうえで、得意を伸ばす視点を持つことが大切です。
また、発達障害などが背景にある場合、自己肯定感の低さや不安から不登校・抑うつなど別の困難が生じることもあり、これは「二次障害」と呼ばれています。
早めに気づき、適切に支援することが予防につながります。
社会全体の価値観に振り回されている
社会が持つ価値観も、お子さまの自己肯定感に大きな影響を与えます。
学力や成績が重視される風潮の中で「点数が低い=自分の価値が低い」と感じるお子さまは少なくありません。
さらに、SNSを通じて同年代の成功や華やかな生活と比較することで「自分は劣っている」と落ち込みやすくなります。
社会全体の価値観に振り回される状況が続けば、自己肯定感を支える土台が揺らいでしまうでしょう。
自己肯定感が低い子どもに家庭でできる関わり方

自己肯定感が低い状態を改善するには、家庭での接し方が大きな鍵となります。
保護者様の言葉や態度はお子さまに直接影響するため、日常の中でできる工夫を意識して取り入れることが大切です。
否定せず受け止める
自己肯定感が低いお子さまは、「どうせできない」といった否定的な言葉を口にすることがあります。
そのようなときは頭ごなしに否定するのではなく、まず受け止めることが大切です。
気持ちを認めてもらえた安心感は、自分を肯定する力につながります。
否定せずに耳を傾ける姿勢は、信頼関係を深める土台になるでしょう。
小さな成功体験を積ませる
日常の中で達成できる小さな目標を設定し、成功体験を積ませることも有効です。
たとえば「今日は宿題を10分やる」「料理を手伝う」など、無理なくできる範囲で取り組ませることで「できた」という実感を得られます。
こうした経験が積み重なると、自信が芽生え、自己肯定感を育てる基盤となるでしょう。
成功を喜ぶときには、結果だけでなく「がんばった過程」も褒めると、一層お子さまの自信につながります。
人と比べない
自己肯定感が低いお子さまは、周囲との比較で自分を評価しがちです。
保護者様が「〇〇はできるのに」といった言葉をかけると、その傾向を強めてしまいます。
比べるのではなく「昨日よりできるようになったね」と本人の成長に注目することで、お子さまは自分自身を前向きに捉えやすくなります。
他人基準ではなく、自分基準で評価する視点を持たせることが大切です。
また、兄弟や友人と違う得意分野を見つけられるようにサポートするのも効果的です。
保護者自身の気持ちを整える
家庭での関わりには、保護者様自身の心の余裕も影響します。
忙しさや不安から苛立ちが募ると、つい厳しい言葉を投げかけてしまうこともありますよね。
自己肯定感を支えるためには、まず保護者様が気持ちを整えることも欠かせません。
ときにはリフレッシュする時間を確保し、心に余裕を持つことがお子さまを安心させる環境づくりにつながります。
また、悩みを専門家に相談することで、保護者様自身の心も軽くなり、より穏やかな関わりができるようになるでしょう。
カウンセリングを活用すれば、安心して気持ちを整理できる時間が持てるため、保護者様の心の安定にも役立ちます。
子どもの自己肯定感を支える外部サポート

家庭での関わりは大切ですが、それだけでは十分に支えきれないこともあります。
そのようなときに頼れるのが、学校や地域、専門機関による外部サポートです。
周囲の力を借りることで、保護者様とお子さまが安心して過ごせる環境を整えることができます。
学校でのサポート
学校はお子さまが日常の多くを過ごす場であり、自己肯定感を育む重要な役割を担っています。
担任の先生やスクールカウンセラーに相談すれば、学習面や友人関係のサポートを受けられる場合があります。
家庭と学校が連携することで、よりきめ細やかな支援が可能になるでしょう。
行政や地域の相談窓口
地域には、子育て支援センターや教育相談室など、保護者様が気軽に相談できる窓口が用意されています。
専門的なスタッフに話すことで、悩みを整理し具体的な支援策を紹介してもらえることがあります。
行政や地域の支援は費用の負担が少ないことも多く、継続して利用しやすい点が特徴です。外部の第三者に相談するだけでも、気持ちが軽くなる保護者様は少なくありません。
医療機関やカウンセリング
お子さまの自己肯定感の低さが強く表れているときや、不安や抑うつの症状が続くときには、医療機関やカウンセリングの利用を検討することが大切です。
小児科や児童精神科では専門的な診断や治療を受けることができ、カウンセリングでは気持ちを整理しながら前向きに過ごす方法を一緒に考えていけます。
カウンセリングのよさは、安心して本音を話せる「安全な場」が得られる点にあります。
家庭では言いづらい思いや不安を表現することで、気持ちが軽くなり、新しい視点を得られることも少なくありません。
また、専門家の客観的な視点が入ることで、保護者様が気づけなかったお子さまの強みや可能性に目を向けられることもあります。
専門家のサポートを受けることで、保護者様も安心してお子さまに関わることができるようになるでしょう。
子どもの自己肯定感に悩んだときは「不登校こころの相談室」へ

自己肯定感の低さは、放っておくと学習意欲の低下や友人関係の不安、不登校といった形で表れることがあります。
早めに気づき、家庭や外部のサポートを取り入れることで、少しずつ前向きな気持ちを取り戻すことができるとよいでしょう。
「不登校こころの相談室」では、臨床心理士など専門性を持つカウンセラーがオンラインで相談をお受けしています。
自宅から利用できるため、移動の負担がなく、安心して継続できる点が特長です。
お子さまの気持ちを丁寧に整理しながら、保護者様と一緒に適切な関わり方を考えていくサポートを行っています。
まずは、無料で受けられるAI診断から、お子さまの状況や保護者様の悩みに合わせたサポート方針を確認することができます。
診断結果をもとに、最適なカウンセラーとつながることが可能です。
お子さまの自己肯定感の低さに不安を抱いたときは、保護者様だけで抱え込まず、一度「不登校こころの相談室」にご相談ください。