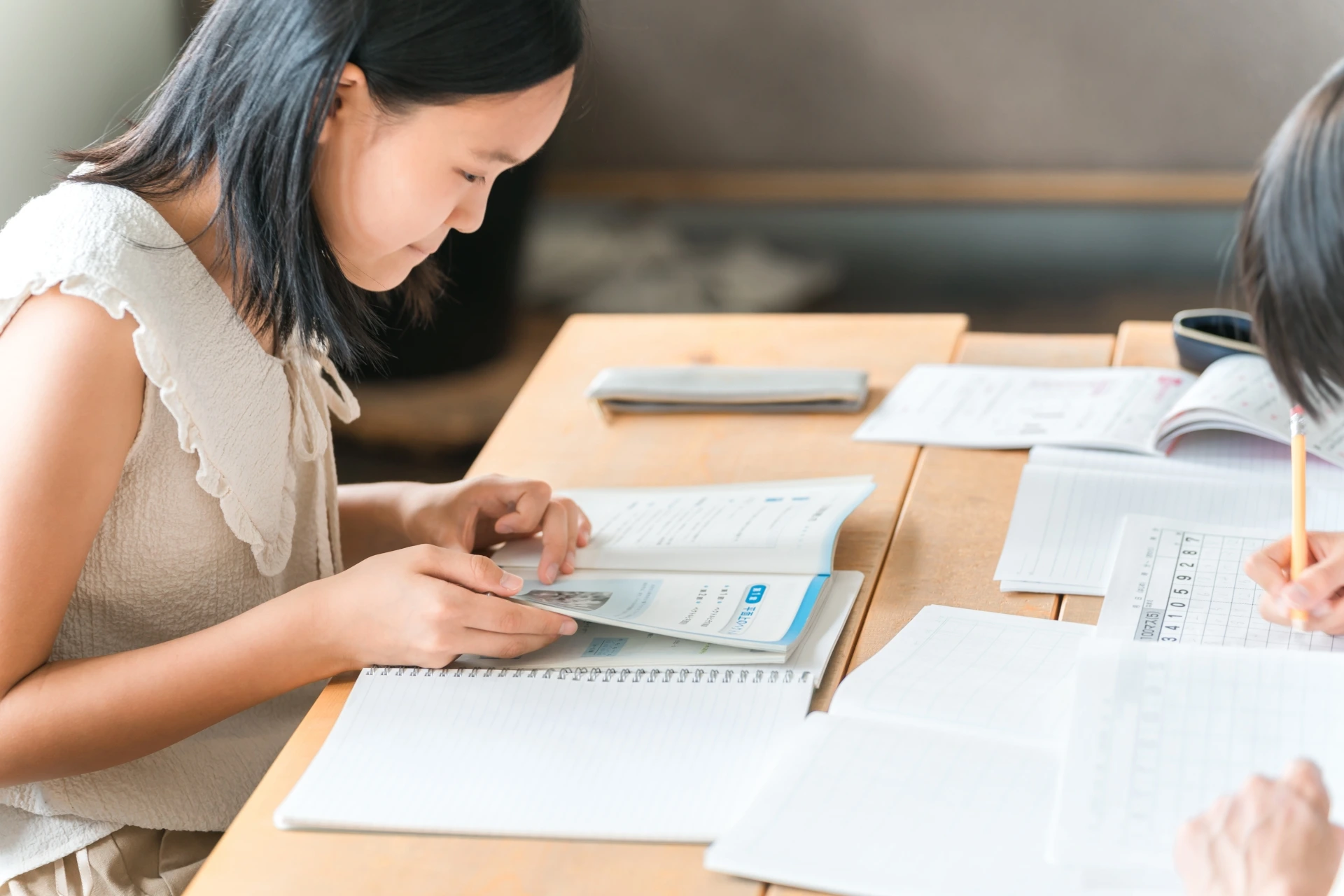目次
不登校の中学生と進路の現状

文部科学省の調査によると、中学生の不登校は年々増加しており、令和5年度には約22万人の生徒が不登校であると報告されています。
しかし近年では、不登校の増加に伴い、高校進学をめぐる進路選択にも変化が見られます。
従来は全日制高校が一般的でしたが、現在は定時制・通信制高校やフリースクールなど、多様な学びの場が整備されているのが特徴です。
教育委員会や学校側も、不登校の生徒を受け入れるために面接や作文を重視する入試方式を導入するなど、柔軟な対応を広げています。
不登校の中学生にとって、進路選択には多くの課題があることは事実ですが、多様な選択肢を前に、悲観的になりすぎる必要はありません。
「不登校だから進路が限られる」と思い込まず、お子さまに合った学び方や制度を調べて選べるとよいでしょう。
(参考:文部科学省 令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 概要)
不登校の中学生が抱えやすい悩み
.webp)
中学生で不登校になると、保護者様やお子さまは進路について多くの悩みを抱えやすくなります。
多くのお子さまは高校進学を控えた時期であるため、学習面や人間関係、将来に関わる不安が重なりやすいのが特徴です。
ここでは、不登校の中学生が直面しやすい代表的な悩みを整理します。
学力の低下や勉強の遅れ
不登校期間が長期化するにつれ、授業の遅れへの不安は増大します。
実際、出席日数や課題の提出は内申点にも関わるため、学力面の悩みは切実です。
一方で、家庭学習や塾、通信教材を活用するなど、学校以外の学び方で学力低下をカバーする方法もあります。
学習の遅れが心配なときは「どこから取り組めばよいか」を明確にすることが、解決に向けた最初の一歩となるでしょう。
人間関係や学校生活への不安
不登校の背景には、人間関係の問題があるケースも多く見られます。
クラスでの孤立や友人関係のトラブル、いじめなどが原因となり、再び登校すること自体に強い不安を感じることもあります。
進路を考えるうえでも、人間関係に再び悩まされるのではないかという懸念が大きなハードルになるのです。
意欲や自信の低下
学校に行けない状態が続くと、自分への評価が下がり「どうせ自分なんて」という気持ちを持ちやすくなります。
このようなときには、学力や出席日数だけでなく、お子さま本人が安心できる環境を整えることが重要です。
小さな成功体験を積むことが、自信を少しずつ取り戻すきっかけになります。
将来への不安
中学生にとって、高校進学は大きな分岐点です。
不登校が続くことで「このまま高校に行けないのでは」「将来の選択肢が狭まるのでは」といった不安が強くなります。
しかし、進学先は全日制高校に限らず、定時制や通信制、高卒認定試験の受験といった道もあります。
進路は一つではないと知ることが、不安を和らげる助けとなるでしょう。
不登校の中学生に想定される進路
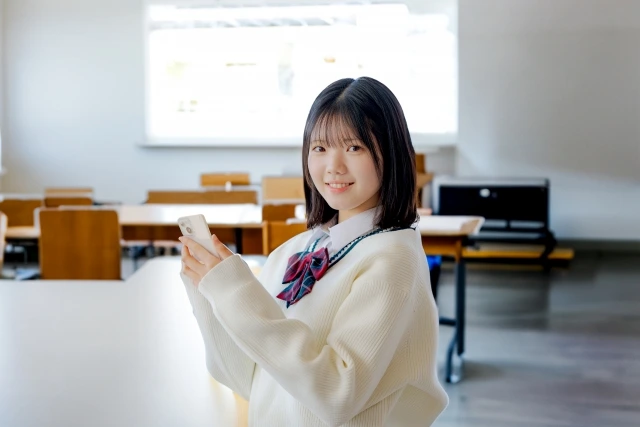
不登校の中学生の進路は、一つではありません。
高校への進学のほか、多様な選択肢が存在します。
ここでは、具体的な進路の選択肢と、それぞれの特徴やメリット・注意点を解説します。
全日制高校
中学生の最も一般的な進学先は、全日制高校です。
全日制高校に進学するためには、出席日数や内申点が選考に影響するため、不登校期間が長い場合はハードルが高く感じられることもあります。
ただし、近年では面接や作文などを重視する学校もあり、必ずしも学力だけで判断されるわけではありません。
学校によっては、不登校経験のある生徒への理解が進んでいるケースもあります。
定時制高校
夕方や夜に授業が行われる定時制高校は、出席スタイルに柔軟性があります。
日中にアルバイトや別の活動をしながら通えるため、自分のペースで学びたいお子さまに向いています。
一方で、通学時間帯が遅くなることや学習期間が長めになる点を考慮する必要があります。
通信制高校
通信制高校では、レポート提出やスクーリング(登校日)を組み合わせて学ぶことが一般的です。
自宅中心で学習を進められるため、体調や気持ちの波があるお子さまでも続けやすい傾向にあります。
最近ではオンライン授業やサポート校と連携した学習環境も増えており、柔軟な進学先の一つとして注目されています。
特別支援学校
特別支援学校は、知的障害や発達障害、肢体不自由、病弱といった特性があり、特別な支援を必要とするお子さまのための学校です。
対象になるかどうかは、教育委員会の就学相談や専門機関の判定によって決まります。
療育手帳や障害者手帳が必須というわけではありませんが、医師の診断や意見書が必要になる場合があります。
授業では基礎的な学習だけでなく、生活面や社会で役立つスキルを身につけることにも重点が置かれています。
専門の教員や支援員が配置されているため、安心して学べる環境が整っており、お子さまの特性に合わせた成長を支えることができます。
卒業後は進学や就職につながる進路もあり、将来を見据えて支援を受けられるのが特徴です。
フリースクール
学校以外の居場所として、フリースクールを利用するケースもあります。
学習支援を受けられる場所もあれば、安心できる人間関係づくりに重点を置いた居場所型のスクールもあり、種類はさまざまです。
フリースクールに通うだけでは、正式な学歴(高卒)としては認められません。
しかし、その後の高校進学や高卒認定試験に挑戦する際の準備としては、大きな意味を持つでしょう。
勉強の基盤を整えたり、気持ちを前向きにしたりする場として活用できるのが大きな特徴です。
高卒認定試験の受験
高校に進学せずとも、高卒認定試験(高認)に合格すれば「高校卒業と同等の学力がある」と認められます。
これによって、大学や専門学校への進学が可能になり、学歴の面で将来の選択肢が広がります。
独学での挑戦は困難なことも多いですが、予備校や通信講座を利用して受験する生徒も増えています。
就職
中学卒業後に就職する道もあります。
すぐに働き始めたいと考える場合や、家庭の事情で進学が難しい場合に選ばれることがあります。
ただし、中卒での就職は職種が限られるため、将来的には転職やキャリア形成に不安が残ることもあります。
そのため、職業訓練校や資格取得を経て働く道を選ぶ人もいるのが現状です。
不登校の中学生が進路を選ぶときのポイント

進路を決める場面では、学力や制度だけでなく、お子さまの体調や気持ちを含めた総合的な判断が必要です。
保護者様としては「とにかく高校に行かせなければ」と焦ってしまうこともありますが、無理に進学を急ぐと再び不登校が長引く可能性もあります。
ここでは、不登校の中学生の進路選択において大切にしたいポイントを解説します。
子どもの体調や意向を尊重する
まず大切なのは、お子さまの体調や気持ちを軽視しないことです。
たとえ学力的に合格できる学校があったとしても、毎日通うことが難しい状況であれば現実的ではありません。
お子さま本人の声を聞きながら「どんな環境なら通えそうか」を一緒に考えていきましょう。
子どもに合った進路を探す
全日制・定時制・通信制など、それぞれの進路先には特色があります。
たとえば、規則正しい生活を取り戻したいなら全日制、ゆっくり学びたいなら定時制や通信制、といったように特性に応じた選び方ができます。
通信制高校の場合、同じような境遇のお子さまに出会いやすいのも特徴です。
学力だけでなく、生活リズムや人間関係への安心感なども含めて「合うかどうか」を見極めることが大切です。
受験資格や入試制度を調べておく
不登校が続いた場合に気になるのが、受験資格や出席日数、内申点の扱いですよね。
高校によっては、中学校での出席日数を重視するところもあれば、面接や作文を中心に評価するところもあります。
一部の地域では、不登校経験者を対象にした特別枠入試が設けられている場合もあります。
こうした制度を早めに把握しておくことで、進路選びの幅が広がります。
学校に相談する
不登校のお子さまが進路を考えるときは、学校に相談することが欠かせません。
学校は出席状況や成績のデータを持っており、進路に関する最新の情報も得ることができます。
家庭だけで判断せず、学校と協力して方針を考えることで、選択肢が明確になるでしょう。
進路に悩む不登校中学生への家庭での関わり方

進路の話題はお子さまにとって大きなプレッシャーになりやすく、保護者様の声かけ一つで受け止め方が変わることもあります。
正解が決まっているわけではありませんが、家庭での関わり方を工夫することで、お子さまの安心感や自信につながるでしょう。
ここでは、進路に悩む中学生のお子さまへの、家庭での関わり方を紹介します。
焦らず見守る
「卒業後の進路をきちんと決めなければ」という気持ちは自然なものですが、焦りをそのままお子さまにぶつけると、余計に不安を強めてしまいます。
まずは焦らず見守り、進路の話題は様子を見ながら話せるとよいでしょう。
子どもを責めないよう注意する
不登校の状態に対して「怠けている」「努力が足りない」といった言葉をかけるのは逆効果です。
責められたと感じると心を閉ざしてしまい、進路の話がさらに進みにくくなります。
お子さまを頭ごなしに否定せず、本音や意向を聞き出す姿勢が大切です。
親子で話し合う時間を設ける
進路を考えるときは、本人の気持ちを引き出すことが欠かせません。
食事のときや外出の合間など、自然に話せる時間を持つことで本心を語りやすくなります。
保護者様が意見を押しつけるのではなく、一緒に選択肢を整理していく姿勢が信頼関係を深めることにもつながります。
親も休息の時間を持つ
不登校に向き合っていると、保護者様も無意識のうちにストレスが溜まってしまいます。
常にお子さまのことを考えていると疲れが蓄積し、気づかないうちに余裕をなくしてしまうこともあるかもしれません。
友人に話を聞いてもらったり、趣味の時間を持ったりするなど、保護者様の心を休めることも忘れないようにしましょう。
不登校の中学生が進路に悩んだときの支援先

不登校の中学生の進路を家庭だけで考えるのは、大きな負担になることがあります。
そのようなときは、信頼できる支援先とつながることで進路の選択肢を広げられるだけでなく、安心感を得ることができます。
ここでは、不登校の中学生が進路に悩んだときの支援先を紹介します。
学校
最も身近な相談先は、在籍している中学校です。
担任の先生や進路指導の先生は、受験に関する最新の制度も把握しています。
また、スクールカウンセラーに相談することで、進路選択に関わる心理的な不安を和らげるサポートも受けることができます。
教育支援センター(適応指導教室)
教育委員会が設置する教育支援センター(適応指導教室)は、不登校のお子さまを対象にした学習や生活支援を行う場です。
通うことで学習習慣を維持できたり、集団生活の感覚を少しずつ取り戻したりすることができます。
また多くの場合、利用することで学校出席扱いとみなされます。
進路相談にも応じており、地域の高校や支援機関とつながるきっかけにもなります。
フリースクール
フリースクールは、学校以外の学びや居場所として利用される場です。
上記でも解説したように、過ごし方や特徴は施設によってさまざまです。
フリースクールには同じような境遇のお子さまが多く通っており、同年代のお子さまとの交流を通して、対人関係への不安を軽減させることが期待できます。
そうした心のケアが、進路を考える際の自信につながることがあります。
外部の相談機関・カウンセリング
不登校問題では、お子さまだけでなく保護者様も大きな負担を抱えやすくなります。
繊細で複雑な問題であるがゆえに、気軽に誰かに話すことが難しい場合もあるでしょう。
家庭内で解決するには負担が大きすぎると感じるときは、外部の相談先を活用するのも一つの方法です。
「不登校こころの相談室」では、保護者様自身の気持ちを整理するサポートも行っており、安心して話せる場として利用できます。
不登校の中学生の進路に関するよくある疑問(Q&A)

不登校の中学生が進路を考えるとき、お子さまや保護者様が感じやすい疑問がいくつかあります。
ここでは特に気になるものを取り上げ、分かりやすく解説します。
内申点の基準は?不登校だとどうなる?
内申点は、出席日数や授業態度、提出物などを含めた総合評価で決まります。
不登校が続くと欠席日数が多くなり、内申点が下がる可能性はあります。
ただし、学校によっては出席日数だけで判断せず、提出物やテストの結果を考慮する場合もあります。
また、高校によっては内申点よりも面接や作文、小論文などを重視するところもあります。
必ずしも内申点だけが進路を決める基準ではないため、具体的な評価方法については学校に確認しておくことが大切です。
高校入試に「不登校枠」はある?
一部の地域や学校では、不登校経験のある生徒を対象にした特別な選抜枠を設けている場合があります。
これは、学力試験の結果だけでなく、面接や作文を重視する方式が多いのが特徴です。
ただし、すべての地域や学校に制度があるわけではありません。
利用できるかどうかは地域や年度によって異なるため、教育委員会や学校に確認してみましょう。
不登校になると将来どうなる?
「不登校になったら将来が閉ざされてしまうのでは」と不安に思う保護者様は少なくありません。
しかし実際には、進路は全日制高校だけに限らず、定時制や通信制、高卒認定試験など幅広く用意されています。
不登校を経験しながらも大学進学や就職に至っている人も多く、不登校経験そのものが将来を決定づけるわけではありません。
大切なのは「不登校だから選択肢が狭まる」と思い込まず、お子さまに合った道を一緒に探していくことです。
不登校の経験を通じて得られる気づきや成長が、将来に生きる場合もあります。
それでも将来への不安が強く、家庭では抱えきれないと感じるときは、外部の専門家に話してみるのも有効です。
「不登校こころの相談室」では、進路や将来に悩む保護者様やお子さまの気持ちを支えるサポートも行っています。
不登校の中学生の進路に関する悩みは「不登校こころの相談室」へ

中学生のお子さまが不登校になると、学力や内申点、将来の見通しなど、多くの不安を抱えやすいものです。
しかし、進路の選択肢は全日制高校だけでなく、定時制・通信制・特別支援学校や高卒認定試験、フリースクール、就職など幅広く存在します。
お子さまに合った道を、お子さまと一緒に探し、希望をもって進める進路先を検討していけるとよいでしょう。
とはいえ、その過程を保護者様だけで担うのは心身の負担が大きく、迷いや不安が尽きない場合もあります。
そのようなときは、専門家のサポートを取り入れてみてください。
「不登校こころの相談室」には、臨床心理士や公認心理師などの専門カウンセラーが在籍し、お子さまや保護者様の気持ちを整理しながら、進路や生活に関する不安に寄り添っていくことが可能です。
まずは無料で利用できるAI診断から、サポートの方向性を見つけることもできます。
不登校の中学生の進路に悩んだときは、ぜひご相談くださいね。