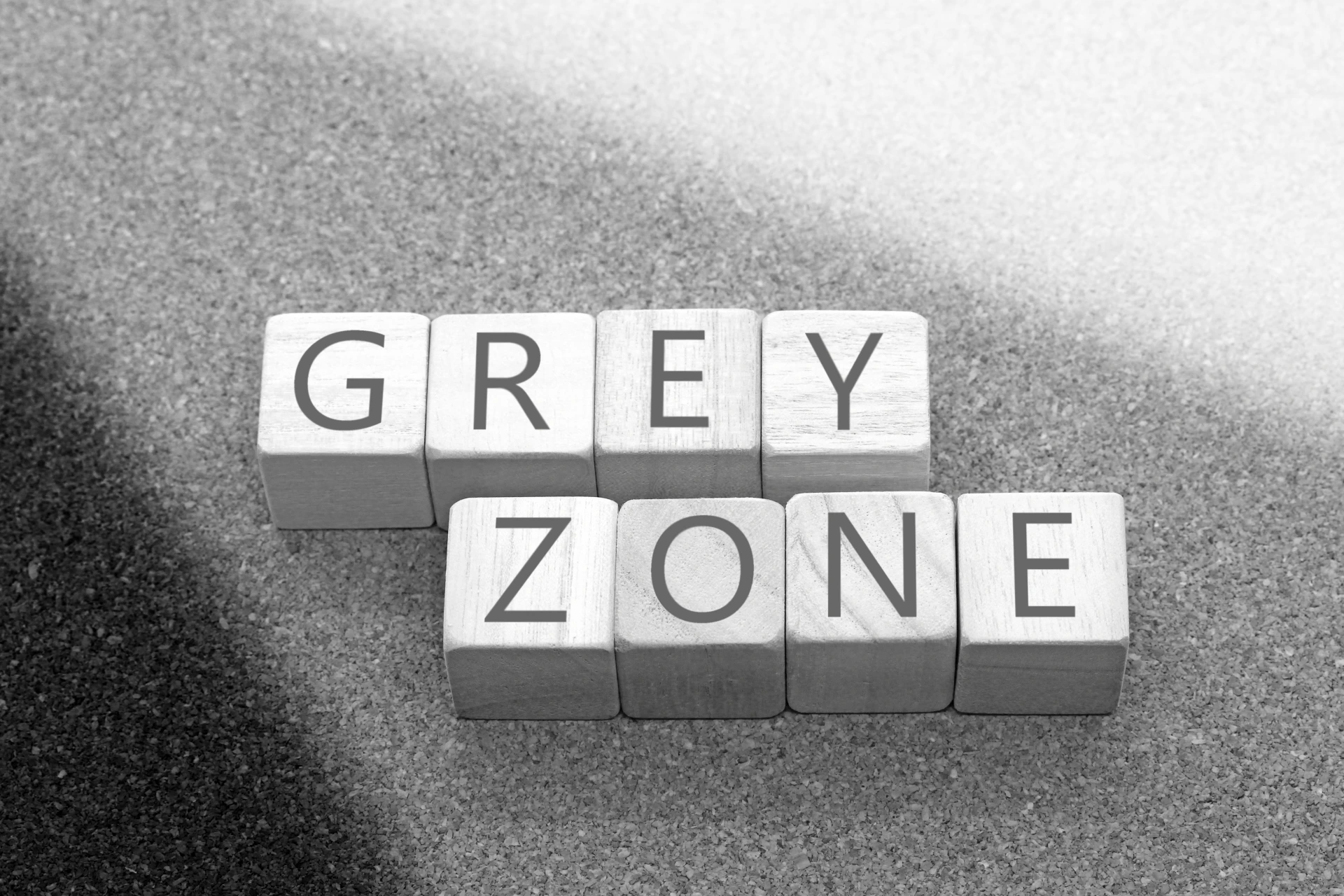目次
ギフテッドとは?

ギフテッドという言葉は、日本ではまだ広く浸透しているとは言えないかもしれません。
多くの場合、「勉強が極めて得意な子」といったイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
しかし実際には、知的な能力だけでなく、感受性や集中力、人間関係のあり方にも独特の傾向が見られることがあります。
まずは、ギフテッドの基本的な定義や特徴、そして発達障害との違いについて整理していきます。
ギフテッドの定義と特徴
ギフテッドとは、特定の分野で高い能力や才能を発揮するお子さまのことを指します。
「IQ130以上」が一つの目安とされますが、単に知能指数だけでは測れない個性を持っているのが特徴です。
たとえば、強い好奇心や集中力、深い思考力を持つ一方で、感覚が過敏だったり、感情の起伏が激しかったりするケースも見られます。
豊かな才能と同時に、繊細で扱いの難しい側面を抱えていることも少なくありません。
文部科学省は、特異な能力を持つゆえに、学校生活に困難を抱えるお子さまへの教育的支援の必要性を指摘しています。
しかし、日本ではまだ支援体制が十分に整っているとは言いがたい状況です。
ギフテッドは「優秀な子」であると同時に、「能力に応じた理解やサポートが必要な子」として捉えることが求められます。
(参考:文部科学省 令和5年度「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」(特異な才能のある児童・生徒の特性を把握するツールや特異な才能のある児童・生徒の支援に資するプログラム等のデータ収集・整理)最終報告書)
ギフテッドと発達障害の違い
ギフテッドのお子さまは、発達障害と誤解されることがあります。
たとえば、感覚過敏や集団行動の苦手さなどは、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠陥多動性障害)に見られる特徴と似ているからです。
確かに、行動の一部は共通して見えることもありますが、背景にある特性や必要な支援は異なります。
ギフテッドは、知的好奇心の強さや独自の思考パターンが原因で、学校のペースや人間関係に違和感を覚えやすい傾向があります。
また、ギフテッドと発達障害の両方の特性をもつ「2E(twice-exceptional)」というタイプも存在します。
この場合は、才能を伸ばしながら、困りごとへの支援も同時に行うことが求められます。
お子さまの特性を一面的に見るのではなく、個性として丁寧に理解していくことが大切です。
なお、発達障害への理解や不登校対応については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

発達障害の子どもが不登校になったら?親が持つべき3つの心構えを解説
不登校は、単に「学校に行きたくない」という気持ちだけではなく、発達障害による環境への適応困難が深く関わっている場合があります。お子さまが不登校になり、その背景に発達障害があると気づいたとき、不安に押し...
続きを見る
ギフテッドの子どもが不登校になりやすい原因
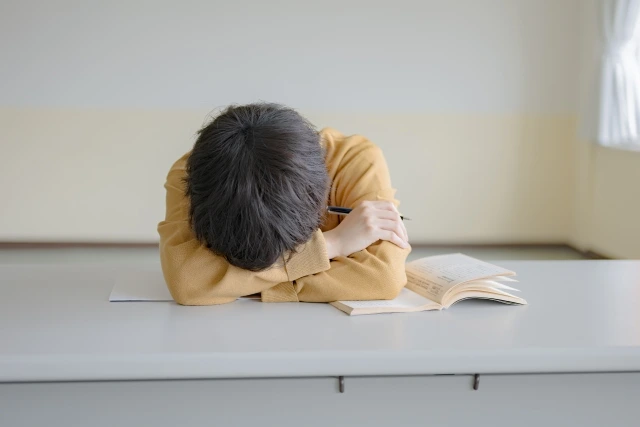
ギフテッドのお子さまは、学力に問題がないにもかかわらず、不登校になることがあります。
その背景には、学習への不満や学校環境との相性、感情の扱いにくさなど、複数の要因が重なっている傾向にあります。
ここでは、ギフテッドのお子さまが不登校になりやすい原因を解説します。
勉強がつまらない
ギフテッドのお子さまは、学校の授業を「つまらない」と感じやすい傾向があります。
その理由は、授業内容が簡単すぎたり、自分のペースで学べなかったりするためです。
知的好奇心が強く、深く考えることが得意なお子さまにとって、一斉に同じことを学ぶ授業は退屈に感じてしまうでしょう。
学びたいのに学べない状況は次第にストレスとなり、学校に行く意欲そのものが薄れていくこともあります。
また、「つまらない」と感じていてもそれを表現するのが難しく、結果的に学習への興味を失っているように見えてしまうこともあります。
周囲からは問題がないように見えるだけに、気づかれにくい悩みでもあるのです。
ギフテッドのお子さまにとって本来の力を発揮できる場がないことが、不登校のきっかけにつながることがあります。
学校環境に馴染めない
ギフテッドのお子さまは、学校という集団環境に馴染みにくい傾向があります。
これは、対人関係の違和感や、形式的なルールへの戸惑いといった強いストレスを感じてしまうことがあるためです。
たとえば、同年代との会話がかみ合わなかったり、価値観が合わず孤立感を抱えたりする場面も見られます。
また、周囲の空気を読みすぎて疲れてしまったり、教師との関係に敏感に反応してしまうお子さまも少なくありません。
このようなストレスが蓄積すると、学力に問題がなくても、学校の空気に合わない苦しさが不登校の要因となることがあります。
感情のコントロールが難しい
ギフテッドのお子さまは感情の揺れが大きく、自分でも気持ちをうまく扱えないことがあります。
完璧主義や感受性の強さが影響し、些細なことで不安になったり、落ち込んだりすることがあります。
学校生活では、思い通りにいかない場面も多く、気持ちが追いつかなくなると「もう行きたくない」と感じてしまうでしょう。
感情をコントロールする力は、年齢とともに少しずつ育っていくものです。
周囲は本人の困り感に気づき、丁寧に寄り添うことが、不登校の予防や回復につながります。
周囲との違いから孤立感を感じる
ギフテッドのお子さまは、周囲との感覚や興味の違いから孤立感を抱きやすい傾向があります。
自分だけが「浮いている」と感じてしまうと、学校に行くこと自体に不安を覚えるようになってしまうでしょう。
無理に周囲に合わせようとするうちに、疲れや自己否定感が強まることも珍しくありません。
こうした孤独感が続くと、「学校に居場所がない」と感じ、不登校へとつながっていく場合があります。
ギフテッドの不登校に親が戸惑う理由

ギフテッドのお子さまが不登校になると、保護者様自身も大きな戸惑いを抱えることがあります。
「勉強は得意なのに、なぜ?」という疑問に加え、どこに相談すればよいのか分からず、途方に暮れてしまうことも少なくありません。
学校や周囲に理解されにくいからこそ、保護者様が一人で悩みを抱えてしまうケースもあります。
ここでは、ギフテッドの不登校に保護者様が感じやすい悩みの背景について解説します。
「頭がいいのに」と理解されにくい
ギフテッドのお子さまが不登校になると、「頭がいいのに、なぜ?」と不思議がられることがあります。
周囲に説明しても理解されにくく、保護者様が孤立感を抱える原因になることもあるでしょう。
たとえば、成績が良いから問題ないと思われたり、甘えているだけと誤解されたりすることもあります。
しかし、表面的な学力と、心の状態はまったく別の問題です。
こうした誤解があると、周囲に相談すること自体をためらってしまい、悩みを一人で抱え込むことにつながります。
子育ての正解が見えない
ギフテッドのお子さまを育てる中で、「どう接すればよいのか分からない」と感じる保護者様は少なくありません。
一般的な子育てのアドバイスが当てはまらず、試行錯誤を重ねることが続くと、次第に自信を失ってしまうこともあります。
たとえば、感情が不安定だったり、興味の幅が極端だったりすると、しつけや対応の正解がわかりにくくなります。
さらに、学校や医療機関によって見解が異なることもあり、戸惑いが深まることもあるでしょう。
「このままで大丈夫なのか」という不安を抱えながら、模索を続けている保護者様は少なくないのです。
周りに相談しにくい
ギフテッドという言葉自体があまり知られていないため、悩みを相談しにくいと感じる保護者様は多くいます。
たとえ話しても、「贅沢な悩み」と受け取られてしまうこともあり、共感が得られにくいのが現実です。
また、専門的な対応を求めても「どこに頼ればいいのか分からない」と感じることもあるでしょう。
安心して話せる場所が見つからないと、保護者様自身の孤立感も高まってしまいます。
支援を受けるためには、まず安心して相談できる場所を見つけることが必要です。
ギフテッドの不登校にできる対応

ギフテッドのお子さまが不登校になったとき、保護者様は「どう支えればよいのか」と悩まれることでしょう。
正解が一つではないからこそ、特性に合わせた柔軟な関わりが大切です。
ここでは、ギフテッドのお子さまの不登校にできる対応を紹介します。
子どもの感情に寄り添う
まず大切なのは、お子さまの気持ちに丁寧に寄り添うことです。
ギフテッドのお子さまは、自分の感情をうまく伝えられず、「なんとなくつらい」という状態に陥ることがあります。
頭では理由を理解していても、気持ちがついてこないこともあります。
「なぜ行けないの?」と詰めるのではなく、「つらかったんだね」と言葉を受け止めてあげる姿勢が大切です。
保護者様が味方であると感じられることで、徐々に気持ちが落ち着き、次のステップを考えられるようになることもあります。
学校と連携する
不登校が続く場合でも、学校とのつながりは継続させておくことが望ましいでしょう。
これは、ギフテッドの特性について理解のある先生や支援担当者がいれば、校内での支援や配慮が期待できるためです。
たとえば、保健室登校や別室対応、通級指導など、学校側ができることを確認しながら調整することが有効です。
担任だけでなく、スクールカウンセラーと連携することで、より柔軟な対応が可能になります。
無理に登校させるのではなく、本人のペースを尊重しながら、少しずつ学校とのつながりを継続していくことが大切です。
学びの場を柔軟に選ぶ
学校にこだわらず、学びのスタイルを見直すことも選択肢の一つです。
ギフテッドのお子さまは、知的好奇心が強いため、自分の関心に合った方法で学ぶことで本来の力を発揮できることがあります。
たとえば、教育支援センター、フリースクール、ホームスクーリングや探究型のオンライン学習などが挙げられます。
この場合、現在通っている学校に籍を置いたまま利用することが可能です。
特に、教育支援センターやフリースクールの利用は、要件を満たせば「学校出席扱い」となることがあり、将来の進路への不安を軽減することもできます。
学校以外の学びの場を検討することで、学びへの意欲を保てる場合があります。
周囲と比べる必要はありません。
お子さまにとって「安心して学べる環境」は、将来にもつながる大切な土台になります。
カウンセリングを活用する
ギフテッドのお子さまは、感情や思考をうまく整理できず苦しんでいることがあります。
そのようなとき、第三者に話を聞いてもらえるカウンセリングは、有効なサポート手段となるものです。
学校内のスクールカウンセラーだけでなく、外部の専門家に相談することで、より特性に合った支援が受けられることもあります。
保護者様自身が悩みを整理するために、カウンセリングを利用することも有効です。
家庭での関わり方を一緒に考えることで、無理のない支援につながるケースもあります。
近年では、通院に抵抗のあるお子さまや、家から出にくい場合にも利用しやすい方法として、オンラインカウンセリングを選ぶ方も増えています。
お子さまの状況に応じて、安心して相談できる方法を選ぶことが大切です。
ギフテッドのお子さまへの最適なサポートは?

ギフテッドのお子さまの不登校は、学習環境や人間関係、心の負担などが複雑に絡み合っていることが少なくありません。
保護者様が「どうして登校できないのだろう」と不安を抱えるのは自然なことですし、周囲に理解されにくい苦しさにお子さま自身も戸惑っていることがあります。
「不登校こころの相談室」では、ギフテッド特有の個性や状況に合わせ、臨床心理士や公認心理師といった専門カウンセラーが丁寧に寄り添いながら支援を行っています。
オンラインだからこそ、ご家庭から安心してご利用いただけるのも大きな特徴です。保護者様だけでのご相談も可能です。
さらに、最初の一歩としてAI診断を活用いただけます。
数分で答えられるチェック形式で、お子さまの傾向を客観的に整理でき、その結果をもとに最適なカウンセラーをご案内することも可能です。
お子さまの才能や繊細さを強みとして伸ばすサポートを、一緒に見つけていきませんか。