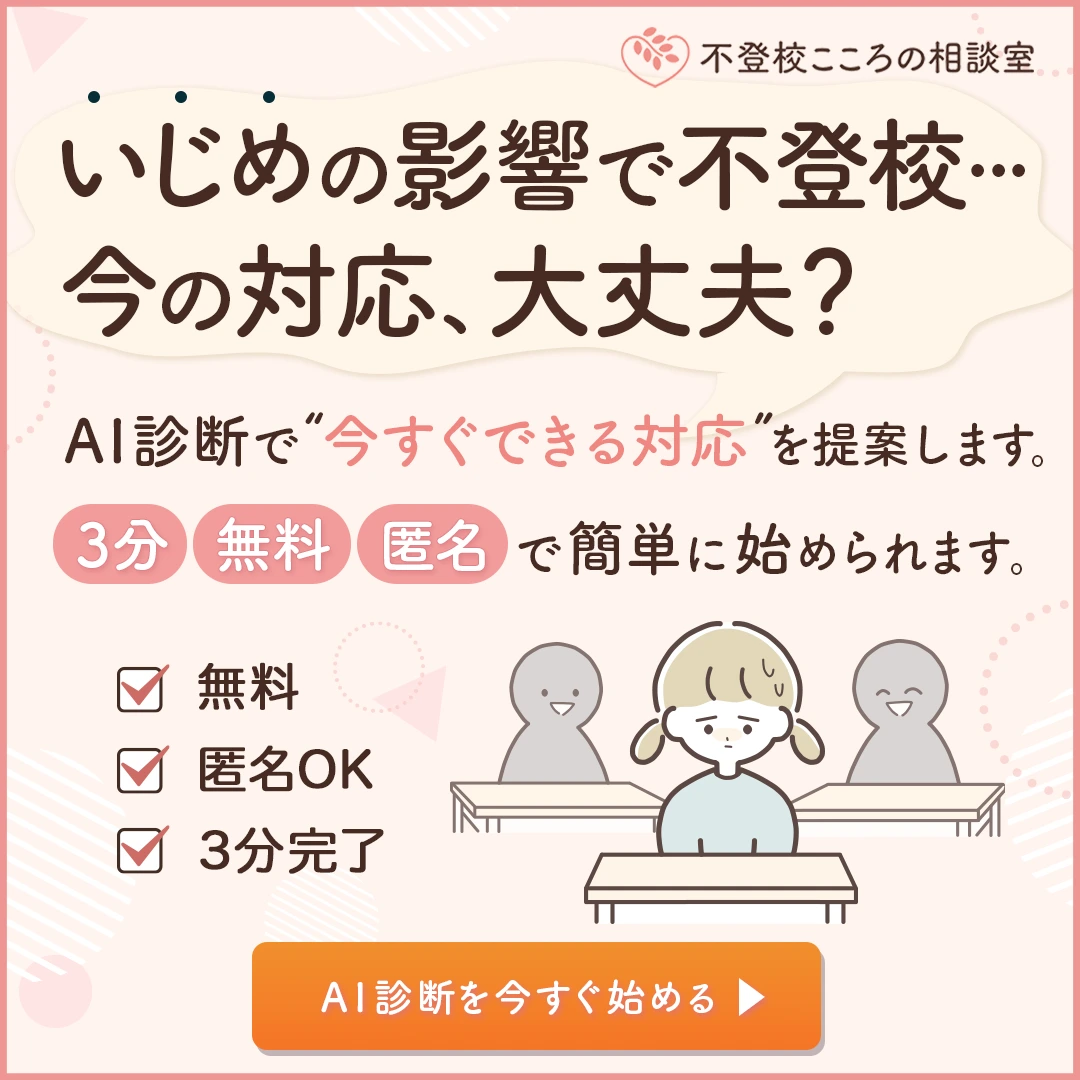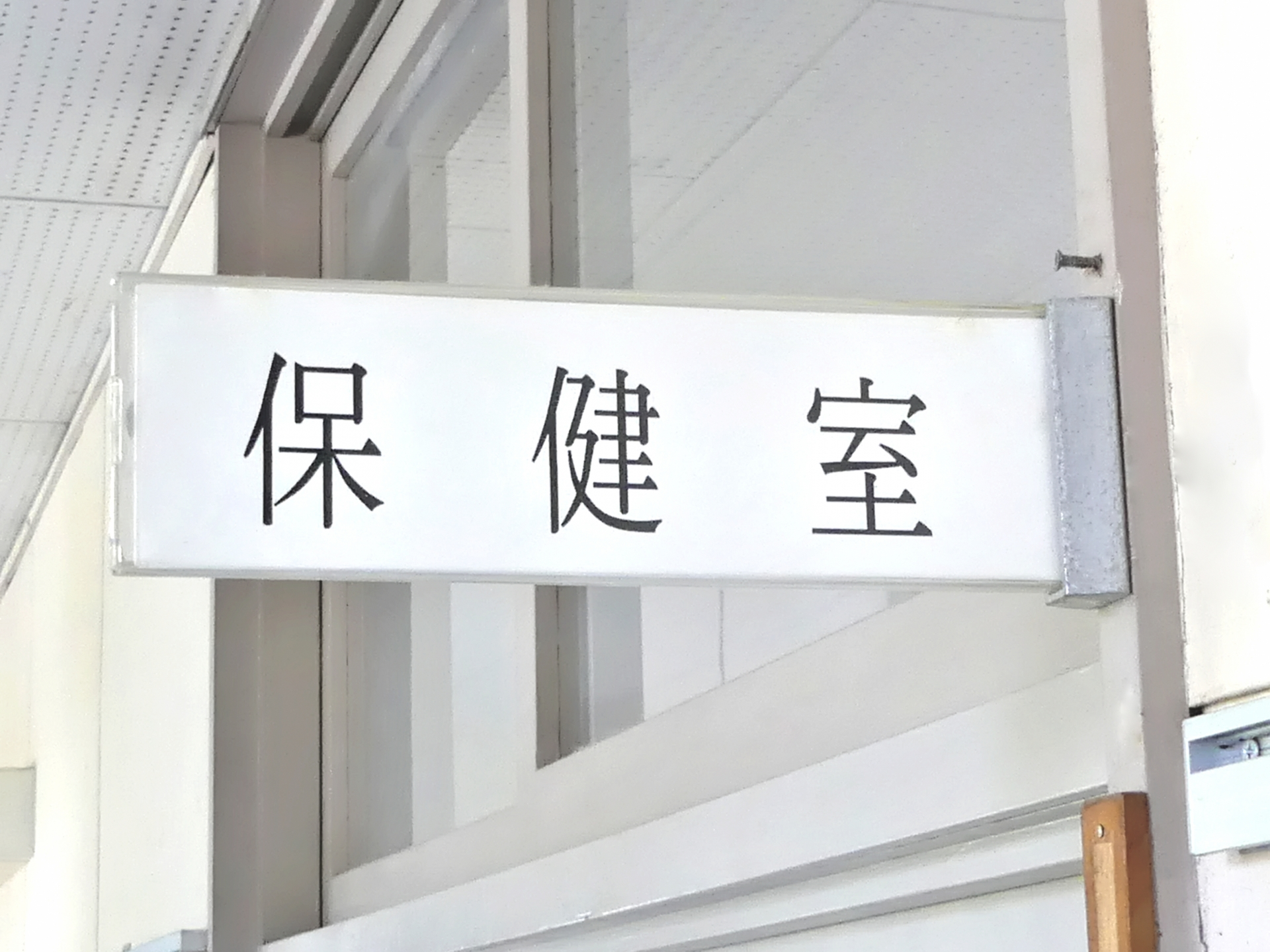目次
中学生にいじめが多い理由

中学生は心も体も大きく成長する時期であり、いじめが起こりやすいタイミングともいわれています。
思春期特有の心の不安定さや、複雑な人間関係の中での戸惑い、そしてSNSの影響など、さまざまな要因が重なることで、いじめが生まれやすくなっているのです。
ここでは、中学生にいじめが多い理由を3つに分けて解説します。
思春期の心のゆれ
中学生は思春期の真っ只中にあり、心が不安定になりやすい時期です。
この時期には、自分と他人を比べたり他人の視線を過剰に気にしたりと、感情が大きく揺れ動きます。
たとえば、自分の存在を確かめたくて強くふるまったり、誰かに不安やストレスをぶつけてしまったりすることがあります。
その結果として、無意識に相手を傷つけるような言動が、いじめにつながることもあるのです。
思春期の心のゆれは、加害の意図がないまま、いじめを生んでしまうリスクも含んでいます。
複雑な人間関係
中学生になると、友人関係は小学生のころよりも複雑になります。
複数のグループができたり、上下関係や役割分担が意識されたりと、人間関係のバランスに悩むことが増える時期です。
たとえば、特定の友だちと距離ができたことでグループから外されたり、仲の良かった相手が突然よそよそしくなったりといった経験は、多くの中学生が直面します。女児の場合、一層顕著にその傾向がみられるかもしれませんね。
このような状況が続くと、いじめへと発展してしまうこともあります。
実際、文部科学省が令和6年度に発表した調査では、令和5年度の中学校におけるいじめの認知件数は約12万件とされています。
この膨大な数字の背景には、思春期特有の人間関係の難しさが背景にあると考えられます。
(参考:文部科学省 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)
SNSの影響
近年、SNSやLINEの普及により、いじめの形態も大きく変化しています。普及に応じて、スマートフォンを通したいじめの被害が増えているのです。
具体的には、グループチャットでの仲間外れや悪口の書き込み、SNSでの無視や「いいね」を押さないといった行動が、いじめにつながることがあります。
このような「見えにくいいじめ」は、保護者様や先生が気づきにくいため、発見が遅れてしまいがちです。
また、SNS上のやりとりは形として残るため、被害者が何度も見返してしまい、傷が深まりやすいという問題もあります。
こうした状況から、SNSの影響は、いじめの長期化や深刻化を引き起こす一因になっているのです。
なお、こちらの記事では、いじめが起こる原因についてさらに詳しく解説しています。原因別の対処法も紹介しているので、あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

いじめが起こる原因は?文部科学省の指針や原因別の対処法を解説します
近年、いじめが大きな問題となっています。 いじめの原因はさまざまであり、原因を特定することが難しいケースも珍しくありません。 しかし、いじめが起こりやすい背景や原因を少しでも知っておくことで、家庭や学...
続きを見る
中学生のいじめに気づくサイン

中学生のお子さまは、自分の気持ちやつらさをうまく言葉にできないことがあります。
そのため、いじめを受けていても「何でもない」と装ってしまうケースが少なくありません。
保護者様がいじめに早く気づくためには、言葉以外のサインに目を向けることが大切です。
ここでは、日常の中で見られるいじめのサインを4つ紹介します。
口数が減る
いじめを受けているお子さまは、自分から話すことが少なくなりがちです。
話しかけても短く答えるだけだったり、目を合わせなくなったりする変化が見られることがあります。
以前は学校での出来事を楽しそうに話していたのに、最近は「別に」「普通」といった返答が多くなった場合、何か悩みを抱えている可能性があります。
話すことを避けるのは、つらい気持ちを知られたくないという防衛的な反応でもあるのです。
こうした口数の変化は小さなことのように見えても、いじめの初期サインであることも少なくありません。
頻繁に体調不良を訴える
いじめによるストレスは、心だけでなく体にも影響を与えることがあります。
「お腹が痛い」「頭が重い」といった不調を繰り返し訴えるようになるのは、そのサインの一つです。
特に、週明けや登校時間の直前になると体調不良を訴える場合は、心理的な原因が関係している可能性が高いといえるでしょう。
学校に行きたくない理由をうまく説明できず、体の不調として表現しているケースも多く見られます。
保護者様には、お子さまの体調の訴えを軽く受け取らず、背景にある気持ちに寄り添う姿勢が求められます。
登校をしぶる
登校前に「今日は行きたくない」と言ったり、準備のスピードが極端に遅くなったりするのも、いじめのサインの一つです。
また、はっきりとした理由がなくても、表情や態度に違和感があるときは注意が必要です。
「なんとなく疲れた」「行っても楽しくない」といった曖昧な言葉で学校を避けようとする場合、その背景には学校でのつらい経験があるかもしれません。
登校しぶりは、いじめが本格化する前のサインである可能性も高いため、早期の対応が大切です。
持ち物に異変が起きる
持ち物の異変も、いじめを受けているお子さまからのサインかもしれません。
ノートや教科書が破れていたり、文房具がなくなっていたりといったことが続く場合には注意が必要です。
お子さまが「自分でやった」「落としただけ」と説明している場合でも、背景にいじめがある可能性を否定できません。
お子さまが真実を話さず、隠そうとしているときこそ、大人の冷静な観察と声かけが重要です。
持ち物の異変は、見た目にも分かりやすいサインです。
日々の生活の中で、小さな変化に気づく目を持つことが、早期発見につながります。
中学生がいじめを打ち明けにくい理由

いじめのサインに気づいても、お子さま本人が何も話してくれないことに悩む保護者様も多いのではないでしょうか。
実は、中学生がいじめを打ち明けない背景には、年齢特有の心理や周囲への信頼感が関係しています。
ここでは、お子さまがいじめについて話しにくくなる3つの理由を解説します。
親に心配をかけたくない
中学生は、少しずつ大人に近づいていく時期です。
そのため、自分の問題は自分でなんとかしようとしたり、保護者様に心配をかけたくないという気持ちから、つらいことを隠そうとする傾向があります。
「何でもない」「大丈夫」と言いながら、実は内心で苦しんでいるケースは珍しくありません。
保護者様のことを信頼していないのではなく、むしろ信頼しているからこそ、迷惑をかけたくないと考えてしまうのです。
お子さまの言葉だけで判断せず、気持ちの奥にある「助けて」のサインを見逃さないことが大切です。
いじめられていると気づいていない
いじめを受けていても、本人が「いじめられている」と自覚していないことがあります。
特に、からかいが日常化していたり、グループ内で特定の役割を押しつけられていたりする場合、「自分が悪いのかもしれない」と思い込んでしまうこともあります。
たとえば、無視されたり嫌なことを言われたりしても、「冗談のつもりだったのかな」「自分に問題があるのかも」と解釈してしまうことがあります。
こうした思い込みは、お子さま自身を追い込んでしまう原因となります。
このような場合、周囲の大人が状況を客観的に見て「それはいじめだよ」と伝えることで、本人が現状を受け止めやすくなることがあります。
学校や先生に不信感がある
過去に相談しても対応してもらえなかった、あるいは逆に状況が悪化してしまったという経験から、学校や先生に対して不信感を抱いてしまうお子さまもいます。
そうした経験があると、「どうせ言っても意味がない」と感じてしまい、誰にも話せなくなってしまうのです。
また、「先生に言ったことが相手にバレたらどうしよう」といった不安や、「大ごとにしたくない」という気持ちが、相談を躊躇わせることもあります。
学校が安全な場所でないと感じたとき、お子さまはますます孤立してしまいます。
保護者様が「あなたの味方だよ」と伝え、安心して話せる環境を作ることが、再び信頼を築く第一歩になるでしょう。
いじめで不登校になる前にできること

いじめが続くと、「学校に行きたくない」と感じるようになるのは自然な反応です。
中学生のいじめは、不登校に発展しても不思議ではないほど深刻な問題です。
しかし、不登校に至る前の段階で保護者様ができることも多く存在します。
ここでは、不登校になる前にできる対応について具体的に紹介します。
家庭と学校で連携して対応する
いじめの問題は、家庭や学校が単独で解決に向かうのは難しいケースが多いものです。
保護者様と学校が情報を共有しながら、協力して対応していくことが大切です。
たとえば、担任の先生だけでなく、スクールカウンセラーや養護教諭とも連携を取り、お子さまの学校での様子や心の状態について話し合う機会を設けるとよいでしょう。
その際、お子さまの気持ちを最優先にし、「学校に戻すこと」だけを目的にしないこともポイントです。
家庭と学校が同じ方向を向いて対応することで、お子さまが「ひとりじゃない」と感じられるようになります。
保健室登校や別室登校を検討する
いじめを受けたお子さまは、教室に向かう足が遠ざかってしまうことがあります。完全な不登校とまではいかなくとも、休みがちになっているお子さまも珍しくありません。
いくら周囲が働きかけても、いきなり教室に戻るのは容易ではないでしょう。
このような場合、保健室や別室などを利用した「部分的な登校」から始める方法もあります。
これは、無理のないペースで学校と関わる機会を持ち続ける上で、有効な手段と言えるでしょう。
たとえば、学校側と相談・調整することで、午前中だけ保健室で過ごしたり、授業が始まる前や終わった後の時間に登校したりするといった、負担の少ない形で学校とつながりを持つことが可能です。
お子さまの状態に合わせて登校スタイルを調整することで、心理的なハードルを下げることができるでしょう。
登校への意欲が失われているお子さまにとっては、たとえ小さな一歩でも、「行けた」という経験が自信につながることも多くあります。
今後の学校生活や進路について考える
つらい状況が続いているときは、「これからどうなるのだろう」と先が見えなくなるものです。
だからこそ、今の状態を整理し、今後の学校生活や進路について一緒に考える時間を持つことが大切です。
たとえば、「転校した方が安心して学べるのではないか」「フリースクールや通信制高校も視野に入れてみようか」といった選択肢を知ることで、気持ちが少し楽になることもあります。
どんな道を選ぶにせよ、「自分で決められる」という感覚が、お子さまの回復につながるきっかけになることもあるのです。
進路を考えることは、目の前の不安を乗り越えるだけでなく、その先の未来に目を向けるための大切なプロセスでもあります。
なお、いじめと不登校の関係性については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。文部科学省の対策についても紹介しているため、あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

不登校といじめの関係性は?国の対策や親にできることを詳しく解説します
近年、不登校やいじめは深刻な問題となっています。 文部科学省は、不登校やいじめを解決するためにさまざまな対策を行っており、国をあげて取り組むべき課題と言っても過言ではありません。 保護者様としては、お...
続きを見る
中学生のいじめに親ができる対応

いじめに直面しているお子さまにとって、保護者様の存在は心の支えになります。
とはいえ、「どう声をかけたらいいのか分からない」「学校との関わり方に迷う」という保護者様も多いのではないでしょうか。
ここでは、保護者様ができる具体的な対応について、4つの視点からお伝えします。
子どもの話を受け止める
いじめについて話すことは、お子さまにとって非常に勇気がいることです。
その言葉を否定せず、最後まで丁寧に耳を傾けることが、親子の信頼関係を築く第一歩になります。
たとえ驚くような内容であっても、まずは「話してくれてありがとう」と伝えることが大切です。
保護者様が安心できる受け皿になることで、お子さまは「味方がいる」と感じることができるようになります。
学校と連携する
いじめの問題に向き合う上で、学校との連携は欠かせません。
担任の先生やスクールカウンセラー、学年主任など、信頼できる大人と協力しながら解決に向けて動いていく必要があります。
たとえば、学校での様子を聞いたり、必要に応じて面談の機会をつくったりすることで、お子さまの状況を共有しやすくなるでしょう。
万が一、学校側の対応に納得できない場合は、教育委員会や第三者機関に相談することも検討しましょう。
家庭だけで抱え込まない姿勢が、いじめの早期対応につながります。
いじめの証拠を残す
もしお子さまがいじめを受けているとわかった場合には、その記録を残しておくことも重要です。
証拠があることで、学校や行政に相談する際に状況を正確に伝えることができます。
具体的には、ノートにいじめの内容をメモしたり、LINEなどのやりとりを保存したりといった方法があります。
お子さま本人に負担をかけないように配慮しながら、保護者様がそっと記録を取ることも一つの手段です。
「言った・言わない」ではなく、客観的な記録があることで、周囲の大人も動きやすくなります。
相談先を知っておく
いじめの対応に悩んだときは、家庭内で抱え込まず、外部の専門機関に相談することも大切です。
スクールカウンセラーや児童相談所、自治体の教育相談窓口など、相談先はいくつか存在します。
たとえば、文部科学省が運営する「24時間子供SOSダイヤル」では、いじめや不登校
いじめによる傷を癒す方法としてカウンセリングはとても有効です。以下の記事でくわしくを解説していますので参考にしてください。などの悩みに対して、いつでも電話で相談を受けつけています。
(参考:文部科学省 24時間子供SOSダイヤル)
また、「不登校こころの相談室」も中学生のいじめ問題の相談先の一つです。
保護者様が相談先を知っていることは、「何かあったときに頼れる場所がある」と感じられる安心材料になります。
無理にひとりで答えを出そうとせず、外部の力も借りながら対応していきましょう。
中学生のいじめによる傷を癒す方法としてカウンセリングはとても有効です。以下の記事でくわしくを解説していますので参考にしてください。
- こちらもチェック
-

いじめにカウンセリングは必要?効果や選び方をわかりやすく解説します
いじめは、被害者の心を深く傷つける行為です。 いじめによって受けた心の傷は、後遺症となってその後の人生にも影響を与えることがあります。 いじめによる傷を癒すことができるのが、カウンセリングです。 いじ...
続きを見る
中学生のいじめに悩んだとき、保護者が踏み出せる最初の一歩とは?

中学生のいじめは、お子さまの心に深い傷を残すだけでなく、保護者様にとっても「どう接すればいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか迷ってしまう」といった大きな悩みにつながります。
無理に家庭だけで抱え込もうとせず、信頼できる支援先とつながることが、お子さまの回復と保護者様の安心のために欠かせません。
「不登校こころの相談室」では、不登校やいじめの悩みに特化した臨床心理士・公認心理師などの専門カウンセラーが、オンラインで丁寧に対応しています。
自宅から相談できるため外出の負担がなく、安心して気持ちを整理できる環境をご用意しています。専門家との対話を通じて、新たな選択肢や前に進むためのヒントが見えてくることも少なくありません。
とはいえ、「いきなりカウンセリングを受けるのは不安」という方も多いでしょう。そこで最初の一歩としておすすめなのが、AI診断です。
数分で答えられるチェック形式で手軽に取り組め、お子さまの現状や課題を整理するきっかけになります。さらに診断結果をもとに、最適なカウンセラーをご案内することも可能です。
中学生のお子さまのいじめに悩んだとき、まずはAI診断から始めてみませんか?
小さな一歩が、親子にとって大きな安心と回復への道しるべになるはずです。