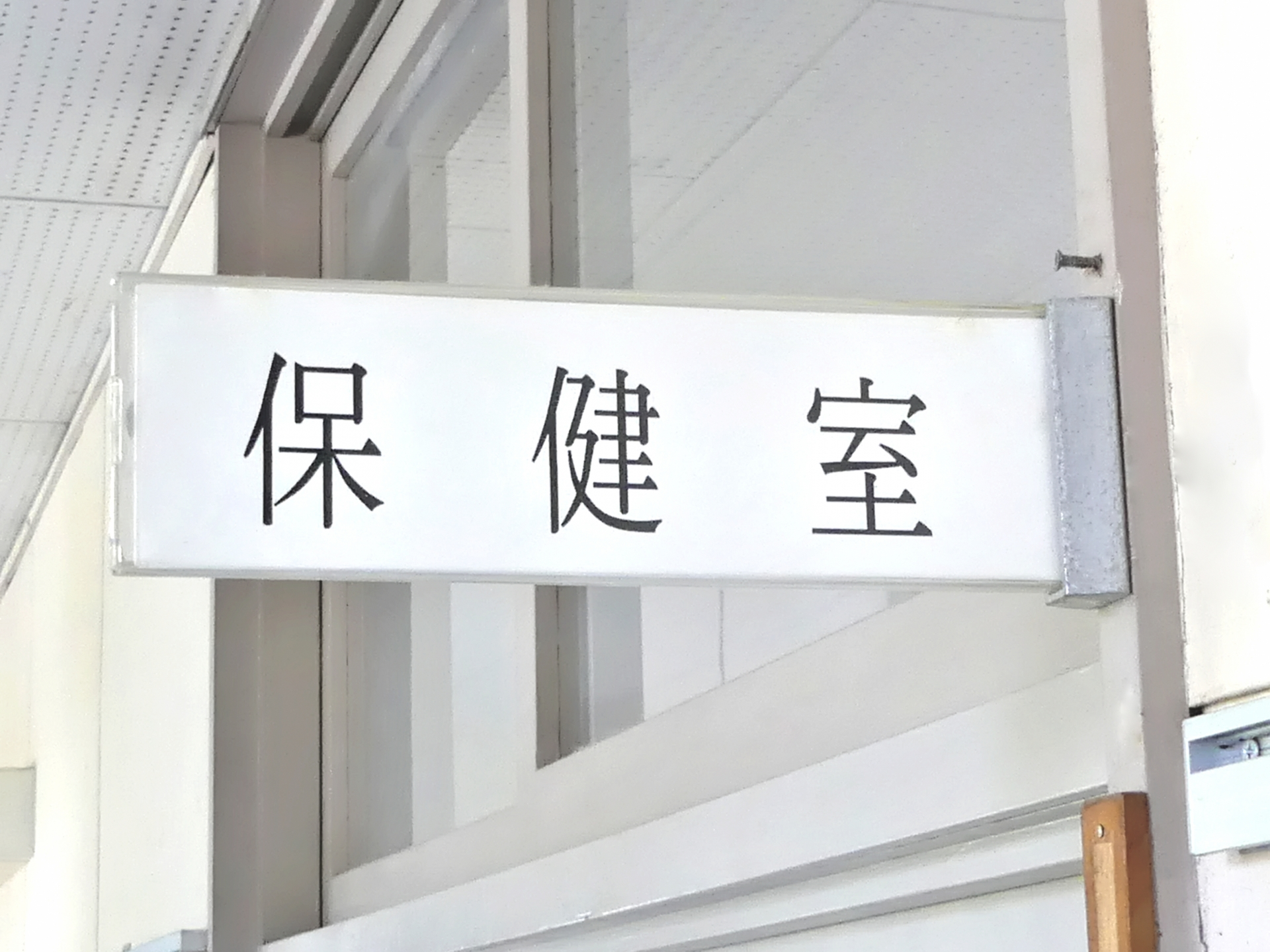目次
「行き渋り」はなぜ起こる?

お子さまが朝になると「学校に行きたくない」と訴える理由は、単なるわがままや怠けではない場合があります。学校生活でのストレスや不安、身体的・精神的な不調など、さまざまな理由で行き渋りになっていると考えられます。
行き渋りしているお子さんが小学校低学年の場合、学校に行きたくない理由を上手く言葉にして保護者様に説明するのは難しいかもしれません。ここでは「行き渋り」が起こる主な原因について詳しく解説します。
学校生活でのストレスや不安から
お子さまが学校を嫌がる理由として、学校生活がストレスになっている場合があります。特に、友人関係の悩みは多いかもしれません。小学校高学年から中学生にかけては、グループや派閥ができ、ちょっとした行き違いから良好だった関係が崩れてしまうケースもあるのです。
行き渋りがあるお子さんは、以下のような状況かもしれません。
- 仲の良かった友達から仲間外れにされた
- 休み時間や給食の時間は1人で過ごしている
- LINEやSNSでのやりとりが負担になっている
こうした状況が続くと、学校生活のストレスは溜まる一方です。「学校に行くと嫌な思いをする」といった不安が膨らみ、登校を渋るようになるでしょう。お子さまが「学校に行きたくない」と言い出したとき、最近の友人関係について話を聞いてみるといいかもしれません。
また、友人関係以外の悩みでは、授業についていけない学習の不安も行き渋りの大きな要因になり得ます。学年が上がるにつれ、学習内容はどんどん難しくなるもの。一度つまずいてしまうと、授業についていけなくなる不安が積み重なり「もう行きたくない」といった気持ちに変わるケースもあります。
特に、真面目なお子さまほど「わからない=自分が悪い」と思い込みやすく、自信をなくしてしまいます。「勉強ができない自分が情けない」「授業で発言を求められるのが怖い」といった気持ちがあると、学校へ行くこと自体が苦痛になるのではないでしょうか。
ほかに、先生との相性が合わない場合も行き渋りに大きく影響します。先生の雰囲気が、お子さまにとってプレッシャーになっているかもしれません。お子さまの話を聞く際「先生が怖い」と言っていたり、授業の話を避けたりしている場合は、悩みを抱えている可能性があるでしょう。
身体的・精神的な要因から
朝起きられないのも「行き渋り」の大きな要因です。起立性調節障害が考えられる場合は、夜型の生活になりやすい傾向があります。そのため、朝スムーズに起きられず登校が難しいケースもあるでしょう。
起立性調整障害は自律神経の乱れが考えられ、無理に起こすと余計につらくなりさらに行き渋りが悪化する場合もあります。
起立性調節障害については、こちらでも詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。
- こちらもチェック
-

中学生が朝起きられないのは病気?起立性調節障害の原因や治し方は?
不登校の中学生のお子さまの中には、朝起きられないことが悩みの種である方がいるのではないでしょうか。不登校の原因の中には「生活リズムの乱れ」があり、朝起きられないことは決して看過できる問題ではありませ...
続きを見る
頭痛・腹痛・吐き気など体調不良を訴えるお子さまは、ストレスが身体の不調となって現れている可能性があります。「仮病では?」と疑うのではなく、お子さまがどのような気持ちでいるのかを確認するのが大切です。
また、お子さまの行き渋りが長期化している場合、適応障害や発達特性が影響している可能性も考えられます。学校の環境が合わず、少しずつ精神的な負担が蓄積され登校がしんどくなっているケースもあるでしょう。
「行き渋り」にどう対応する?

お子さまの行き渋りに対して「甘えでは?」「無理にでも行かせたほうがいいのでは?」と悩む保護者様も多いかもしれません。しかし、行き渋りには必ず理由があります。その理由を無視して無理に学校へ行かせると、お子さまの心身の負担が大きくなり、不登校につながる場合も。
では、お子さまが「学校に行きたくない」と言い出したとき、どのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、具体的な対応方法を詳しくお伝えします。
子どもの気持ちを受け止める
お子さまが「学校に行きたくない」と訴えたとき、つい「どうして?」「理由を教えて」と問い詰めたくなるかもしれません。しかし、理由を説明するのが難しい場合もあります。特に、小学校低学年や思春期のお子さまは、自分の気持ちを言語化するのが苦手です。
まずは、次のような言葉かけを意識してください。
- 「行きたくないんだね」と気持ちをそのまま受け止める
- 「どんな気持ちなのか聞かせてくれる?」と問いかけてみる
- 「理由はわからなくても大丈夫だよ」と安心させる
「なぜ行きたくないの?」と問い詰めると、お子さまは「ちゃんと説明しなきゃ」とプレッシャーを感じてしまいます。まだ自分の気持ちが整理できていない段階では、無理に理由を聞くのではなく「つらいんだね」と共感する姿勢が大切です。
行き渋りが続くと、保護者様は「なんとかして学校に行かせなければ!」と焦る気持ちが生まれるかもしれません。しかし、お子さまの気持ちを無視して無理に学校へ行かせると、次のようなリスクが生じる可能性があります。
- 精神的な負担が大きくなり、ますます学校が怖くなる
- 体調不良(頭痛・腹痛・吐き気など)が悪化する
- 「親にわかってもらえない」という孤独感が生まれる
一時的に登校できても、心のエネルギーが回復していなければ、学校生活を続けるのが苦しくなり、結局は長期的な不登校につながりかねません。
まずは、学校へ行かせるよりも、お子さまの気持ちを優先する姿勢が大切です。
学校と連携する
行き渋りが続く場合、学校と連携して対応を考えるのも重要です。しかし、親が相談すると学校で余計に注目されてしまうのでは?と不安に思う方もいるでしょう。
相談する際は、お子さまの気持ちを第一に考えながら、次のポイントを意識するといいでしょう。
- 担任の先生に現状を伝え家庭での様子を共有する
- 無理に登校させるのではなく、安心して通える環境を作りたいと伝える
- スクールカウンセラーがいる場合は、専門的なアドバイスをもらう
また、学校とのやり取りは保護者様だけで進めるのではなく、お子さまの意向を尊重するのも大切です。「先生に相談してもいい?」と事前に確認し、お子さまの気持ちに寄り添いながら進めていきましょう。
お子さまによっては「教室に入るのはつらいけれど、学校には行きたい」といった気持ちを持っているかもしれません。その場合は、別室登校や短時間登校を活用するのも1つの方法です。別室登校のメリットは以下が挙げられます。
- 人目を気にせず、落ち着いた環境で過ごせる
- 必要なときに先生と話せる機会がある
- 少しずつ教室に入れるようになる
短時間登校を活用する際は、午前中だけ登校して給食の時間には帰宅したり、好きな授業や得意な科目の時間だけ参加したりするのもいいかもしれません。学校側と相談しながら、お子さまにとって負担の少ない方法を見つけることが大切です。
休むべき?無理に行かせるべき?
行き渋りが続いたとき「このまま休ませていいのか?」「少しは頑張らせるべき?」と迷う保護者様もいるのではないでしょうか。休ませる判断基準として、次のポイントを参考にしてください。
- 朝、体調不良(頭痛・腹痛・吐き気)が頻繁にある
- 登校前に涙を流したり、パニックになったりする
- 学校に行く話をすると、極端に落ち込む
このような場合は、無理をせずお子さまの気持ちを落ち着かせる時間が大切です。一時的に休ませて心と身体のエネルギーが回復すれば、自然に「学校に行こうかな」という気持ちが生まれる場合もあります。
不登校にならないようにするためには、無理に登校させるのではなく学校とのつながりを持っておくといいでしょう。お子さまが「学校に行かなければならない」と感じるプレッシャーが強いと、登校への抵抗感が大きくなってしまいます。
「今は休んでもいい」と伝えつつ、少しずつ学校とかかわる機会を作るのが、不登校を防ぐためのポイントです。
「行き渋り」に悩んだとき、保護者が踏み出せる最初の一歩とは?

お子さまの行き渋りは、決して珍しいことではありません。環境の変化や人間関係、学習の不安、体調不良など、さまざまな要因で「学校に行きたくない」と感じる時期は誰にでもあります。大切なのは、その気持ちを「甘え」と決めつけずに受け止め、安心できる環境を整えることです。
しかし、行き渋りが続くと「このままでいいのか?」と不安になり、焦ってしまう保護者様も多いでしょう。その焦りはお子さまにも伝わり、かえってプレッシャーになることもあります。そんなときこそ、専門家のサポートを取り入れることで、客観的な視点からお子さまの気持ちを整理し、適切な対応策を見つけることができます。
「不登校こころの相談室」では、行き渋りや不登校に悩むご家庭を対象に、臨床心理士や公認心理師によるオンラインカウンセリングを行っています。自宅から安心して相談できるため、近くに相談先がない方や忙しい方でも無理なく利用できます。保護者様自身の悩みや不安も整理しながら、家庭全体が前に進めるよう支援しています。
とはいえ、「いきなりカウンセリングは不安」という方も少なくありません。そこでおすすめなのが、数分で答えられるチェック形式のAI診断です。手軽に取り組めて、お子さまの状態を整理するきっかけになり、診断結果をもとに最適なカウンセラーをご案内することも可能です。
行き渋りが気になるとき、まずはAI診断という小さな一歩から始めてみませんか?その一歩が、お子さまに寄り添いながら前に進むための大切なきっかけになるはずです。