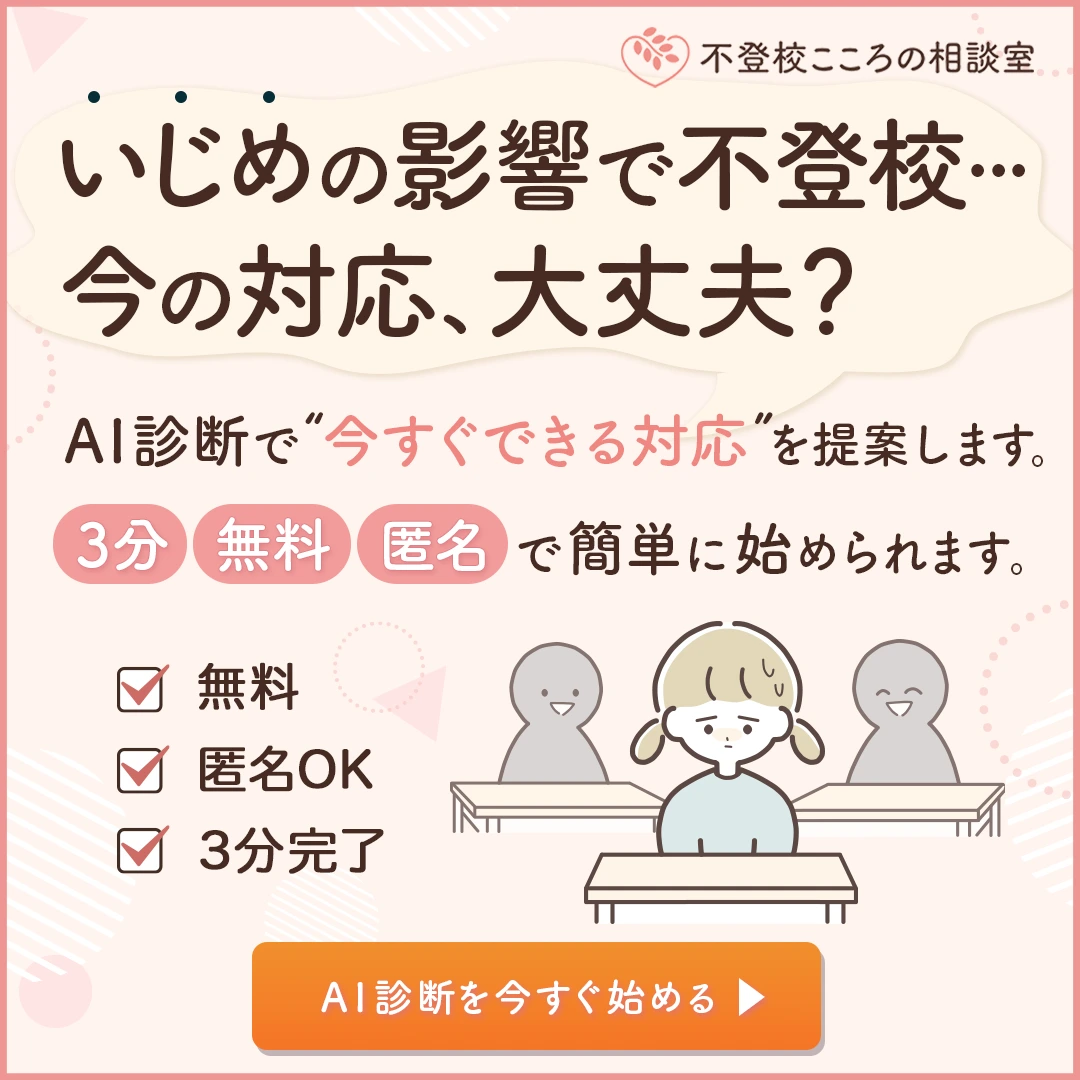目次
いじめ被害者が抱える心理とその後への影響

いじめの被害者となったお子さまは、外からは見えにくい深い心の傷を負っていることがあります。
ここでは、いじめの被害直後から長期的に及ぶ心理的な影響について解説します。
不安や自己否定感が強まる
いじめを経験すると、お子さまは他人への不信感や恐怖に加えて、自分を責める気持ちを抱えやすくなります。
特に「なぜ自分が狙われたのか」と理由がわからないでいる場合、納得できず、心の中で自己否定感が強まってしまいます。
「どうせ自分なんて」「誰も助けてくれない」といった思考が定着すると、前向きな気持ちを持ちづらくなり、人間関係を避けたり、自分の感情を抑えこむようになってしまうこともあります。
こういった考え方は、その後の学校生活や社会生活にも影響する可能性があるため、注意が必要です。
日常生活や学業に支障をきたす
いじめの影響は、学業や生活習慣にも及びます。
学校に行こうとすると体調を崩す、勉強に集中できない、夜眠れないなどの変化が現れるときは、注意が必要です。
これは、いじめの被害によるストレスや慢性的な緊張が強くなることで起きている場合があります。
また、「またいじめられるかもしれない」という恐怖から、不登校に至るケースも少なくありません。
実際に、文部科学省が行った調査では、いじめの被害をきっかけに不登校となった児童生徒は、全体の1.3%(小中計)存在することが報告されています。
なお、これは学校側が認知している件数であり、実際にはさらに多くのいじめ被害に悩むお子さまがいることが予想されます。
(参考:文部科学省 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)
将来的な心の病につながる
いじめによる心の傷は、時間が経っても消えないことがあります。
自己否定感や不安が積み重なると、将来的にうつ病や不安障害、PTSDなどの心の病につながる恐れがあります
被害の深刻さや対応の遅れによっては、長期的な治療が必要になることもあるため、早期の気づきと適切なサポートが不可欠です。
いじめ被害者への適切な対応

お子さまがいじめの被害に遭っているとわかったとき、保護者様はどのように対応すればよいのでしょうか。
ここでは、親子の信頼関係を損なわず、心の回復を支えるための基本的な対応を紹介します。
被害者の気持ちを最優先に動く
まず大切なのは、被害者であるお子さまの気持ちを優先するということです。
事実確認や加害者への対応を急ぐ前に、「つらかったね」「話してくれてありがとう」といった、気持ちに寄り添う言葉をかけてあげましょう。
いじめの被害者は、「自分は悪くない」と頭ではわかっていても、心のどこかで罪悪感を抱いていることがあります。
保護者様が一方的に行動するのではなく、常にお子さまの気持ちや希望を確認することが大切です。
学校と連携して安全を確保する
お子さまがいじめの被害者であると明らかになった場合、学校との連携は欠かせません。
担任や学年主任だけでなく、スクールカウンセラーや校長など、複数の関係者と情報を共有できるとよいでしょう。
具体的な対策として「加害者と物理的に距離をとる」「教室以外で学習できる場を設ける」など、お子さまが安心して過ごせる環境づくりを、学校と一緒に考える必要があります。
安全が確保されなければ、心の回復は始まりません。
いじめ対応の記録を残す
いじめの対応を進める上で、対応の記録を残すことは非常に重要です。
記録があることで、状況を正確に把握しやすくなり、対応が長期化した場合や第三者の介入が必要なときにも有効な資料となります。
日付や時間、いじめ被害の内容、お子さまの様子、学校とのやりとりの経緯などを、客観的に整理しておきましょう。
状況によっては、学校が十分に対応してくれないケースもあります。
そのような場合には、教育委員会への相談や、弁護士など法律の専門家への相談も視野に入ってくるでしょう。
その際、詳細な記録が法的手続きを進める上でも重要な証拠となるのです。
記録は、お子さまの権利を守るための備えであると同時に、保護者様ご自身の心を整理するツールにもなります。
医療機関の受診を検討する
心身に不調が出ている場合は、早めに医療機関を受診することも検討しましょう。
精神科や児童思春期外来など、子どもの心の専門機関では、いじめによるストレスや不安に対して医学的な視点からの支援を受けることができます。
身体的な不調がある場合も、まずはかかりつけ医に相談するのがよいでしょう。
カウンセリングを活用する
医療機関と同様に効果的なのが、カウンセリングです。
心の専門家に話を聞いてもらうことで、お子さまの気持ちが少しずつ整理され、落ち着いていくことがあります。
特に、他者には話しづらいと感じているお子さまにとっては、安心して気持ちを打ち明けられる場所として重要な意味を持ちます。
また、保護者様自身の不安や対応の悩みについて相談することも可能です。
家庭でできるいじめ被害者との関わり方

学校や医療機関と連携することに加えて、日常生活の中での関わりも心の回復を後押しします。
ここでは、いじめ被害者であるお子さまへの関わり方について解説します。
否定せず話を聴く
お子さまが話をしてきたときは、内容に驚いたり否定したりせず、まずは最後まで耳を傾けることが大切です。
「そんなことないよ」「気にしすぎ」などの言葉は、悪気がなくてもお子さまを傷つけてしまうことがあります。
家庭では何を話しても大丈夫だと思える環境づくりが、心の回復に繋がります。
安心できる家庭環境を整える
学校でつらい思いをした分、家庭では安心して過ごせるように心がけましょう。
無理に会話を増やす必要はありませんが、普段通りの食事やスキンシップ、ちょっとした声かけが支えになります。
また、今は叱責や指導よりも、安心と受容を優先する時期と捉えておけるとよいでしょう。
たとえば、登校できない日が続いても、今はそういう時期だと受け止めることで、お子さまは自分のペースで回復していくことができます。
自己肯定感を育む関わりをする
いじめを受けたお子さまは、「自分には価値がない」と思い込みやすくなります。
このような状態が続くと、自分を認める感覚が薄れ、他人との関係もうまく築けなくなることがあります。
そのため、家庭では自己肯定感を育てる関わりが重要となります。
具体的には、結果や成果ではなく、お子さまの「行動」や「存在そのもの」を認める姿勢が求められます。
「テストの点数がよかった」などの評価よりも、努力した過程や感じたことに目を向けて、「頑張ったんだね」と伝えるほうが、深い安心感につながることもあるでしょう。
また、過度に先回りして励ましたり、「大丈夫」と気軽に断定するのではなく、お子さまの感情を丁寧に受け止めることも大切です。
無理にポジティブな声かけをしなくても、日々の関わりの中で「見てもらえている」と感じられれば、少しずつ心の安定を取り戻すことができます。
自分を大切に思えるという感覚は、その後に続く心の土台となります。
保護者様が穏やかに関わり続けることで、お子さまは再び自分らしさを取り戻していけるのです。
いじめ被害に遭ったときの相談先

お子さまがいじめの被害を受けたとき、その対応を家庭だけで抱えこむのは大きな負担です。
ここでは、悩みを共有し、専門的な支援を受けるための相談先を紹介します。
スクールカウンセラー
多くの学校には、スクールカウンセラーが配置されています。
校内にいるため通いやすく、教員と連携した対応ができる点が特徴です。
保護者様が相談することも可能で、学校での様子を共有しながら、具体的な対応策を一緒に考えてもらえます。
定期的に利用することで、お子さまが心を開きやすくなることも期待できるでしょう。
児童相談所
いじめを受けたことによって、お子さまの心身に深刻な影響が出ている場合、児童相談所への相談も可能です。
虐待と同様に、いじめも重大な子どもへの人権侵害として扱われます。
家庭での対応に限界を感じたときや、学校との連携がうまくいかないときなどに、相談先の一つとして検討してみましょう。
医療機関
前述のとおり、いじめによって心や体に不調が出た場合は、医療機関での対応が必要になることもあります。
児童精神科や心療内科では、お子さまの心理状態を専門的に評価し、必要に応じて治療や支援につなげてくれます。
また、医学的な診断があることで、学校や教育委員会との交渉においても説得力を持ちやすくなることがあります。
予約が取りづらいこともありますが、かかりつけの小児科などを通して相談するのも一つの方法です。
オンラインカウンセリング
近年では、場所を問わず相談できるオンラインカウンセリングのニーズが高まっています。
自宅で相談できるため、お子さまが外出をためらっている場合や、周囲に知られたくないという気持ちがあるときにも利用しやすい手段です。
また、保護者様ご自身の不安や戸惑いを話せる場としても活用できます。
いじめに悩むとき、最初の一歩はどう踏み出せばいい?

いじめに悩むとき、最初の一歩はどう踏み出せばいい?
いじめの影響は、お子さまの心に深い傷を残し、日常生活にも大きな影を落とします。
ですが、保護者様のあたたかな関わりと専門的な支援が重なれば、少しずつ安心を取り戻すことができます。
「不登校こころの相談室」では、臨床心理士や公認心理師などの専門カウンセラーが、お子さまだけでなく保護者様の不安や戸惑いにも丁寧に寄り添いながら、無理のないペースで支援を進めています。
外出をためらうお子さまや、周囲に知られたくないと感じる場合でも、オンラインだから安心して利用できます。保護者様だけでのご相談も可能です。
そして、最初の一歩としておすすめなのがAI診断です。数分で答えられるチェック形式で、お子さまの状況やご家庭の不安を整理でき、その結果をもとに最適なカウンセラーをご案内します。
ご家庭だけで抱え込まず、安心してこの一歩から始めてみてください。