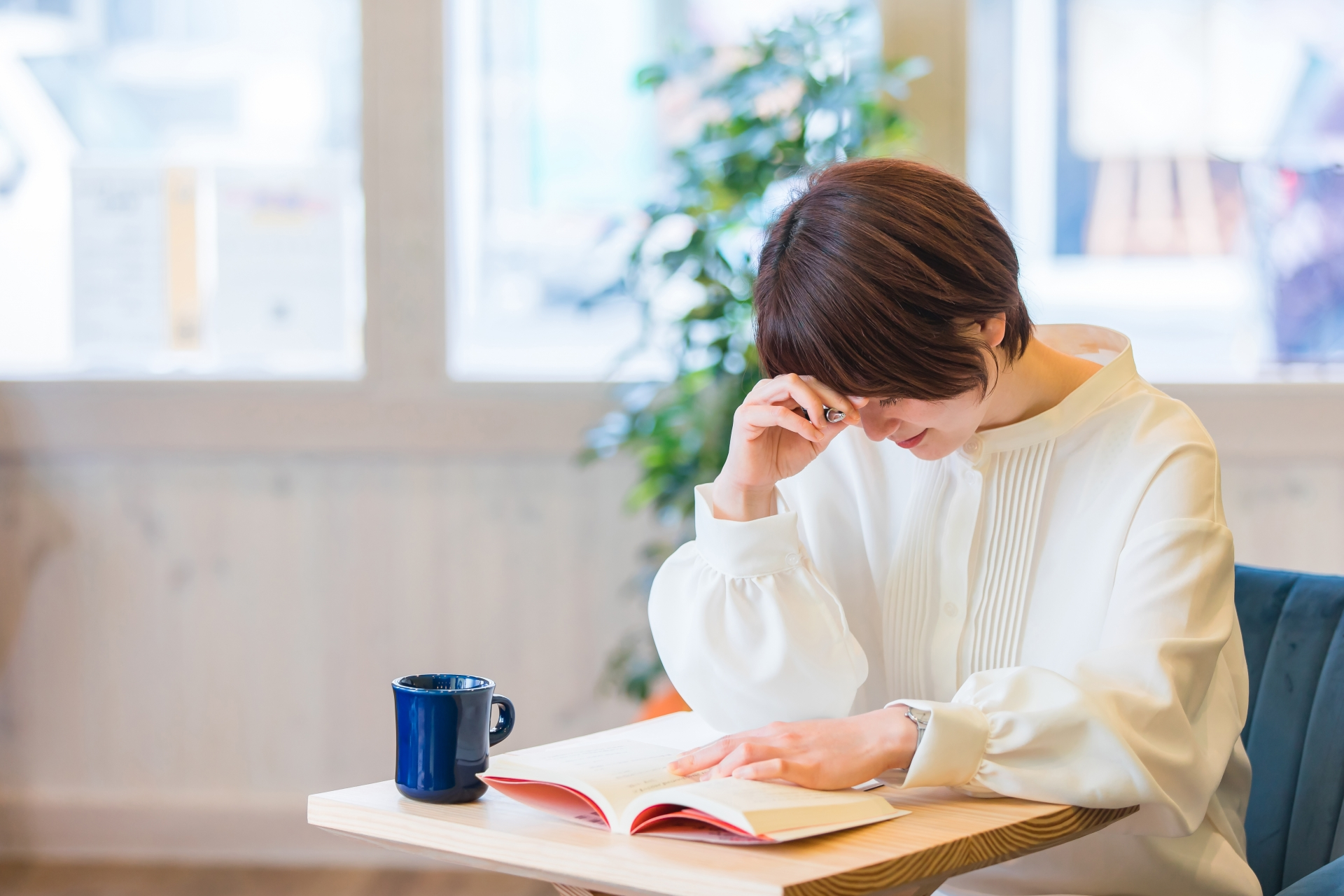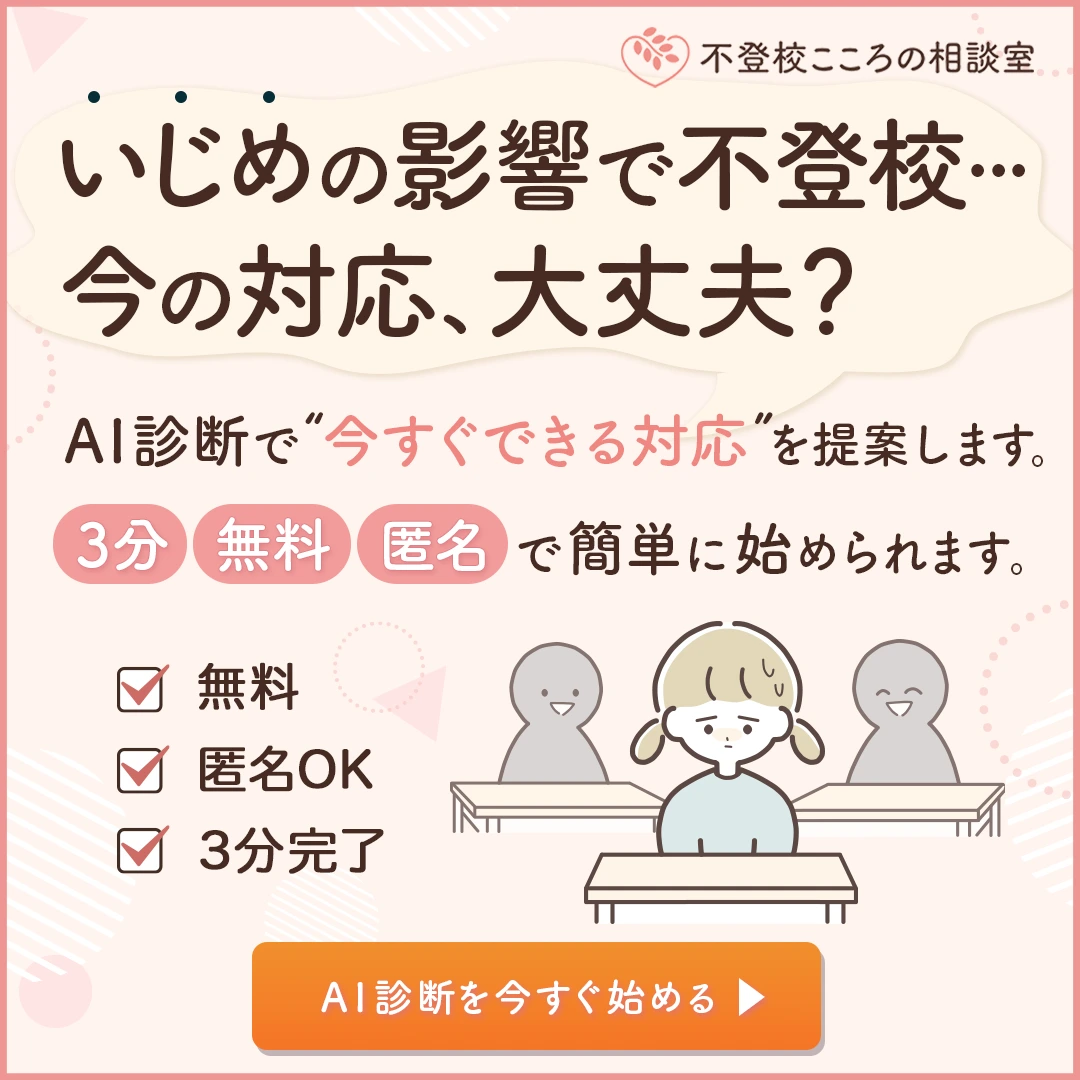いじめ加害者の親の特徴

いじめ加害者の親には、特定の性格や育て方があるわけではありません。
多くの場合、わが子を大切に思う気持ちが強く、その思いが行動や関わり方に影響しています。
ここでは、いじめ加害者の親に見られる傾向と、その背景にある心理を解説します。
子どもの行動をコントロールする
お子さまの行動を細かく指示し、日常生活のあらゆる場面で管理しようとする親は少なくありません。
その背景には、失敗させたくないという思いや、社会の中で正しく行動してほしいという願いがあると考えられます。
ただし、過剰な管理はお子さまの自主性を奪い、「自分で決めていい」という感覚を育てにくくする傾向があります。
家庭で自由に意見を言えない環境では、外の世界で自分の考えを押し通したり、相手を支配しようとしたりする行動につながることもあるでしょう。
自分の正しさを押しつける
親の中には、自分の考えや価値観を重視し、それをお子さまにも従わせようとする方がいます。
しつけやマナーを大切に思う気持ちは立派ですが、常に「こうすべき」と決めつけてしまうと、お子さまが自分の感じたことを否定されているように受け止めてしまうことがあります。
親の意見が絶対になる環境では、他人の立場や気持ちを想像する機会が減り、対人関係の中で衝突を起こしやすくなります。
まずは、お子さまの感じ方を尊重する姿勢を持つことが大切です。
わが子を守ろうとしすぎる
お子さまを思う気持ちが強いあまり、無意識のうちに事実を否定してしまう親もいます。
いじめの話を聞いたときに、「そんなことをする子ではない」と感じるのは自然な反応です。
しかし、その思いが強すぎると、現実を冷静に見ることが難しくなり、問題の根本に向き合う機会を失ってしまう恐れがあります。
お子さまの味方であることと、行動を正当化することは別です。
事実を受け止めながら、お子さまの心の中にある問題を見つめていくことが必要です。
理想の親であろうと頑張りすぎる
「きちんと育てなければ」と考えるあまり、常に完璧な親でいようと努力する方もいます。
真面目で責任感が強い一方で、自分の失敗を許せず、心に余裕をなくしてしまうケースもあります。
完璧さを追い求めるほど、親自身の疲労や焦りがたまりやすくなり、お子さまの感情に気づく余裕を失ってしまうため、注意が必要です。
感情表現が苦手
怒りや悲しみを我慢し、冷静さを保つことが「大人の対応」と考えている親の場合、お子さまも気持ちを表に出すことを躊躇ってしまう場合があります。
感情を伝え合う機会が少ない環境では、不安を抱え込みやすくなり、他者との関わり方にも影響が出ることがあります。
親が素直に「悲しかった」「心配だった」と言葉にすることで、お子さまも安心して感情を共有できるようになるでしょう。
いじめ加害者の親が陥りやすい誤解

お子さまのいじめ加害行動による衝撃から、無意識のうちに誤った理解や思い込みをしてしまう方もいます。
ここでは、いじめ加害者の親が陥りやすい誤解について解説します。
厳しいしつけが正しいと思い込んでいる
しつけを重視するあまり、「厳しくすることが正しい教育」と考えてしまう親は少なくありません。
もちろん、一定のルールや責任感を教えることは大切です。
しかし、厳しさばかりが続くと、お子さまは周囲への配慮よりも「怒られないように」と考えるばかりになってしまいます。
厳しさだけでなく、「安心して失敗できる環境」を作ることが、健全な人間関係を育むうえでは重要です。
謝罪だけで解決できると思っている
いじめの加害が明らかになったとき、まず被害者やその家族への謝罪を考える親は多いでしょう。
謝罪はもちろん欠かせない行動ですが、それだけで問題が解決するわけではありません。
いじめの背景には、感情の未熟さや人間関係の歪みなど、表面的な行動だけでは見えない要因が隠れています。
謝罪の言葉だけで終わらせるのではなく、お子さまが「なぜそんな行動を取ったのか」を一緒に振り返ることが欠かせません。
加害者へのケアを軽視している
加害者のお子さまへのケアについて指摘されたとき、「加害者なのにケアが必要なのか」と感じる方は少なくないでしょう。
しかし加害の背景には、孤独感や自己否定感、他者との関わりの不器用さが潜んでいることがあります。
お子さま自身も、心のどこかで罪悪感や不安を抱えているのです。
「罰を与える」だけでは、行動の根底にある感情を理解することはできません。
お子さまが反省や後悔を自分の言葉で表現できるように、心のケアを同時に進めていくことが大切です。
わが子に悪意がないと信じ込んでいる
「うちの子はそんなことをする子ではない」と信じる気持ちは、親として自然な反応です。
しかし、善悪の判断ができても、その通りに行動できるとは限りません。
場の空気に流されたり、友人に認められたい気持ちから思いがけない行動に出てしまうこともあります。
悪意がないから問題ではないと考えてしまうと、お子さまが抱えている本当の課題を見落とす恐れがあります。
たとえ意図がなくても、相手を傷つけてしまった事実を一緒に見つめ、どうすれば同じことを繰り返さずにすむのかを考えていくことが重要です。
なお、加害者となったお子さまへのケアやカウンセリングの必要性について、こちらの記事で詳しくご紹介しています。あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

いじめ加害者にはどう向き合う?カウンセリングの必要性や親の対応を解説
お子さまがいじめの加害者であると知ったとき、保護者様は強い衝撃と戸惑いを感じるものです。 信じたくない気持ちと、どう対応すべきか分からない不安が交錯するのは、当然の反応でしょう。 いじめは、文部科学省...
続きを見る
いじめ加害者の親が抱える苦しみ

わが子がいじめの加害者となったとき、保護者様は深い苦しみを抱えます。
責められる立場に立たされ、自分の育て方や関わり方を見つめ直しながら、どうすればよいのか分からなくなることもあるでしょう。
ここでは、いじめ加害者の親が感じやすい心の痛みについて整理します。
現実を受け止めきれない
いじめの事実を知らされたとき、多くの親は最初に「信じられない」という気持ちを抱きます。
それは、これまで見てきたお子さまの姿と、学校での行動との間に大きなギャップを感じるためです。
受け止めきれない気持ちは防衛反応の一つであり、決して異常ではありません。
しかし、その状態が続くと、問題の本質に向き合うことが難しくなります。
時間をかけて現実を受け入れながら、お子さまと一緒に対応にあたる姿勢が求められます。
自分の育て方を責めてしまう
「自分の育て方が悪かったのではないか」と自分を責める親も多くいます。
子育てにおけるあらゆる場面を思い出し、何がいけなかったのかを探し続けてしまうこともあるでしょう。
しかし、家庭の関わりだけが原因でいじめが起こるわけではありません。
友人関係や学校の環境など、さまざまな要因が重なって行動に表れることがほとんどです。
大切なのは、過去を責めることではなく、今後どう関わるかを考えることです。
周囲の目が怖い
加害者の親という立場は、周囲からの視線に強いストレスを感じやすいものです。
学校や地域での人間関係が気まずくなり、「何を言われるか分からない」と外出を控えてしまう方もいます。
孤立が続くと、悩みを抱えたまま心が疲弊していきます。
信頼できる第三者や専門家に思いを話すことで、気持ちを整理しながら少しずつ前に進むことができるでしょう。
いじめ加害者の親に求められる子どもとの向き合い方

いじめ発覚後、お子さまに対して親がどう関わるかによって、お子さまの回復や成長の方向は大きく変わります。
ここでは、いじめ加害者の親に求められる関わり方や向き合い方のポイントを紹介します。
子どもの気持ちを丁寧に聴く
お子さまの加害行動の背景には、怒りや嫉妬、不安など、さまざまな感情が隠れています。
お子さまが何を感じ、どうしてそのような行動をとったのかを、まずは静かに聴くことが重要です。
すぐに注意や助言をするのではなく、「そう感じたんだね」と受け止める姿勢を意識しましょう。
安心して話せる環境ができると、お子さま自身も気持ちを整理しやすくなります。
感情を受け止めてもらう経験が、お子さまの内面を見つめ直すきっかけにつながります。
頭ごなしに叱らず理由を聞く
親の中には、「いじめをしたのだから厳しく叱るべき」と考える方もいます。
しかし、頭ごなしに叱ってしまうと、お子さまは恐怖や反発の気持ちを抱き、心を閉ざしてしまうことがあります。
まずは、なぜその行動に至ったのか、どうして止められなかったのかを冷静に聞くことが大切です。
叱るよりも、理解する姿勢を見せることで、お子さまは自分の気持ちや行動を振り返りやすくなります。
行動の背景を一緒に整理しながら、再発を防ぐための考え方を育てていきましょう。
肯定的な声かけを増やす
いじめの加害行動を起こしたお子さまは、自分に対する否定感を強く抱えていることがあります。
反省や後悔の気持ちがあっても、どう立ち直ればよいのか分からず、自信を失っているケースも少なくありません。
そのようなときこそ、親からの肯定的な声かけが大切です。
「話してくれてうれしい」「気持ちを聞けてよかった」など、小さな言葉でも安心につながります。
存在そのものを認めてもらうことで、お子さまの自己肯定感は少しずつ回復していきます。
子どもの成長を見守る
お子さまが過ちを反省し、変わろうとするには時間がかかります。
すぐに結果を求めず、日々の小さな変化を見守る姿勢を持つことが大切です。
「まだ完全には立ち直っていない」と感じる場面もあるかもしれませんが、焦らず寄り添い続けることが信頼関係の回復にもつながります。
親が穏やかに見守ることで、お子さまも安心して新しい行動を選び取れるようになるでしょう。
親自身の心のケアをする
お子さまの加害行動を知った親は、自責の念や周囲の視線に苦しむことがあります。
そのつらさを抱えたままでは、冷静にお子さまと向き合うことが難しくなってしまいます。
ときには、家族や友人、専門家など、信頼できる人に話を聞いてもらうことも大切です。
親の心が少しずつ落ち着いていくことで、お子さまとの関係も冷静に、そして前向きに築いていくことができるでしょう。
いじめ加害者の親としての悩みは「不登校こころの相談室」へ

お子さまのいじめ加害の問題は、家庭の中だけで解決することが難しいものです。
専門家のサポートを取り入れることで、親子の気持ちを整理し、よりよい関係を築くための道が見えてきます。
「不登校こころの相談室」では、臨床心理士・公認心理師などの専門カウンセラーが、親子双方の思いを丁寧に受け止めています。
オンラインでカウンセリングを行うため、自宅から安心して相談することが可能です。
まずはAI診断を通じて状況を整理し、今必要なサポートを見つけることもできます。
つらい気持ちを抱えたまま頑張りすぎず、「誰かに聞いてもらう」ことから始めてみてくださいね。