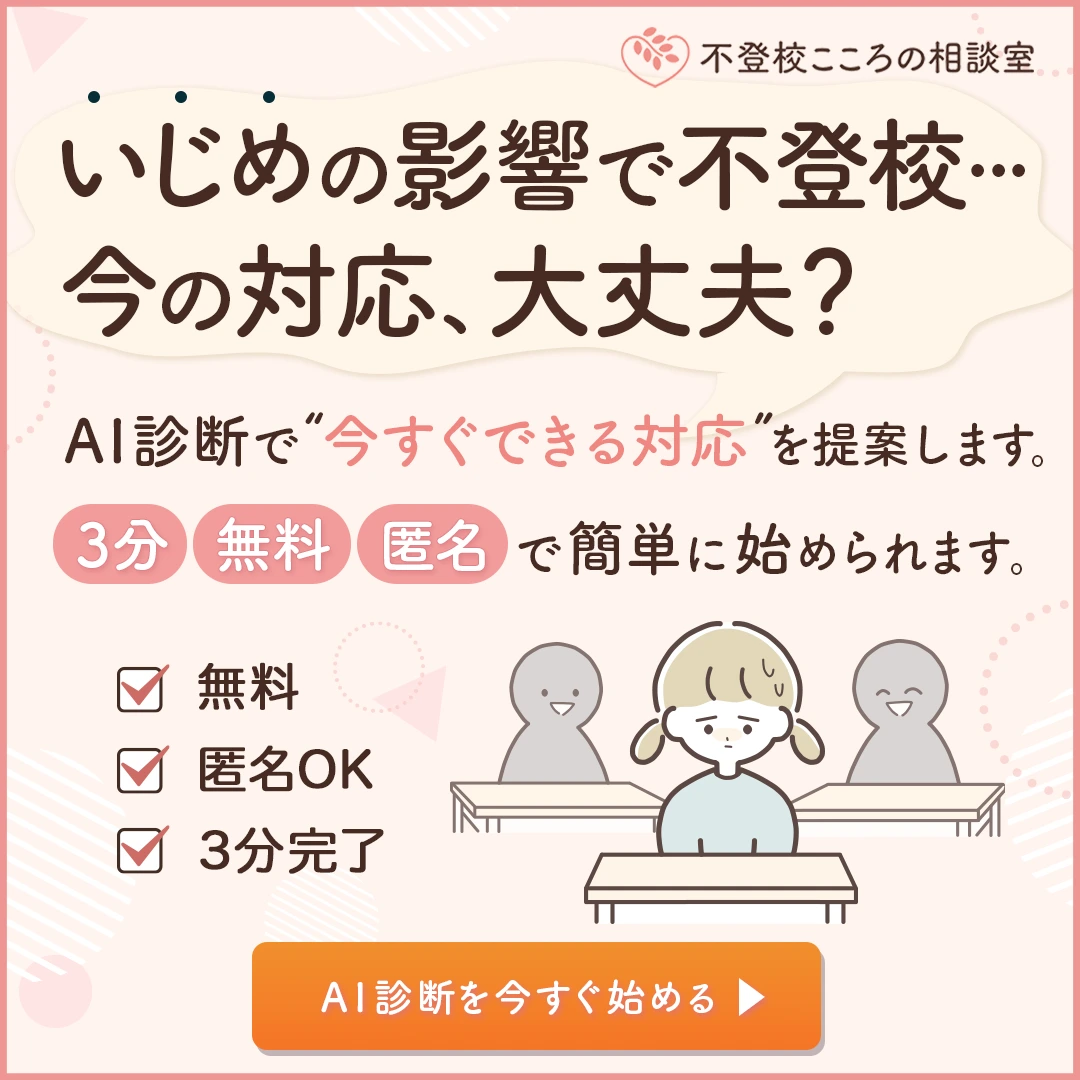目次
いじめとは?

現代においていじめは深刻な問題であり、いつお子さまのクラスで起こり、お子さまが関与してしまうかわからない事態となっています。
ここでは、いじめについて具体的に解説します。
いじめの定義や現状
いじめとは、お子さまに対して意図的に繰り返される嫌がらせや暴力、精神的な攻撃などを指します。
文部科学省の定義によると、「当該児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」とされています。
いじめは学校内外を問わず発生し、近年ではSNSを通じたいじめも増加しています。
文部科学省の調査によれば、いじめの件数は年々増加傾向にあり、多くのお子さまが被害を受けています。
また、いじめを受けたお子さまの中には、不登校になったり心の病気を発症したケースも報告されています。
いじめは一時的なものではなく、長期間にわたるケースもあり、心身の健康に深刻な影響を与える可能性があるものです。
学校や家庭など、周囲の大人には早期の適切な対応が求められます。
(参考:文部科学省 「いじめの定義」 「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」)
いじめの種類
「いじめ」と一口に言っても、種類や被害内容はさまざまです。
文部科学省は、いじめに関する調査を行う中で、いじめの種類を次の9つに分類しています。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団による無視をされる。
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
- パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。
- その他
このように、いじめの種類は、身体的なものや心理的なものだけでなく、ネットを通して行われるものなど多岐にわたることがわかります。
いじめの種類は多様であり、お子さまが苦痛を感じている時点でいじめだとみなすことができるでしょう。
(参考:文部科学省 「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」)
いじめが子どもに与える影響

いじめは、その瞬間だけでなく、お子さまの心身に長期的な影響を及ぼすものです。
これは「いじめの後遺症」と呼ぶこともできるものであり、お子さまのその後の人生に影響を与えかねません。
具体的には、次の3つの影響が懸念されます。
- 身体への影響
- 心への影響
- 将来的な影響
身体への影響
いじめを受けることで、心身症が引き起こされることがあります。
心身症とは、ストレスが原因で身体に不調が起きるものです。代表的な症状は、頭痛や腹痛、吐き気などが挙げられます。
特に、ストレスが原因となる自律神経の乱れにより、睡眠障害や食欲不振が起こることが多く、日常生活に支障をきたします。
さらに、重度のストレス状態が続くと、免疫力が低下して風邪をひきやすくなる、胃痛や消化不良が続くといった慢性的な症状に悩まされることもあります。
小さなお子さまの場合、無意識のうちにストレスが溜まり、それが身体症状として表れることも珍しくありません。
いじめの被害はもちろんのこと、それをうまく言葉にして助けを求められないストレスが蓄積されているのです。
場合によっては、学校生活に適応できなくなり、不登校に至るケースもあります。
お子さまが訴える体調不良は、心理的なストレスである可能性があります。
心への影響
いじめはお子さまの心にも大きなダメージを与えます。
いじめによって過度なストレスや不安が続くと、自己肯定感の低下や慢性的な不安感をはじめ、うつ病やPTSDといった心の病気を引き起こす可能性があります。
また、人と関わることに恐怖を覚えるなど、人間関係の構築に悪影響を与えることもあります。
これらは、心のSOSのサインであり、見過ごさないことが重要です。
身体的な症状は、時間とともにある程度改善することが見込めますが、心が受けたダメージは長期にわたって続くものです。
お子さまがいじめを受けたときは、心への影響にも注意しましょう。
将来的な影響
いじめの影響は、お子さまが大人になっても続くことがあります。
対人関係に不安を抱えたり、仕事や社会生活に支障をきたしたりすることがあるのです。
たとえば、新たな環境になっても「またいじめられたらどうしよう」という不安が拭えず、身近な人を信用できなくなったり、距離を置こうとしたりすることがあります。
特に、幼少期や思春期のいじめの影響は長期間にわたります。
いじめの経験がトラウマとなり、うまく社会に適応できなくなってしまうのです。
また、自分が受けた苦しみを他者に向けることで、加害者になる可能性も否定できません。
いじめの被害や影響は一時的ではなく、長期にわたることがあります。
なお、下の記事では、いじめの後遺症についてさらに詳しく解説しています。その後の人生への影響や乗り越えるための方法を紹介しているので、あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

いじめの後遺症は大人になっても残る?症状・人生への影響と回復の道
いじめは、被害者の心身に大きな苦痛をもたらす行為です。 いじめの被害者は、いじめられているその瞬間だけではなく、長期にわたって悩んだり苦しんだりすることがあります。これが、「いじめの後遺症」です。 で...
続きを見る
いじめが起こる原因
では、いじめが起こる原因は何なのでしょうか。
いじめの原因は、主に次の3つに分類することができます。
- 子ども同士の問題
- 家庭・環境の問題
- 学校の問題
一つずつ詳しく解説します。
子ども同士の問題
お子さま同士の関係性の中で、嫉妬やストレスのはけ口としていじめが発生することがあります。
特に、「スクールカースト」と呼ばれる、クラス内での序列や力関係が固定化されると、いじめが常態化するリスクが高まります。
また、いじめをする側のお子さまが、自分の優位性を確認するために他者を攻撃するケースもあります。
この場合、いじめがエスカレートしやすく、放置すれば深刻化する可能性が高まります。
お子さま同士のトラブルの内容は、大人から見れば些細なものかもしれません。
しかし、家庭と学校が世界のすべてと言っても過言ではないお子さまにとって、それらは大きなトラブルであり、揉め事に発展する可能性があるものです。
家庭・環境の問題
家庭環境も、いじめの原因となることがあります。
家庭内での暴力や過度な厳しさ、愛情不足などが、お子さまの攻撃性を高める要因となることがあります。
保護者様のお子さまへの無関心さが、いじめの発見を遅らせるケースもあります。
家庭環境が安定していない場合、お子さまがストレスを抱え、そのはけ口として他者に攻撃的になることがあります。
また、お子さまが勇気を出して保護者様に助けを求めても、「いじめくらい我慢しなさい」と対応することで、お子さまが助けを求めることを諦めてしまうケースもあります。
家庭の問題は、お子さまの心の健康に影響を与えるものです。
学校の問題
学校の管理体制や指導方法が不十分な場合、いじめが起こったり、認識されていても放置されやすくなったりすることがあります。
また、教師の対応が遅かったり学校内の雰囲気が閉鎖的であったりする場合、いじめが深刻化しやすい傾向にあります。
教師が「見て見ぬふり」をする環境では、被害者のお子さまが助けを求めることができず、いじめが助長されてしまうこともあります。
また、いじめが報告されても適切な対応が取られないと、被害者のお子さまはますます孤立し、事態は悪化してしまいます。
いじめは、学校の対応次第で深刻化・長期化する可能性があります。
【原因別】いじめへの対処法

上記では、いじめの原因を種類別に解説しましたが、対応もそれぞれ異なります。
いじめの原因が特定できたときは、それに合った対応を心がけましょう。
ここでは、原因別にいじめへの対処法を解説します。
子ども同士の問題への対処
いじめが発生した場合、まず大切なのは、被害に遭っているお子さまの気持ちを理解して寄り添うことです。
お子さまが安心して話せる環境を整え、決して否定せずにじっくりと話を聞きましょう。
保護者様には、学校と連携し、お子さま間のトラブルを解決できるようサポートすることが求められます。
このとき、被害に遭っているお子さまの意向を聞くことが大切です。
意に沿わない、大人主導の問題解決ではお子さまのその後の学校生活に支障をきたす可能性があります。
また、いじめを目撃した周囲のお子さまが適切に対応できるよう、傍観者ではなく「助ける側」になる意識を育むことも重要です。
学校や家庭で、いじめを見かけた際の適切な対処法を伝え、お子さまが勇気をもって行動できるようにサポートしましょう。
さらに、加害側のお子さまに対しても、単に叱ったり罰を与えるのではなく、なぜその行動を取ったのかを話し合うことが大切です。
背景にある問題を探り、根本的な解決を図ることで、いじめの再発を防ぐことができるでしょう。
家庭・環境的な問題への対処
家庭環境がいじめの原因になっている場合、保護者様がその問題から目を背けず、向き合う姿勢が大切です。
お子さまが日頃から安心して相談できる環境を整え、学校での出来事を話しやすい雰囲気を作れるよう心がけましょう。
また、家庭内のストレスや不安がいじめにつながるケースもあります。
たとえば、兄弟間の扱いの差や過度な期待が、お子さまのストレスを増幅させることがあるため、注意が必要です。
お子さまがいじめの被害者にならないことはもちろん大切ですが、同時に、加害者にならないための配慮も必要です。
場合によっては、家庭内のルールを見直したり、保護者様の接し方を変えたりする必要があるかもしれません。
いずれも、対応する中でお子さまの気持ちを尊重する姿勢を持つことが求められます。
また、いじめ問題に対処するときは、保護者様同士のつながりも重要となります。
ときには、他の家庭との交流や情報の共有が、いじめの未然の防止につながることもあるでしょう。
学校側の問題への対処
いじめが深刻化・長期化している背景に、学校側の対応の至らなさが考えられる場合、保護者様はできるだけ意見を伝えるようにしましょう。
どうしても状況が改善しないと感じる場合、教育委員会に相談するのも一つの方法です。
学校側には、いじめを早期発見しやすい環境を整える責任があります。
たとえば現状では、定期的なアンケート調査やスクールカウンセラーの配置、教師による積極的な声かけなどが実施されています。
これらが適切に実施されていない場合、要望を伝えることが大切です。
本来、いじめ問題に対処するには、学校と保護者様が密に連携を取ることが不可欠です。
家庭と学校が、いじめの現状やお子さまの様子を共有・相談できる関係が理想です。
学校側が積極的にいじめ対策に取り組んでくれることで、お子さまも保護者様も安心することができますよね。
いじめ問題における学校の立ち位置や対応に不安があるときは、学校や教育委員会に相談することを検討しましょう。
なお、下の記事では、いじめの対処法について幅広く解説しています。相談先も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- こちらもチェック
-

いじめが起きたときの対処法は?困ったときの相談先を幅広く紹介します
いじめは絶対にあってはならないことであり、被害を受けたお子さまに多くの影響を及ぼすものです。 保護者様は、我が子がいじめの被害に遭わないことを切に願っていることでしょう。 そのような中で、万...
続きを見る
いじめにまつわるよくある疑問

最後に、いじめにまつわる、次の疑問について解説・回答します。
- 「いじめ」と「いじり」は違う?
- いじめられやすい子の特徴は?
- いじめが起きやすいクラスの特徴は?
「いじめ」と「いじり」は違う?
「いじめ」と「いじり」は似ているように見えるかもしれませんが、実際にはやや異なるものです。
「いじめ」は特定の相手を傷つける意図を持ち、継続的に行われるものです。
精神的・身体的に負荷をかけ、相手を追い詰めるような行動が特徴です。
一方、「いじり」とは一般的に、友人同士でのからかいを指します。
いじりには相手を傷つける意図は含まれておらず、相手が不快に感じた場合にはすぐにやめることが一般的でしょう。
しかし、意図していなくても相手が不快に感じている場合や、冗談が一方的に強制されることがあると、「いじめ」になることもあります。
たとえば、軽い冗談として「今日の髪型変だね」と言うのは「いじり」に該当するかもしれませんが、それを繰り返し、周囲を巻き込んで笑いものにしたり、からかい続けたりする場合は「いじめ」に変わります。
関係性や相手の気持ちを無視して行われるものは、いじりとは呼べないでしょう。
「いじり」は、相手の受け取り方次第で、「いじめ」にもなり得るものです。
いじめられやすい子の特徴は?
いじめられやすい子には、一定の特徴が見られることがあります。
しかし、どのような性格や行動の子どもでもいじめの対象になり得るため、周囲のサポートが重要です。
いじめの標的になりやすいのは、大人しく自己主張が苦手なお子さまや、他の子どもと異なる特性を持つお子さまです。
「他の子どもと異なる」というのは、見た目に限った話ではありません。
学習やスポーツの能力がずば抜けていたり、反対に目に見えて劣っていたりすると、周囲との違いを理由に羨まれたり、からかわれたりすることがあります。
また、新しい環境になじみにくい、または人との距離感が独特である場合もいじめの標的として狙われることがあります。
新しいクラスでなかなか友達ができず、一人でいることが多い子どもは、いじめのターゲットになる傾向があります。
いじめられやすいお子さまの特徴は存在しますが、決してそのお子さま自身が悪いわけではありません。
周囲が多様性を尊重し、いじめを許さない環境を作ることが、いじめの防止につながります。
いじめが起きやすいクラスの特徴は?
いじめが発生しやすいクラスには、いくつかの共通する特徴が見られることがあります。
たとえば、クラス内のルールが曖昧であったり、教師の目が行き届いておらず日常的に孤立している生徒がいたりすることなどが挙げられます。
いわゆる「学級崩壊」が起きているクラスも、いじめが起こりやすいと言えます。
教師に対して子どもが力を持ちすぎており、ルールや秩序が保たれていないのです。
教師ばかりが権力を持つことは望ましくありませんが、子どもから「この先生は怒らない」「いじめに気づいていない」と思われている状況では、問題が悪化しやすくなります。
いじめを防ぎ、悪化させないためには、教師がクラスの雰囲気を把握することが大切です。
とは言え、多忙な教師が、すべてのトラブルの芽に気づくことは難しい場合があるのも事実です。
保護者様が家庭で気づいた異変などがあれば、積極的に学校に共有するよう心がけましょう。
いじめの悩みに直面したとき、保護者が踏み出せる最初の一歩とは?

いじめは複雑な要因が絡み合い、被害を受けているお子さまが自分から助けを求められないことも少なくありません。そのため、保護者様が日頃から小さな変化に気づき、安心してSOSを出せる環境を整えることが大切です。
とはいえ、実際にいじめが判明すると、保護者様ご自身も深い悲しみや衝撃を受け、「どう動けばいいのか」と迷ってしまうのは自然なことです。
「不登校こころの相談室」では、心理学に関する資格を持つ専門家が、いじめに悩むお子さまと保護者様の双方に寄り添い、安心できるオンラインカウンセリングを提供しています。
学校との連携の仕方や、ご家庭での対応についても一緒に考え、親子それぞれが安心を取り戻せるようサポートします。
とはいえ、「いきなりカウンセリングは不安」という方もいるでしょう。そんなときには、数分で答えられるチェック形式のAI診断から始めてみてください。
手軽に取り組めるうえで、お子さまの状況や心の変化を整理する手がかりになり、さらに診断結果をもとに最適なカウンセラーをご案内することができます。
いじめの悩みに直面したとき、まずはAI診断から小さな一歩を踏み出してみませんか?
その一歩が、親子にとって安心を取り戻し、前に進む力へとつながるはずです。