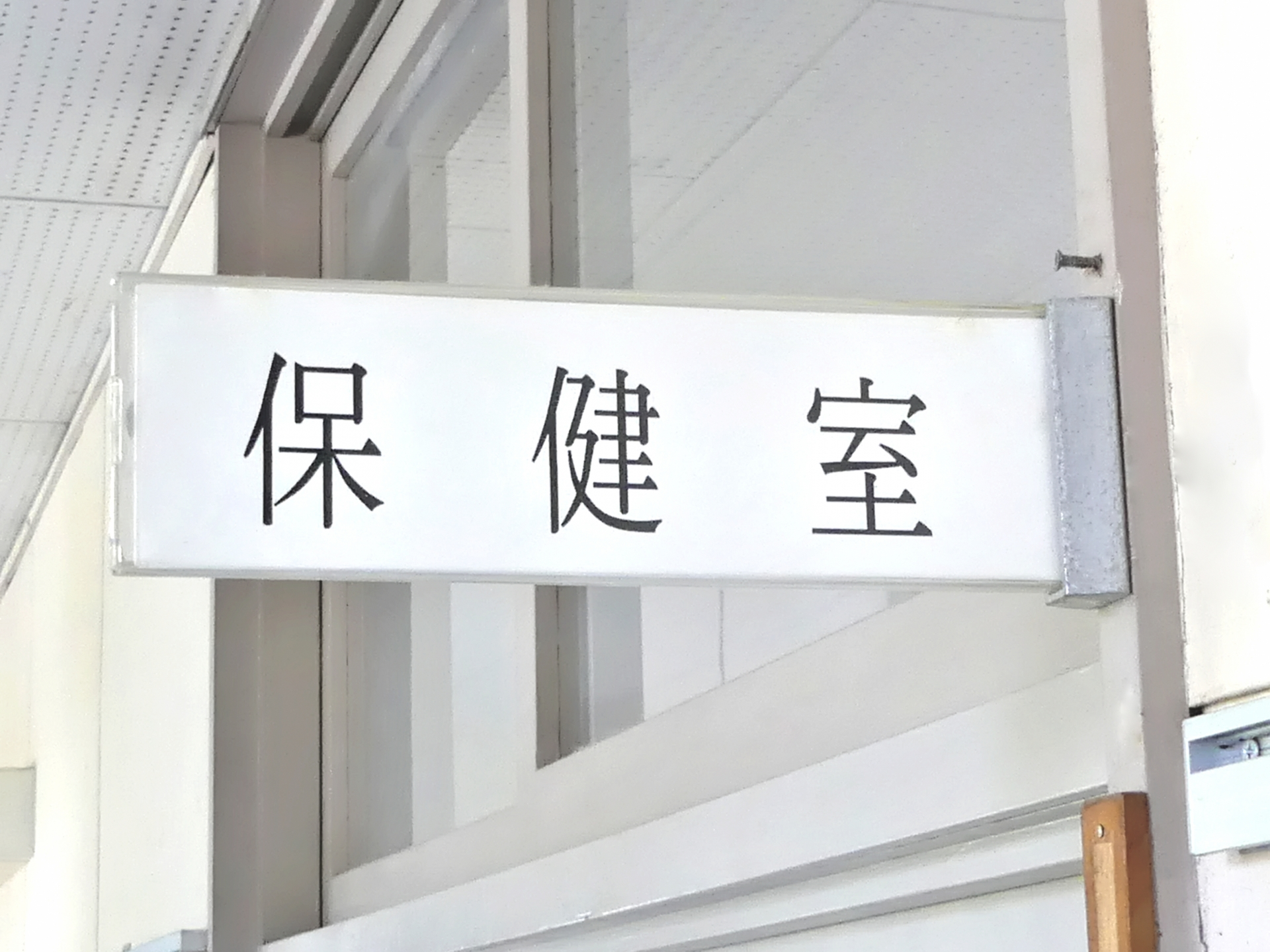目次
進学校に通う子どもが不登校になる理由

進学校に通うお子さまは、過度な競争や期待にさらされ深刻な悩みを抱えている場合があります。中学受験や高校受験のハードルを乗り越え、入学後の学校生活に胸を膨らませていたことでしょう。
しかし、充実した学校生活を期待する一方、進学校特有の大学受験に向けた学習カリキュラムについていけず、気力が続かないケースも。
ここでは、高い学力を持ちながらも進学校に通うお子さまが不登校になってしまう理由を解説します。
成績の競争が続くから
進学校には、もともと成績優秀だった子どもたちが集まってきます。しかし、周囲も同じように「できる子」ばかりの環境では、相対的に自分の位置が下がりやすく、思うような成績が取れない場合もあるでしょう。
クラスでトップの成績だったお子さまが、進学校では中位や下位になり「もう無理だ」と落ち込んでしまうと学習意欲は低下していきます。
がんばり過ぎたから
多くの進学校の生徒は、入学までにたくさんの努力を積み重ねてきたのではないでしょうか。毎日塾に通い、家でも夜遅くまで勉強してきたはずです。しかし、その目標を達成した途端、緊張の糸が切れたように動かなくなってしまう場合があります。
「燃え尽き症候群」と呼ばれる状態に陥ると、急にやる気を失い意欲が低下してしまいます。進学後、また成績の競争が始まり高い学力の維持を求められると、気力が追いつかないお子さまもいるでしょう。
周囲と馴染めないから
進学後の新しい環境で「グループに入れない」「うまく話せない」「誰にも悩みを相談できない」と感じているうちに、学校生活において孤立してしまうケースがあります。
学校生活で一緒に笑い本音で話せる友達がいないと、お子さまの心は孤独感でいっぱいになり心を閉ざしてしまいかねません。
将来が不安だから
進学校では、入学したと思ったらすぐに進路の話が本格的に始まります。周囲の生徒が目標を持って動き出すなかで「自分だけ何も決まっていない」と焦りや不安に駆られる場合もあるでしょう。
自分の進みたい道が見つからず漠然とした不安を抱えるお子さまは、勉強する意欲を失い学校生活に意味を見出せずにいるかもしれません。
進学校で起こる3つの落とし穴

一見すると、進学校は学習環境が整っているように見えます。しかし、すべてのお子さまにとって必ずしも安心して学べる環境とは限りません。学力や意欲の高い生徒が集まる進学校だからこそ、心に負担がのしかかる場合もあるでしょう。
ここでは、進学校に通うお子さまが陥りやすい心理的・環境的な3つのリスクについて解説します。
①自尊心が傷つく
進学校に入るお子さまの多くは、それまでの学校で「成績上位」「努力家」「優等生」として過ごしてきた経験があるのではないでしょうか。しかし、進学校はその優等生たちが集まる場所です。
定期テストの順位や偏差値など、数値で自分の位置がはっきりと可視化される現実に心を痛めるお子さまもいます。学力という点で競争が可視化される進学校では、精神的な耐性も求められる場所かもしれません。
これまで順調に成功体験を積み重ねてきたお子さまほど、成績が下位になると大きなショックを受けてしまうものです。成績の低下で自尊心が深く傷つくと、不安感や自己否定感を招き心のエネルギーが急激に低下します。
②助けを求められない
内向的で真面目なお子さまほど「こんな質問をしたら恥ずかしい」「こんなこともわからないと思われたくない」といった感情を強く持っています。その結果、誰にも質問や相談できない状況に陥ってしまうでしょう。
「わからなければ自分で調べる」といった姿勢が当たり前の環境だと、素直に「教えて」といえるお子さまは意外に少ないかもしれません。また、困った時に誰かに相談する習慣自体が育っていない場合もあります。周囲に「できる人」が多い環境ほど「できない自分」を認められず孤独を深めてしまうでしょう。
こうした状態が続くと「自分だけが取り残されている」と感じ、学校へ行く意欲も低下します。表面的には元気に見えても、心の中では誰にも言えない苦しさを抱えているかもしれません。
③休みたいのに休めない
学校がしんどくて、本当は休みたいのに休むことが許されないと思い込んでいるお子さまもいるでしょう。特に、真面目で責任感が強いお子さまほど「休んだら授業についていけなくなるかもしれない」と周りに置いていかれる不安を抱えている場合があります。
そのため、身体がだるくても、心が限界を超えていても、「まだ頑張れるはず」と自分を追い込んでしまいます。
また、保護者様の何気ない言葉がプレッシャーになることも。例えば「もうちょっとだけ頑張ってみたら?」といった励ましのつもりの言葉が、お子さまにとっては「休むことを許されていない」と感じさせてしまう場合も。体調不良が続いているようであれば、それは「限界が近い」あるいは「すでに限界に達した」というお子さまからのサインかもしれません。
進学校の子どもが抱えるストレスの正体

進学校に通うお子さまが抱える心理的負担は、外からは見えにくいものです。多くの保護者様や先生が「まじめで優秀な子」「何でもできる子」と捉えているタイプのお子さまほど、その裏側では人知れず悩みを抱え込んでいるでしょう。
特に「真面目さ」や「完璧主義」は、一見すると長所に見えるもの。しかし、過度になると自分を苦しめる要因になります。小さなつまずきが大きな挫折感につながる可能性もあるのです。ここでは、進学校の子どもが抱えるストレスについて解説します。
真面目さ・完璧主義がもたらす重圧
目標に向かって努力を続ける真面目なお子さま、そして完璧を目指す強い意志を持つお子さまほど、内に抱える苦悩を誰にも打ち明けられずにいるかもしれません。
周囲からは「しっかり者」「優秀」と見られていると、かえって本音を隠してしまう可能性があります。些細なミスや失敗に対しても、人一倍強い自己嫌悪感を抱いてしまうのは「できて当たり前」という強い思い込みがあるからかもしれません。
自己肯定感の根幹が、成績や周囲からの評価に大きく依存しているため、一度つまずくと自信を失い、崩れてしまう危険性があります。
親の期待・学歴志向によるプレッシャー
進学校に通わせている保護者様の多くは、お子さまに高い期待を寄せていることでしょう。しかし、保護者様の何気ない一言や態度が、お子さまにとって大きなプレッシャーとなる場合もあります。
「せっかく進学校に入ったのだから、〇〇大学を目指してほしい」「あなたならもっとできるはず」といった言葉は、保護者様にとっては励ましのつもりでしょう。しかし、お子さまの立場に立つと「親の期待に応えなければならない」というプレッシャーに変わります。
特に、保護者様ご自身が高学歴であると、お子さまにも同じルートを歩ませようとする傾向が強くなりがちです。「子どものため」といった言葉の裏側に、保護者様の価値観や願望が潜んでいませんか?愛情表現としての「期待」が、お子さまにとっては重荷になっている可能性があります。
情報過多・周囲との比較による孤独感
現代は、SNSをはじめとするさまざまなツールを通じて情報が溢れかえり、常に他者の情報が目に飛び込んできます。進学校の環境においては、友人たちの華々しい成果や学業の進捗が可視化されやすく、意図せずとも自分と比較してしまう状況になるケースもあるでしょう。
SNSで発信される情報は、どうしてもポジティブな側面が強調されがちです。そのため「まわりのみんなは楽しそうにしている」といった印象を受けやすいかもしれません。まわりと比較して孤独感や焦燥感に苛まれる場合もあるでしょう。
進学校で不登校の子の進路はどうなる?

進学校で不登校になっても将来が閉ざされるわけではありません。見方を変えると、新たなスタートを切るための準備期間と捉えられます。大切なのは、お子さまの心の状態を第一に考え、それぞれの状況に合った進路を探っていくことではないでしょうか。
ここでは、進学校で不登校になったお子さまに、どのように進路が考えられるかお伝えします。
多様な学びの選択肢
必ずしも、元の学校に戻る選択だけが正解ではありません。例えば、通信制高校やフリースクールへ進む選択もあります。
通信制高校は、自宅での学習を基本としつつ、必要に応じてスクーリングに参加する形式が一般的でしょう。カリキュラムも多様で、興味のある分野を深く学べるコースも設けられています。オンライン学習システムが充実している通信制高校では、自宅にいながらにして質の高い教育が受けられます。
フリースクールは、学習支援だけでなく、カウンセリングや体験活動など、お子さまの心のケアに力を入れている施設が多いのが特徴といえるでしょう。少人数制で、一人ひとりに寄り添ったサポートが期待できます。さまざまな個性を持つ仲間との出会いを通じて、社会性を育むことができるでしょう。
これらの環境は、学校の枠組みに馴染めなかったお子さまにとって、安心して学びを再開し、自信を取り戻すための有効な選択肢です。
大学進学への道
不登校を経験しても、大学進学を諦める必要は決してありません。近年、大学入試の形も多様化しており、学力試験だけが評価の対象ではなくなってきています。
総合型選抜といった入試方式では、お子さまの個性、意欲、これまでの経験などが総合的に評価されます。大学側は、学力だけではなく多様な背景を持つ学生を受け入れているといえるでしょう。
不登校期間中に考えたこと、興味を持って取り組んだ活動、将来への展望などをしっかりとアピールできれば、難関大学への進学も十分に可能です。不登校の経験を通して、自己理解を深め、将来について真剣に考える時間を持てたなら、それは大きな利点になるに違いありません。
再登校だけがゴールじゃない
元の学校への再登校は1つの選択肢ですが、必ずしもそれが唯一の、あるいは最善のゴールではありません。たとえ再登校できたとしても、お子さまの気持ちが追いつかず再び不登校になる可能性もあるのです。
進路を考えるうえで大切なのは「戻る」といった視点ではなく「これからどう生きたいか」「どんな自分になりたいか」といった未来志向の視点を持つ姿勢ではないでしょうか。不登校の経験を通して見えてきたこと、感じたことを大切にし、そこから本当に進みたい道を探していくことが重要です。
再登校でも、別の道でも、お子さまが主体的に考え、納得できる選択をすることが大切です。そのために、保護者様はお子さまに寄り添い、サポートしていく姿勢が求められるでしょう。保護者様は1人で悩まず、学校の先生やカウンセラー、地域の相談機関など専門家の力を借りながら、お子さまにとって最善の進路を検討してください。
不登校の経験を通して、お子さまは自分と深く向き合い、本当に大切なものを見つけられるかもしれません。
進学校で不登校になった子の親ができるサポートとは?

進学校に通うお子さまが不登校になると「こんなに頑張ってきたのに…」といった思いや「早く元のように戻ってほしい」といった願いが込み上げてくるのではないでしょうか。
しかし、このような保護者様の想いは、無意識のうちにお子さまへのプレッシャーとなってしまう場合もあります。不登校は「心身の限界を超えてしまった」明確なサインです。まずは、家庭のなかにお子さまが安心できる居場所を整えてください。
ここでは、進学校で不登校になったお子さまに対して保護者様ができる3つの基本的なサポートを紹介します。
①子どもの気持ちを聴く
お子さまが話す内容に対して、すぐにアドバイスをしたり、原因を探ろうとしたりしていませんか?不登校になったお子さまは、なぜ不登校になったのかを自分で明確に説明できないケースが多いものです。
まずは「聴く姿勢」を意識して評価や説得をしないよう心がけましょう。また、お子さまの話の内容を批判したり否定したりするのではなく、共感する姿勢を大切にしてください。
②家庭が安全と感じられる環境づくり
進学校で不登校になったお子さまにとって、家でもがんばらなくてはならないと感じさせてしまうと、回復はさらに難しくなります。保護者様は学習の遅れが気になるかもしれません。しかし、勉強よりも心の安全が最優先です。
また、保護者様自身が心を安定させて穏やかに過ごすのも大切です。焦ったりイライラしたりしていると、お子さまは保護者様の表情や態度から不安を感じとってしまいます。
③小さな変化を見逃さない
不登校からの回復には、時間がかかります。そして、回復のプロセスは直線的ではなく、行きつ戻りつを繰り返すのが一般的といえるでしょう。そのような状況で保護者様にできることは、お子さまの小さな変化に気づくこと。
その変化に対して「ありがとう」といった感謝の気持ちを持っていれば、お子さまの自己肯定感が少しずつ回復していきます。お子さまの成長を見守り自ら動き出す未来を信じることこそが何よりのサポートかもしれません。
不登校の子どもを支える具体的な方法については、こちらでも詳しく解説しています。併せて読んでみてください。
- こちらもチェック
-

不登校の子どもにできる親の対応は?子どもを支える7つの具体的な方法
不登校のお子さまを持つ多くの保護者様は「どうすれば学校に行けるのだろうか…」と日々悩み、不安な日々を過ごしていませんか?なかには「不登校は自分のせいなのかも…」と自問自答を繰り返している保護者様もい...
続きを見る
進学校で不登校になったとき、保護者がとるべき最初の一歩とは?

進学校に通うお子さまが不登校になる背景には、完璧主義や期待へのプレッシャー、SNSによる情報過多といった要因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。「小さなミスも許せない」「できて当たり前」といった思い込みが強まり、誰にも相談できず孤独を抱えてしまうケースも多いのです。
不登校は「怠け」ではなく、心が限界を訴えるSOSのサインです。焦って登校を促すのではなく、まずは休息の時間として受け止めることが回復への第一歩になります。
「不登校こころの相談室」では、心理学や教育に精通した臨床心理士・公認心理師が、進学校に通うお子さま特有の悩みに寄り添いながら、根本的な原因を一緒に探るオンラインカウンセリングを行っています。ご自宅から利用できるため、心理的・物理的な負担を最小限に抑えながらサポートを受けられるのも大きな特長です。
とはいえ、「いきなりカウンセリングは不安」という方もいらっしゃるでしょう。そこで最初の一歩としておすすめなのが AI診断 です。数分で答えられるチェック形式で取り組め、今の状態やつまずきやすいポイントを整理する手がかりになります。その結果をもとに、最適なカウンセラーをご案内することも可能です。
お子さまが再び前を向くために――。
まずは気軽にAI診断から始めてみてください。小さな一歩が、回復と成長への大きなきっかけになります。