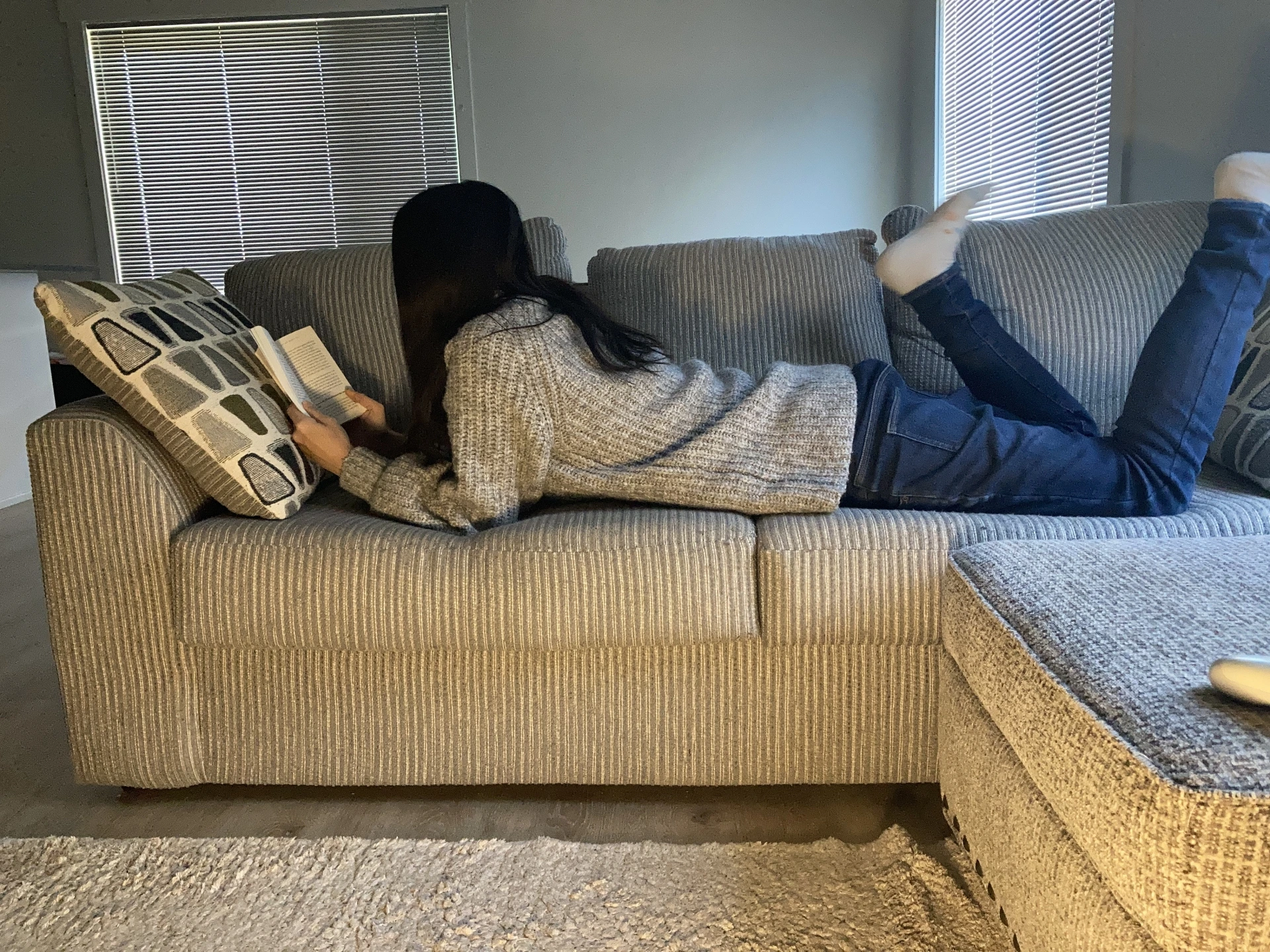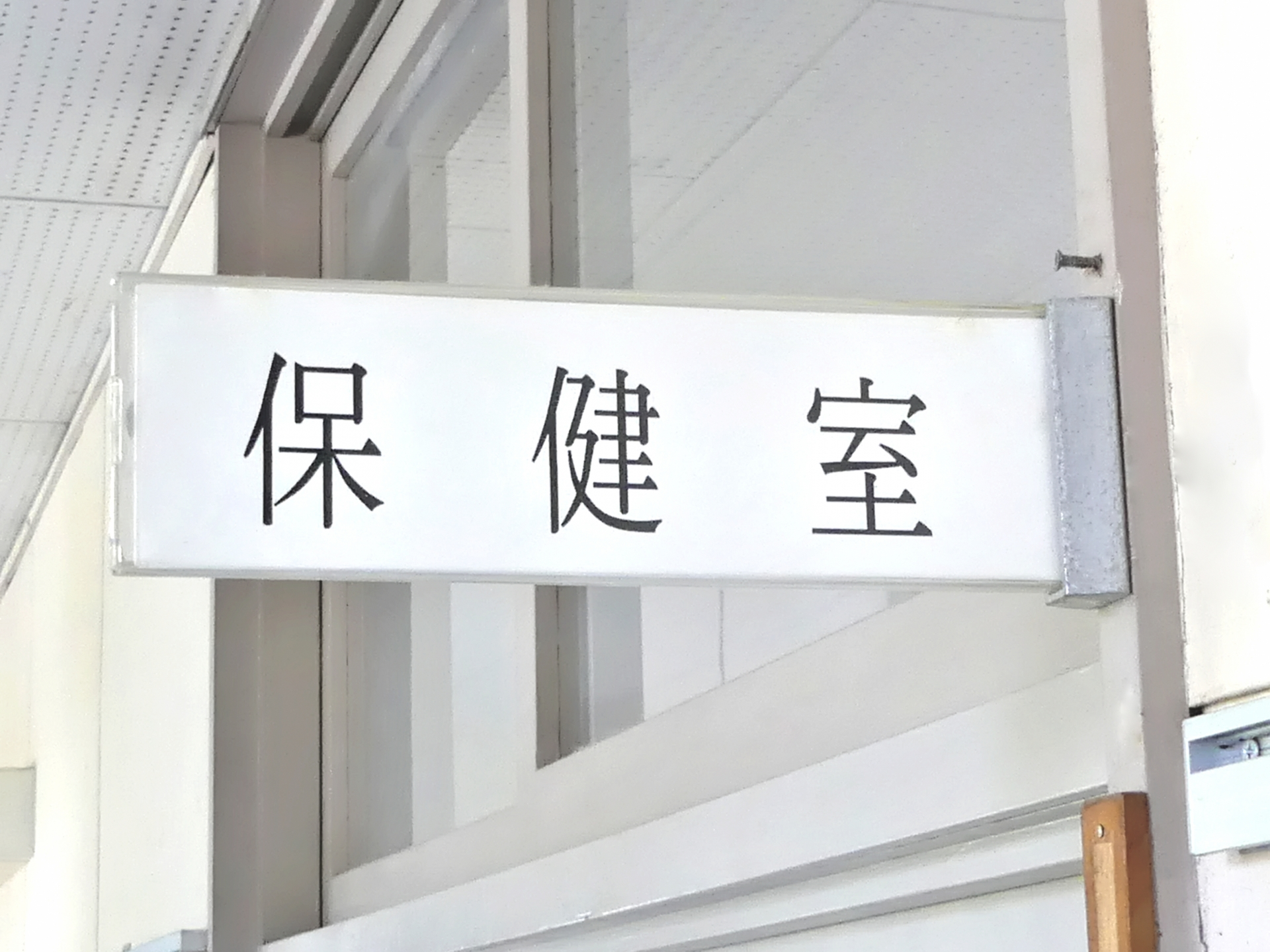目次
不登校の子どもがお風呂に入らない理由

不登校のお子さまがお風呂に入らなくなるのは、決して珍しいケースではありません。多くの不登校の子どもたちが経験することです。
ここでは、不登校の子どもがお風呂に入らない主な理由を3つ解説します。
①気力・体力がない
不登校のお子さまの多くは、心身ともに疲弊しています。一見、家でゆっくりしているように見えても、実は心のエネルギーが枯渇している状態なのです。
お風呂に入るという行動は、想像以上にエネルギーを使います。服を脱ぐ、体を洗う、髪を洗う、体を拭く、服を着る。健康な状態なら何気なくできることでも、心が疲れているときは大きな負担になります。「お風呂に入らなければ」とわかっていても、体が動かないのです。
また、お風呂に入る以外にも、部屋の片付けや勉強などができなくなる場合があります。お風呂だけが問題なのではなく、全体的に活動レベルが低下しているのです。
②生活リズムの崩れ
不登校になると、生活リズムが大きく崩れるケースがあります。特に多いのが昼夜逆転です。夜中まで起きていて、昼間は寝ている。そうなると、「お風呂に入る時間」といった概念そのものがなくなってしまいます。
学校に通っていたころは、朝起きて、学校に行って、夕方帰ってきて、夜お風呂に入るといった一定のリズムがありました。しかし、学校に行かなくなると、このリズムが崩れます。
また、生活リズムが崩れると、食事の時間も不規則になります。朝食を食べない、昼食と夕食の区別がないなど、食生活も乱れがちです。こうした生活全体の乱れから、お風呂も後回しになってしまいます。
昼夜逆転など生活リズム全般の乱れについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので併せてご覧ください。
- こちらもチェック
-

不登校の昼夜逆転は戻せる?無理なく生活リズムを整えるための6つのポイント
不登校のお子さまをもつ保護者様は「子どもが夜遅くまで起きていて、朝起きない」「昼夜が完全に逆転してしまった」と悩んでいませんか?不登校のお子さまが昼夜逆転してしまうのは、決して珍しいことではありません...
続きを見る
③自己肯定感の低下
不登校のお子さまの多くは、自己肯定感が極端に低下しています。「自分なんてどうでもいい」「自分には価値がない」と感じており、自分を大切にする気持ちが持てません。外出する予定も誰かに会う予定もないので、身だしなみを整える必要がないのです。そのため、お風呂に入る必要を感じないという心理状態といえるでしょう。
また、家族と顔を合わせたくない気持ちもあるかもしれません。お風呂に入る前後は、家族と接触する機会が増えます。「お風呂入った?」と声をかけられるのが苦痛に感じる場合もあります。
お風呂に入らないとどうなる?

お風呂に入らない状態が続くと、親御さんが心配になるのは当然です。しかし、数日間お風呂に入らなかったからといって、すぐに深刻な問題が起こるわけではありません。
ここでは、実際にどのような影響があるのか、身体面と心理面から解説します。
身体面での影響
お風呂に入らない期間が長くなると、まず身体面で影響が出てきます。最も多いのが皮膚トラブルです。汗や皮脂、汚れが蓄積すると、皮膚が炎症を起こしやすくなります。また、頭皮が痒くなる場合も。髪がべたついて、不快感を覚えるケースもあるでしょう。
ただし、これらは基本的に命に関わるような深刻なものではありません。お風呂に入れば、ほとんどの問題は解決します。過度に心配する必要はありませんが、長期化は避けたいところです。
心理面での影響
身体面だけでなく、心理面での影響も無視できません。お風呂に入らない状態が続くと、さらに自己肯定感が低下する悪循環に陥る可能性があります。「自分は汚い」「人に会えない」といった気持ちが強くなり、外出のハードルがさらに上がります。
また、お風呂に入らないことで家族関係にも影響が出るかもしれません。「なぜ入らないの?」という問いかけや「入りなさい!」といった命令は、お子さまの心を塞いでしまう可能性があります。
しかし、心理面に関してはまわりの適切なサポートで改善に向かうでしょう。無理強いせず、本人のペースを尊重する姿勢が大切です。
お風呂に入らない不登校の子どもの見守り方

お風呂に入らないお子さまに対して、どう接すればいいのか悩む保護者様は多いでしょう。無理に入れるべきか、このまま見守るべきかの判断は難しいものです。
大前提として、無理強いは逆効果です。プレッシャーをかけると、ますます入りにくくなってしまうからです。ここでは、お子さまの心に寄り添いながら、無理なく見守る方法を解説します。
無理強いしない
お風呂に入らないお子さまに対して、最も大切なのは無理強いしないことです。強制するとかえって頑なになり、さらに入らなくなってしまいます。
「お風呂に入りなさい」と命令口調で言うのも避けましょう。お子さまは、学校に行けない自分をすでに責めています。そこにさらにプレッシャーをかけると、追い詰められた気持ちになります。
また、「なぜ入らないの?」と問い詰めるのも控えてください。本人も理由がわからない場合が多いのです。説明を求められるのは大きなストレスになりかねません。
無理強いしないという姿勢は、放置するという意味ではありません。いつでもお風呂に入れる環境を整えておき、本人が入りたくなるタイミングで入れるようにしてあげることです。
声のかけ方を工夫する
お風呂について声をかける際は、言葉の選び方が重要です。何気ない一言が、お子さまにとっては大きなプレッシャーになる場合があります。
まず避けたいのが「お風呂入った?」という質問です。これは確認のつもりでも、お子さまにとっては責められているように感じます。入っていない自分を否定されているような気持ちになるのです。
「お風呂沸いてるよ」「お湯が入ってるよ」と事実だけを淡々と伝え、入るか入らないかの判断は本人に委ねましょう。
また、「今日入る?明日にする?」と選択肢を与えるのもいいかもしれません。「入らなければならない」ではなく、「いつ入るか」を選べると、自分で決めている感覚が持てます。保護者様は、お子さまがお風呂に入らなくても責めない、そして追及しない姿勢でいることが大切です。
ハードルを下げる
お風呂に入るハードルを下げる工夫も有効です。「必ず毎日お風呂に入らなければならない」という考えを手放しましょう。
2日に1回、3日に1回でも構いません。「毎日入るのが普通」という固定観念を捨ててしまうと、お子さまも保護者様も楽になります。シャワーだけでもOKです。湯船に浸からなくても、体をお湯で流すだけで十分。洗面所で顔を洗うだけでもいいでしょう。あるいは、清拭用のシートで体を拭く方法もあります。これなら、お風呂場に行く必要もありません。
お風呂の環境を整えるのも良い方法です。好きな入浴剤を用意する、好きな音楽を流せるようにする。お風呂が少しでも快適な場所になれば、入りたくなる気持ちも湧いてくるかもしれません。
最後に | 「不登校こころの相談室」ができること

不登校の子どもがお風呂に入らない背景には、心身のエネルギー不足、崩れた生活リズム、自己肯定感の低下があります。お風呂に入らないと身体面・心理面に影響が出る可能性はありますが、焦って無理強いするのは逆効果です。
とはいえ、「いつまでこの状態が続くの?」「もっと積極的に関わった方がいいのでは?」と迷う場面もあるでしょう。お風呂に入らない問題だけではなく、食事や睡眠といった生活全般の乱れに、どう向き合えばいいのか悩む保護者様は少なくありません。
そんなときは、専門家の力を借りることも検討してはどうでしょうか?「不登校こころの相談室」では、オンラインで全国どこからでも相談でき、生活習慣の改善から心のケアまで、幅広くサポートしています。
まずは無料のAI診断で、お子さまの現状を客観的に把握してみませんか。質問に答えるだけで、今お子さまにどんな対応が必要か、様子を見守っていいのか積極的に関わるべきかが整理されます。診断結果に基づいて、適切にサポートできるカウンセラーのご紹介も可能です。
お風呂に入らない問題は、お子さまの心の状態を表しているサインです。表面的な対応だけでなく、その背景にある心の疲れや不安に寄り添う必要があります。「不登校こころの相談室」は、そうした根本的なサポートを提供します。まずはAI診断から、一歩を踏み出してみませんか。