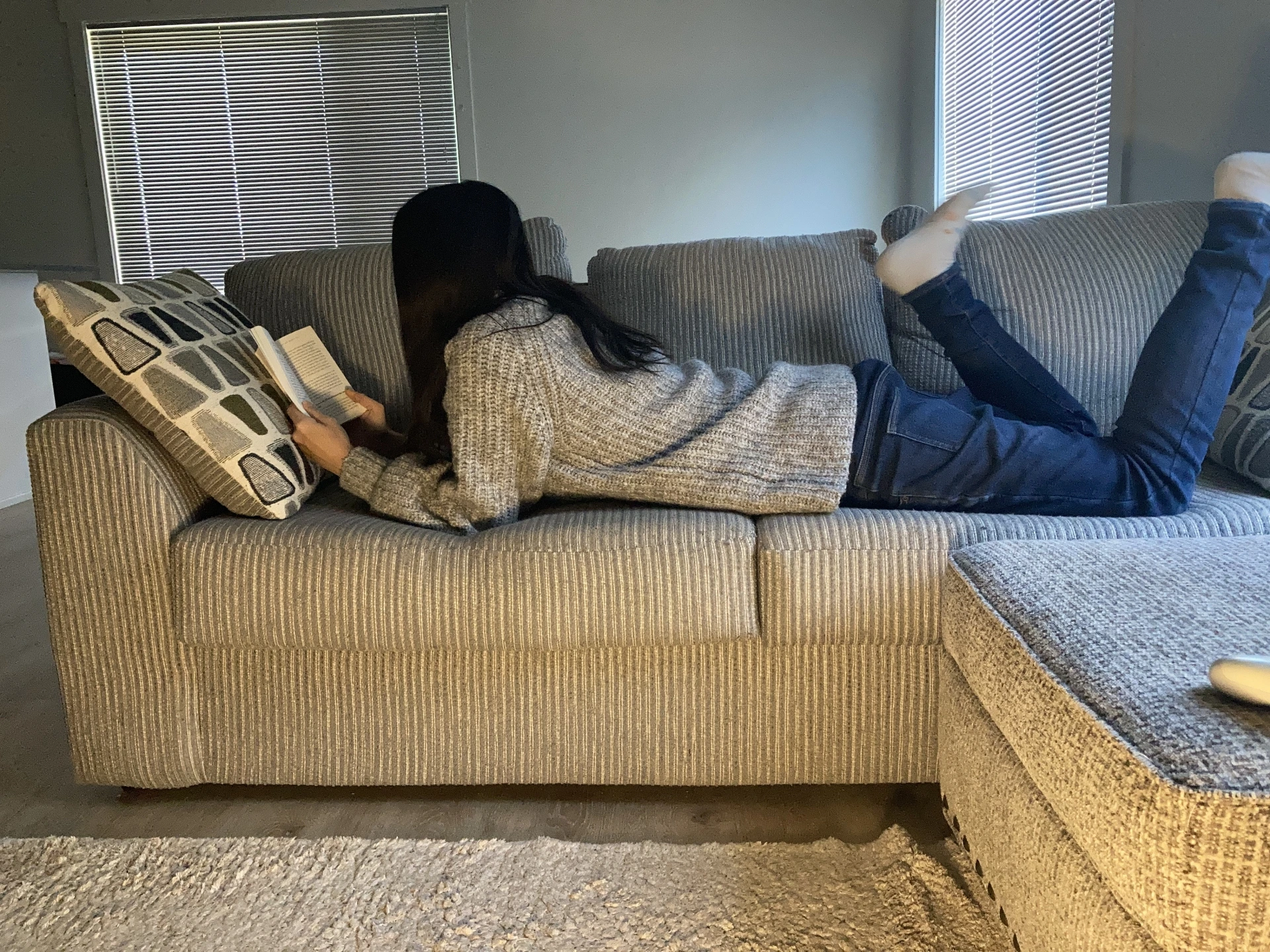目次
不登校からの復帰は難しい?

不登校からの復帰は、一人ひとりの状況や背景によって大きく異なります。
すぐに登校を再開できるお子さまもいれば、時間をかけて段階的に学校生活へ戻っていくケースもあります。
重要なのは、復帰までの「早さ」ではなく、「お子さまがどれだけ安心して再び学校と向き合えるか」です。
無理に登校を促すことがプレッシャーになり、再び休むきっかけになることもあるため、焦りは禁物です。
ここでは、文部科学省の調査などを参考に、不登校からの復帰率や復帰までの期間を解説します。
不登校の復帰率
令和5年度の文部科学省の調査結果によると、不登校の児童・生徒数は約35万人でした。
そのうち、約3割前後のお子さまが在籍校への登校を再開しています。
一方で、教育支援センターやフリースクールに通う、自宅で学習を続けるなど、学校以外の場で学びや社会とのつながりを取り戻しているケースも少なくありません。
これらを含めると、全体の6〜7割が何らかの形で社会的な再出発を果たしているとされています。
このデータから分かるのは、「学校に戻る=復帰」という狭い意味にとらわれすぎないことの大切さです。
お子さまにとって心が落ち着き、再び学びや人との関わりを持てる状態になることこそが、本当の意味での復帰といえるでしょう。
(参考:文部科学省 令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果)
不登校からの復帰にかかる期間
不登校からの復帰までにかかる期間は、お子さまの性格や不登校の背景、周囲のサポート体制によってさまざまです。
一般的には、数週間で再登校できる場合もあれば、半年から1年以上かかるケースも珍しくありません。
特に、心身の疲れや対人関係のストレスが蓄積しているときは、十分な休養と心の整理が必要です。
周りと比べることは避け、お子さま自身のペースを尊重しましょう。
焦らず、一歩ずつ前に進んでいることを信じて支えることが、結果として最も確実な復帰につながります。
不登校からの復帰のサイン

お子さまの不登校からの復帰が近いとき、必ずしも「行ける」と言葉にするとは限りません。
日常の些細な変化に、その兆しが表れることがあります。
ここでは、不登校からの復帰に向けたサインをいくつか紹介します。
前向きな表情や行動が見られる
お子さまの表情がやわらかくなったり、笑顔が増えたりするのは、心の余裕が戻ってきたサインです。
以前よりも軽い口調で会話したり、自分から何かを提案したりする姿が見られることもあります。
このような変化があるときは、無理に話を広げず、さりげなく受け止めることが大切です。
肯定的な反応は、お子さまの安心感をもたらします。
気持ちが安定する
不登校が続いているときは、お子さまの情緒が不安定になりやすい傾向にあります。
しかし、少しずつ心が落ち着いてくると、日々の小さな出来事に対して冷静に反応できるようになります。
不機嫌にならず穏やかに会話ができた、といった小さな変化も見逃せません。
情緒の安定は、登校再開を見据える上で大切なサインとなります。
家族との会話が増える
家庭内での会話が増えるのも、復帰のサインの一つです。
家族とのやりとりは、学校以外での安心できるコミュニケーションでもあります。
お子さまの様子が変化したからといって、焦って「じゃあ学校も行けるね」と結びつけるのではなく、家庭での対話を通じて自己肯定感を育てていきましょう。
生活リズムが整う
起床や就寝の時間が安定してくると、心身の状態も落ち着きやすくなります。
夜更かしが減ったり、朝の目覚めがスムーズになったりしたときは、心身が回復してきたサインです。
生活リズムが整うことで、登校時間帯に合わせた行動をとることが容易になり、登校にも前向きになれます。
学校への関心が戻る
「先生は元気かな」「友達はどうしてるかな」といった言葉が出てくるようになれば、学校への意識が少しずつ戻っている状態といえます。
過去のつらい経験を思い出して戸惑うこともありますが、興味を示すこと自体が前進の証なのです。
保護者様は、その思いを否定せずに受け止めながら、学校との橋渡しをするような関わりを意識しましょう。
不登校から復帰するきっかけ

不登校からの復帰には、「これがあれば必ず」という決まった要素はありません。
ただし、多くのケースで共通しているのは、お子さまが安心できる関係や環境の中で、自信を取り戻しているということです。
ここでは、不登校から復帰するきっかけとなりやすい要因や出来事について紹介します。
信頼できる人と関わる
お子さまが安心して心を開ける存在がいることは、復帰を後押しするきっかけとなります。
保護者様だけでなく、先生やスクールカウンセラーなど、信頼できる大人との関わりが大切です。
話を聞いてもらうことで、自分の気持ちを整理できるようになり、「もう一度学校に行ってみようかな」という思いが生まれることもあります。
小さな成功体験を重ねる
「できた」「やれた」という体験の積み重ねは、お子さまの自己肯定感を育てることにつながります。
登校に限らず、家の手伝いや課題の一部を終える、外出に挑戦するなど、日常の中で無理なく自信を育んでいけるとよいでしょう。
無理にハードルを上げず、できたことを認めるだけでも、自信が少しずつ芽生えていきます。
安心して過ごせる環境を整える
家庭や学校、支援機関など、どこにいてもお子さまが安心して過ごせる環境づくりは欠かせません。
家庭では登校を急かさず、お子さまのペースを尊重した声かけを心がけましょう。
また、学校側とも連携し、保健室登校や別室登校などの段階的な復帰方法を相談しておけると安心です。
「戻る」ことをゴールにするのではなく、「安心して過ごせる場所を増やしていく」意識を持つことが大切です。
自分のペースを取り戻す
心と体のエネルギーを回復させ、自分のペースを取り戻せるようになると、自然と次のステップを考えられるようになります。
生活のリズムを安定させたり、興味のある活動を取り入れたりすることが、ペースを整えるきっかけとなります。
お子さま自身が「これが自分らしい生活だ」と思える状態を目指しましょう。
周囲のサポートを受け入れる
不登校中、周囲からのサポートに抵抗を感じるお子さまは珍しくありません。
しかし、少しずつ人の手を借りることを「安心できること」として感じられるようになると、気持ちは軽くなります。
学校の先生やカウンセラーなど、さまざまな立場の人と関わる中で、新たな視点や安心感を得られることもあります。
サポートを受け入れられるようになること自体が、復帰へ向けた大切な一歩です。
不登校からの復帰前後に親ができるサポート

お子さまが不登校からの復帰を目指すとき、最も身近で頼れる存在は保護者様です。
学校や支援機関の協力も欠かせませんが、家庭での関わり方が復帰の安定に大きく影響します。
ここでは、お子さまが不登校から復帰する前後の時期に、保護者様ができるサポートについて紹介します。
子どもの気持ちを受け止める
お子さまが不登校からの復帰を考えるとき、まず必要なのは「気持ちをわかってもらえた」という安心感です。
学校に行けない理由を問い詰めるよりも、お子さまの気持ちに共感を示すことを意識しましょう。
お子さまが自分の思いを言葉にでき、それを受け止める存在がいることは、復帰に向けた大切なステップです。
安心できる居場所を作る
保護者様が家庭を「安心して過ごせる場所」にすることは、不登校からの復帰を支えるうえで欠かせません。
学校でうまくいかなくても家で受け入れられているという感覚が、お子さまの心を安定させます。
特別なことをしなくても、穏やかな時間を共有するだけで効果があります。
食事を一緒にとる、今日あった些細な出来事を話す、そのような日常の積み重ねが心のエネルギーを回復させる土台となります。
学校や支援先と連携する
保護者様が学校や教育支援センター、スクールカウンセラーなどと情報を共有することも大切です。
家庭での様子やお子さまの状態を伝えることで、支援の方向性を一緒に考えることができます。
不登校からの復帰を目指すには、家庭と学校が同じ方向を向いて協力し合うことが大切です。
不登校問題は保護者様一人で抱え込まず、積極的に周囲と協力しながら解決を目指しましょう。
無理のない登校ペースを検討する
不登校からの復帰後はすぐに通常登校を目指すのではなく、お子さまの心身の状態に合わせた段階的な登校ペースを検討できるとよいでしょう。
たとえば、短時間登校や別室登校など、無理のないペースで慣らしていくと負担が軽くなります。
保護者様が「今日はここまでで十分」と見極めながら支えることで、お子さまの不安感を軽減できます。
焦らず、お子さまが自分のペースで登校できる流れを一緒に整えていきましょう。
再び休んだときを見据える
不登校からの復帰後も、再び学校を休むことは珍しくありません。
保護者様は、順調に思えた復帰が叶わなくなったことに落胆してしまうこともあるかもしれませんね。
しかし、それは後退ではなく、心や体を整え直すための自然な反応です。
保護者様はそのサインを冷静に受け止め、お子さまが休息を取れる環境を用意できるとよいでしょう。
「少し休めばまた進める」と考えることで、お子さまも安心して回復に向かうことができます。
カウンセリングを活用する
保護者様自身も、不登校からの復帰を支えるなかで不安や迷いを感じることがありますよね。
そのようなときは、専門家によるカウンセリングを利用するのも一つの方法です。
第三者に話すことで、自分では気づけなかった視点を得たり、家庭での関わり方を整理できたりします。
「不登校こころの相談室」では、オンラインで経験豊富なカウンセラーに相談でき、自宅から安心して利用できます。
お子さまへの理解を深めながら、保護者様自身も心を整えていくことが可能です。
カウンセリングを通して、これまで言葉にできなかった不安や葛藤が整理されることもあります。
保護者様が穏やかな気持ちを取り戻すことで、お子さまへの接し方にも余裕が生まれ、家庭全体の空気が落ち着いていくでしょう。
不登校からの復帰相談は「不登校こころの相談室」へ

不登校からの復帰は、焦らずお子さまのペースに寄り添うことが何よりも大切です。
信頼関係や安心できる環境づくり、そして小さな成功体験の積み重ねが、再び学校と向き合う力を育てます。
また、家庭・学校・専門機関が連携し、継続的に支えることが復帰につながります。
「不登校こころの相談室」では、臨床心理士などの専門カウンセラーがオンラインでご家庭の状況に合わせたサポートを行っています。
まずは、無料AI診断でお子さまの状況に合った支援の方向性を確認することも可能です。
一人で悩みを抱えず、「不登校こころの相談室」と一緒にお子さまのこれからを考えていきましょう。