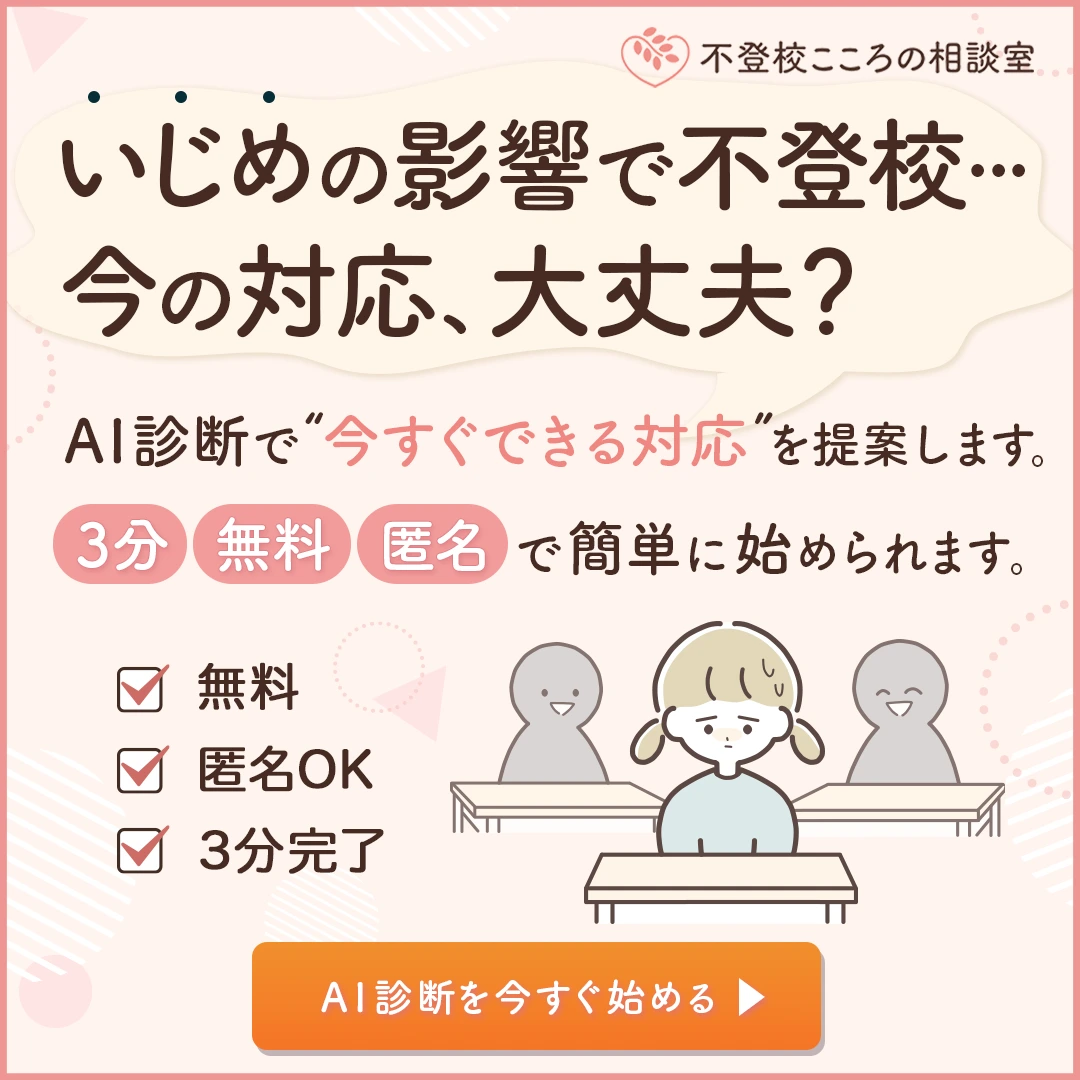目次
小学生のいじめはどこから?

お子さまの異変に「いじめかもしれない」と感じたとしても、すぐに判断するのは難しいものです。
保護者様の中には、「どこからがいじめにあたるのか分からない」と感じて悩む方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、文部科学省のいじめの定義や小学生に多い具体的なケースをもとに、いじめ実態を見ていきましょう。
いじめの定義・認知件数
文部科学省では、いじめを「一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことで、子どもが精神的な苦痛を感じているもの」と定義しています。
重要なのは、加害の意図があるかどうかではなく、被害を受けたお子さまがつらいと感じているかどうかという点です。
つまり、ふざけているつもりでも本人が傷ついていれば、それはいじめと判断される可能性があります。
いじめかどうかを判断する際は、周囲の大人が「受け手の気持ち」に寄り添う視点を持つことが求められます。
令和5年度の文部科学省調査によると、小学校でのいじめの認知件数は約60万件にのぼり、年々増加しています。
些細な言動がいじめの引き金になることもあり、見逃されるケースも少なくありません。
保護者様が日頃から意識を向けておくことが、大きな被害の防止につながります。
(参考:文部科学省 いじめの定義の変遷、文部科学省 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)
小学生に多いいじめの内容
小学生のいじめは、暴力だけでなく、言葉や態度によるものが多く見られます。
「無視される」「悪口を言われる」「仲間外れにされる」といった心理的ないじめが典型です。
また、見た目や話し方、持ち物の違いをからかうなど、些細なきっかけで標的にされることもあります。
最近では、SNSでの仲間外れや陰口など、ネット上でのいじめも問題になっています。
特に女子児童の場合、「グループ内での無視」など、表に出にくい形でいじめが進むこともあります。
表面的には穏やかでも、見えないストレスが積み重なっている可能性があるため、周囲の大人が慎重に見守ることが重要です。
小学生のいじめの原因

いじめの原因は一つではありません。
複数の要因が絡み合い、複雑に影響しあっていることが多いため、「これが原因」と断定するのは困難です。
そのような中で文部科学省は、いじめの背景を「本人」「家庭」「学校」の3つの観点から捉えることが重要だとしています。
ここでは、いじめの原因として考えられる要因を整理し、解説します。
(参考:文部科学省 いじめへの対応のヒント)
子ども本人によるもの
いじめのきっかけが、被害を受けるお子さま自身の言動にあるように見えるケースもあります。
たとえば、空気が読めない、言葉がきつい、人との距離感が近すぎるなど、周囲との関わり方に難しさを抱えていると、誤解や衝突が生まれやすくなることがあります。
特に、発達特性や強いこだわりなどがあるお子さまの場合、集団の中で浮きやすく、いじめの標的になってしまうことがあります。
ただし、こうした特性や性格の違いは、いじめを受けてよい理由にはなりません。
お子さまの個性を理解し、周囲が受け入れる環境づくりが求められます。
家庭環境によるもの
家庭の状況が、お子さまの行動や感情に影響を与えることもあります。
たとえば、親子関係が不安定であったり、保護者様の言動が過干渉・無関心に偏っていたりすると、お子さまの対人関係に影響が出やすくなることがあるのです。
また、家庭内でストレスを感じている場合、学校でその不満をぶつけてしまうこともあります。
これは加害行動にも被害行動にもつながり得るため、家庭の安定や安心感が、いじめの予防においても大切な要素となります。
学校生活によるもの
学校での人間関係や環境も、いじめが起こる背景として軽視できないものです。
たとえば、クラス替えや席替えでの孤立、新しい担任との相性、先生の注意の仕方などが、いじめのきっかけになることがあります。
また、教師の指導が行き届かない中で、特定の児童が「いじられ役」として扱われてしまうような空気が生まれると、それが本当のいじめに発展することもあります。
まだ幼いお子さまにとって、学校は社会生活のすべてといっても過言ではありません。
学校という小さな社会の中では、ちょっとしたバランスの崩れが大きな問題につながることもあるのです。
なお、いじめの原因については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

いじめが起こる原因は?文部科学省の指針や原因別の対処法を解説します
近年、いじめが大きな問題となっています。 いじめの原因はさまざまであり、原因を特定することが難しいケースも珍しくありません。 しかし、いじめが起こりやすい背景や原因を少しでも知っておくことで、家庭や学...
続きを見る
小学生のいじめに気づくために親ができること

いじめは、見えないところで進行することが多く、子ども自身が声を上げられないケースも少なくありません。
そのため、保護者様が早い段階でいじめのサインに気づき、適切に対応することが大切です。
ここでは、日常の中でできるいじめの気づき方や関わり方のポイントを紹介します。
行動や体調の変化に気づく
いじめを受けているお子さまは、言葉ではなく行動や体調にサインを表すことがあります。たとえば、急に無口になる、笑顔が減る、登校前にお腹が痛いと言う、学校に行きたがらなくなるといった変化は、心のSOSかもしれません。
こうしたサインは、日頃の疲れや体調不良と混同されやすいため、保護者様が日々の様子を丁寧に観察することが大切です。
普段と違う様子に気づいたときは、些細なことでも見逃さず、「何かあったのかな」と心を寄せてみましょう。
気持ちを引き出す工夫をする
お子さまがいじめにあっていたとしても、自分からその事実を話すとは限りません。
特にお子さまが、「言ったらもっとひどくなるかも」「親に心配をかけたくない」と感じていると、尚更口を閉ざしてしまいます。
そのようなときこそ、保護者様の関わり方が重要です。
「学校どうだった?」ではなく、「今日いちばん楽しかったことはなに?」といった具体的な問いかけにすると、気持ちが引き出しやすくなるでしょう。
心配事があると、ついいろいろと質問したくなってしまうものですが、子どものペースを尊重し、安心して話せる雰囲気づくりを心がけましょう。
いじめの初動対応を知っておく
「いじめかもしれない」と感じたとき、どう行動すればいいのか分からず戸惑う保護者様も多いでしょう。
しかし大切なのは、感情的に問い詰めるのではなく、お子さまの話を丁寧に聴き、気持ちに共感することです。
いきなり学校に連絡するのではなく、まずは事実を冷静に整理し、できるだけ記録に残すことも重要です。
初動での対応が今後の対応に大きく関わってくるため、焦らず、お子さまや学校との信頼関係を保ちながら進めるようにしましょう。
小学生のいじめへの対応

小学生のお子さまがいじめにあっていると感じたとき、保護者様がどう動くかは非常に重要です。
記録の残し方、学校との関わり方、必要に応じた法的対応など、落ち着いて段階的に行動することが求められます。
ここでは、小学生のいじめへの対応を順を追って解説します。
記録を残す
いじめを疑う場面では、できるだけ早い段階から記録を取っておくことが大切です。
日時、場所、どのような内容だったか、お子さまがどう感じたかといった点を、日記やメモ、スマートフォンのメモアプリなどに簡単にまとめておくだけでも有効です。
このような記録は、学校や第三者に相談する際の「証拠」として活用できるだけでなく、保護者様自身の気持ちの整理にもつながります。
いじめの内容が複数回にわたるときは、時系列で記録しておくと全体像が見えやすくなります。
学校・教育委員会に相談する
いじめに関しては、基本的にまず担任や学年主任など学校の教職員に相談できるとよいでしょう。
学校にはいじめの防止や早期対応の責任があり、対応マニュアルを整備しているところも少なくありません。
万が一、学校側が真摯に対応してくれない、あるいは改善が見られない場合は、教育委員会への相談を検討しましょう。
教育委員会には、学校に対して指導や調査を行う権限があります。
学校内で解決が難しいと感じたときは、ためらわず次のステップに進むことも必要です。
警察や弁護士に相談する
いじめの内容が暴力、恐喝、性的被害など犯罪に該当する場合は、警察への相談が必要になるケースもあります。
被害届の提出や相談窓口を通じて、適切な保護を受けられる可能性があります。
また、損害賠償請求や加害者側との対応を進める必要があるときには、弁護士への相談も視野に入れておきましょう。
法的な支援は敷居が高いと感じられがちですが、近年では初回無料の相談窓口や子ども専門の支援団体と連携する弁護士も増えています。
緊急時の対応を把握しておく
お子さまが強いストレスを抱えていたり、命の危険が疑われたりするような場合には、通常の手順にこだわらずすぐに行動することが必要です。
たとえば、自傷行為の兆候がある、明らかな暴力行為が繰り返されているなどの場面では、110番通報や救急受診をためらわないようにしましょう。
その場でどうすればよいか分からないときは、警察相談専用ダイヤル「#9110」などの利用もおすすめです。
学校外の相談窓口を活用する
学校や家庭だけでは対応が難しいと感じたとき、外部の相談窓口を活用することも一つの手段です。
たとえば以下のような支援先があります。
- 文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)
- 各自治体の教育相談センター・子ども相談室
- 民間のカウンセリング機関やNPO団体
こうした窓口は、保護者様だけでなく、お子さま本人が匿名で相談できる場合もあります。
「どうしたらよいか分からない」と感じたときこそ、誰かに話してみることが、前に進む第一歩になります。
小学生のいじめ相談は「不登校こころの相談室」へ

小学生のいじめは、ふざけ合いに見える言動の裏で深刻な苦しみが進行していることがあります。
本人がつらいと感じていれば、それはいじめに該当するものです。
特に小学生は、言葉で助けを求めるのが難しいことも多く、保護者様の気づきと寄り添い方が大きな鍵になります。
また、いじめの背景には、本人の特性や家庭の状況、学校との関係性などが複雑に絡み合っており、単純に原因を特定することは難しいものです。
冷静に状況を整理し、必要に応じて学校や外部機関と連携していく姿勢が大切です。
「いじめかもしれない」と感じながらも、どう対応すればいいのか分からないこともあるでしょう。
そのようなときは、不登校こころの相談室のAI診断を活用してみてください。
無料で数分の質問に答えるだけで、状況に応じた対応のヒントを得ることができます。
いじめ問題を家庭だけで抱えこまず、問題を整理するきっかけとして、ぜひご利用くださいね。