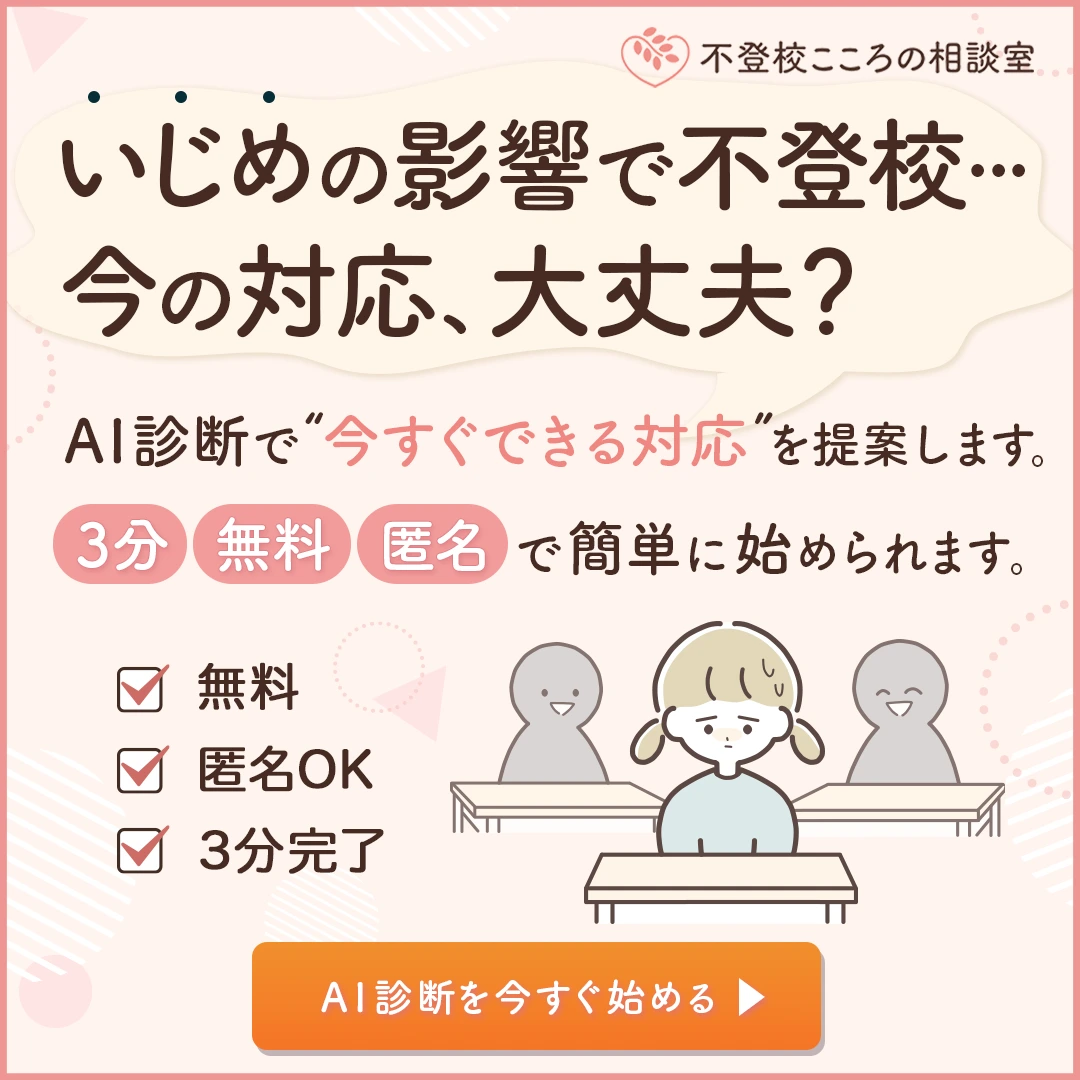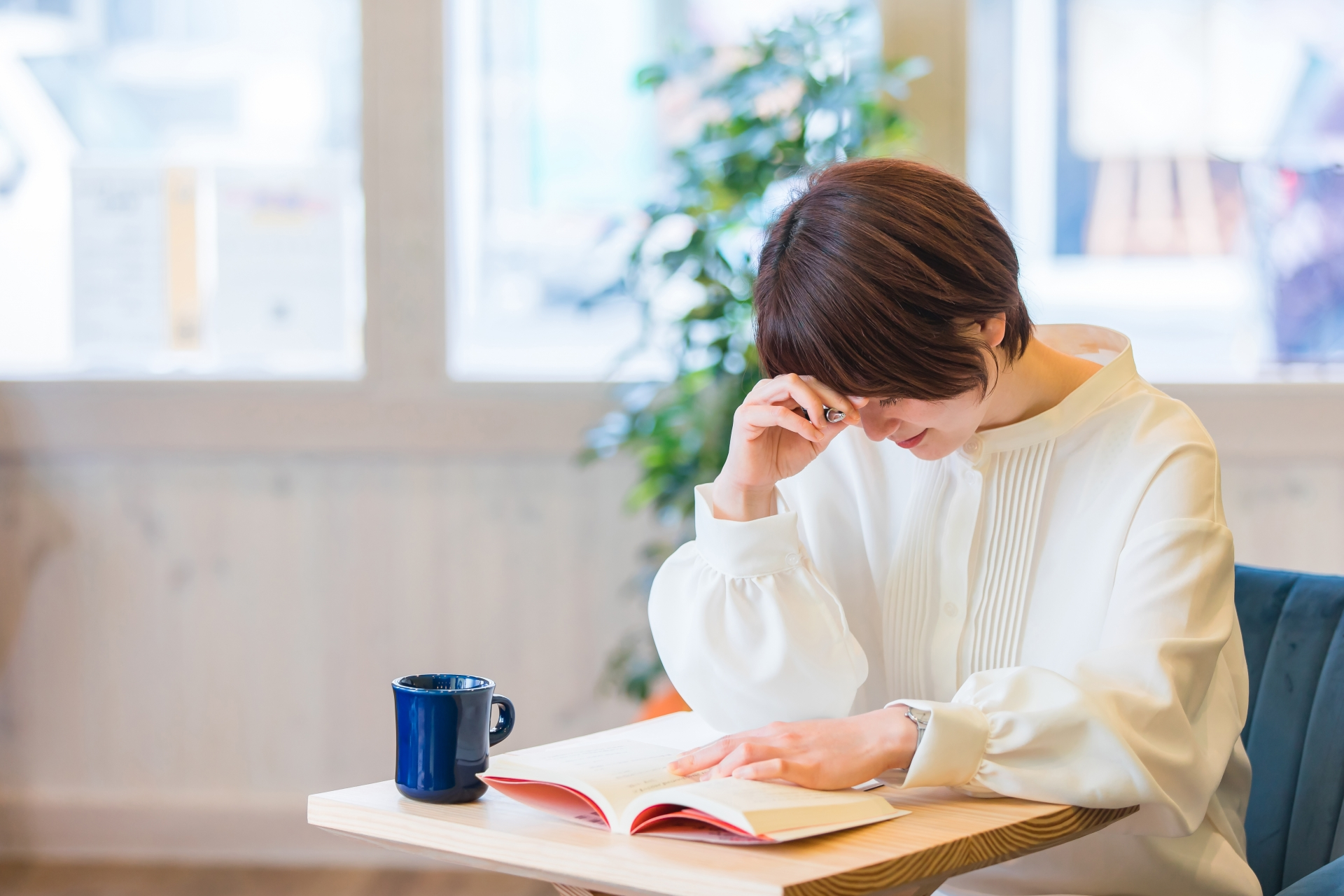目次
いじめ加害者の親がとるべき対応

お子さまがいじめの加害者となったとき、保護者様は大きなショックを受け、どう対応すべきか戸惑ってしまうのではないでしょうか。
しかし、感情が揺れ動くなかでも、冷静に状況を把握し、適切な行動をとる必要があります。
ここでは、いじめの加害者の保護者様がとるべき基本的な対応を整理します。
事実確認をする
まずは、いじめと言っても具体的には何が起きたのか、事実を冷静に確認することが大切です。
学校の説明だけで判断せず、お子さまの話にも耳を傾け、状況を多角的に把握しましょう。
問い詰めるのではなく穏やかに尋ねることで、お子さまも話しやすくなります。
保護者様が落ち着いて対応することで、必要な支援や改善の糸口が見えやすくなります。
被害者への対応を学校と相談する
いじめ被害を受けたお子さまへの対応は、保護者様だけで決めるのではなく、学校と相談しながら慎重に進める必要があります。
特に、謝罪の方法やタイミングは、被害者側の気持ちに十分な配慮が必要です。
お子さまがいじめの加害者となったとき、親として誠心誠意対応したいと考えるのは、ごく自然なことです。
しかし、文部科学省の指針でも、加害者と被害者の接触には慎重さが求められています。
誠意を持って対応することが大切ですが、再び傷つけてしまうことがないよう、学校との連携を忘れずに進めていきましょう。
(参考:文部科学省 いじめ問題の対応について、文部科学省 いじめ対策Q&A)
加害の背景を理解する
いじめの加害行動には、表面的な“悪意”だけでなく、さまざまな心理的背景が関係していることがあります。
お子さまへの対応を検討するにあたって、まずはその背景を知ることが大切です。
ただ叱るだけでは、その根本にある問題を見逃してしまうかもしれません。
具体的には、以下のような要因がいじめの加害行動につながるケースがあります。
- 自己肯定感の低さ:自分の価値を感じられず、他者を見下すことで優位に立とうとする
- 家庭や学校でのストレス:孤立、不安、過度なプレッシャーなどが攻撃的な言動に表れる
- 共感力の未発達:相手の気持ちを想像する力が育っておらず、傷つけることへの実感が乏しい
- 仲間関係の同調圧力:誰かに逆らえず、雰囲気で加害行動に加わってしまう
こうした背景を理解することは、いじめの再発防止のためにも不可欠です。
保護者様がお子さまの内面に目を向け、共に考える姿勢を持つことで、サポートの方向性が定まっていきます。
家庭でできるいじめ加害者への支援

我が子がいじめ加害者であるという事実に直面したとき、保護者様は「親として何をすべきなのか」と強い責任を感じることもあるでしょう。
学校での対応と並行して、家庭での関わり方を見直すことは、お子さまの心を支える上で非常に重要です。
ここでは、保護者様が日常生活の中でできる関わり方や支援の工夫について、紹介します。
感情的な叱責は避ける
いじめが発覚したとき、怒りや動揺からお子さまを強く叱ってしまうことは少なくありません。
しかし、感情的な叱責はお子さまの心を閉ざし、行動を振り返る機会を奪ってしまうこともあります。
いじめの行動は否定しても、気持ちには寄り添う姿勢が大切です。
保護者様の冷静な対応は、お子さまに安心感を与え、反省や変化につながるきっかけになります。
本音を引き出す関わり方をする
加害行為の背景には、不安や孤独、ストレスなど、お子さま自身が抱える苦しさが隠れていることもあります。
それに気づくためには、日々のコミュニケーションが重要です。
一方的に注意するのではなく、「最近どう?」とさりげなく話しかけたり、一緒に過ごす時間を意識的に増やしたりすることで、少しずつ心の距離が縮まるでしょう。
無理に問い詰めるのではなく、話したいときに話せる空気を作ることが、本音を引き出すための第一歩です。
家庭環境を見直す
お子さまの加害行動には、家庭内の雰囲気や関係性が影響している場合もあります。
たとえば、日常的に否定的な言葉が多かったり、きょうだい間で競争が激しかったりすると、無意識のうちに攻撃的な行動を学んでしまうことがあるのです。
家庭の中が安心できる場所であるかどうかは、子どもの心の安定に大きく関わります。
「どうせ言っても聞いてくれない」と思わせない関係作りが、いじめの再発防止にもつながります。
いじめ加害者へのカウンセリングの必要性

いじめの加害行動には、内面の葛藤や感情が関わっていることがあります。
だからこそ、カウンセリングを通して、いじめという行動そのものだけでなく「心」に目を向けることが求められます。
ここでは、いじめ加害者に対してカウンセリングがどのような役割を果たすのか、また保護者様にとってどのような助けになるのかについて解説します。
いじめの根本的な原因にアプローチできる
カウンセリングでは、いじめという行動の奥にある感情や思考の癖に目を向けます。
表面的な反省だけでは再発を防ぐのは難しいものです。
専門家のサポートを通じて、自分の気持ちを整理し、他者との関係を見つめ直すことが必要なケースもあります。
加害者となった根本的な原因に丁寧に向き合うことは、再発防止だけでなく、お子さまの健全な心の成長にもつながります。
支援が必要な存在だと捉えることができる
「いじめをした子=悪い子」と決めつけてしまうと、親子関係の修復は難しくなります。
しかしカウンセリングでは、加害者である前に「支援を必要としている子」として捉える視点が大切にされます。
行動の背景にある不安や孤独に目を向けることで、保護者様自身もお子さまを新しい視点で見られるようになるかもしれません。
親子関係を見直すきっかけになる
カウンセリングは、お子さまだけでなく保護者様にとっても意味のある時間です。
親子での関わり方を振り返り、必要に応じて対話の仕方や接し方を見直すことで、関係の改善につながることがあります。
親子の距離感を整えることで、家庭内の安心感も高まります。
子どもだけでなく親のケアもできる
カウンセリングは、お子さまのためだけの場ではありません。
お子さまのいじめ問題によってストレスや罪悪感を抱える保護者様にとっても、自分の気持ちを整理できる貴重な時間になります。
カウンセリングを受けることによって、必要以上に自分を責めずにすみ、次の一歩を前向きに考える余裕も生まれるでしょう。
いじめ加害で悩んだときの相談先

いじめに関する悩みを家庭だけで抱え続けることは、大きな負担になります。
ここでは、カウンセリングをはじめ、いじめ加害で悩んだときの主な相談先を紹介します。
学校内のスクールカウンセラー
多くの学校にはスクールカウンセラーが配置されており、いじめに関する相談も受け付けています。
学校という身近な場所で相談できることは、保護者様やお子さまにとって安心材料になるでしょう。
ただし、相談内容が学校内で共有される場合があることを理解しておきましょう。
まずは担任や学年主任を通じて、連携を図ることが大切です。
医療機関や自治体の相談機関
地域の子ども家庭支援センターや児童相談所などでは、いじめに関する相談を受け付けています。
また、精神科(児童精神科)や心療内科などの医療機関では、必要に応じてカウンセリングや治療を受けることも可能です。
家庭だけで悩みを抱えるのではなく、外部の専門機関を頼ることで、客観的な視点や専門的な支援を受けることができます。
オンラインカウンセリング
最近では、オンラインでカウンセリングを受けられるサービスも広がっています。
時間や場所にとらわれず、自宅から相談できる点が大きな魅力です。
いじめ問題のように、対面では話しづらい内容も、画面越しなら話せるというお子さまや保護者様も少なくありません。
家庭での対応と並行しながら支援を受けたい場合に適した選択肢です。
子どもがいじめの加害者になったとき、どんな支援を選ぶべき?

お子さまがいじめの加害者となったとき、保護者様にのしかかる責任感や不安は計り知れません。
被害者への申し訳なさを抱えつつも、「どう支え、どう導けばいいのか分からない」と悩むのは自然なことです。
そんなときこそ、一人で抱え込まず、第三者の専門的な力を借りることが大切です。
「不登校こころの相談室」では、臨床心理士や公認心理師といった専門カウンセラーが、加害・被害どちらの立場でも丁寧に寄り添いながら、保護者様と一緒に解決の糸口を探していきます。
オンラインで相談できるため、ご自宅から安心してご利用いただけますし、保護者様ご自身の心のケアにもつながります。
さらに、最初の一歩としてAI診断をご活用いただけます。
数分で答えられるチェック形式に取り組むだけで、お子さまの状況や保護者様の不安を整理でき、その結果をもとに最適なカウンセラーをご案内することも可能です。
抱え込みすぎる前に、この小さな一歩から始めてみてください。