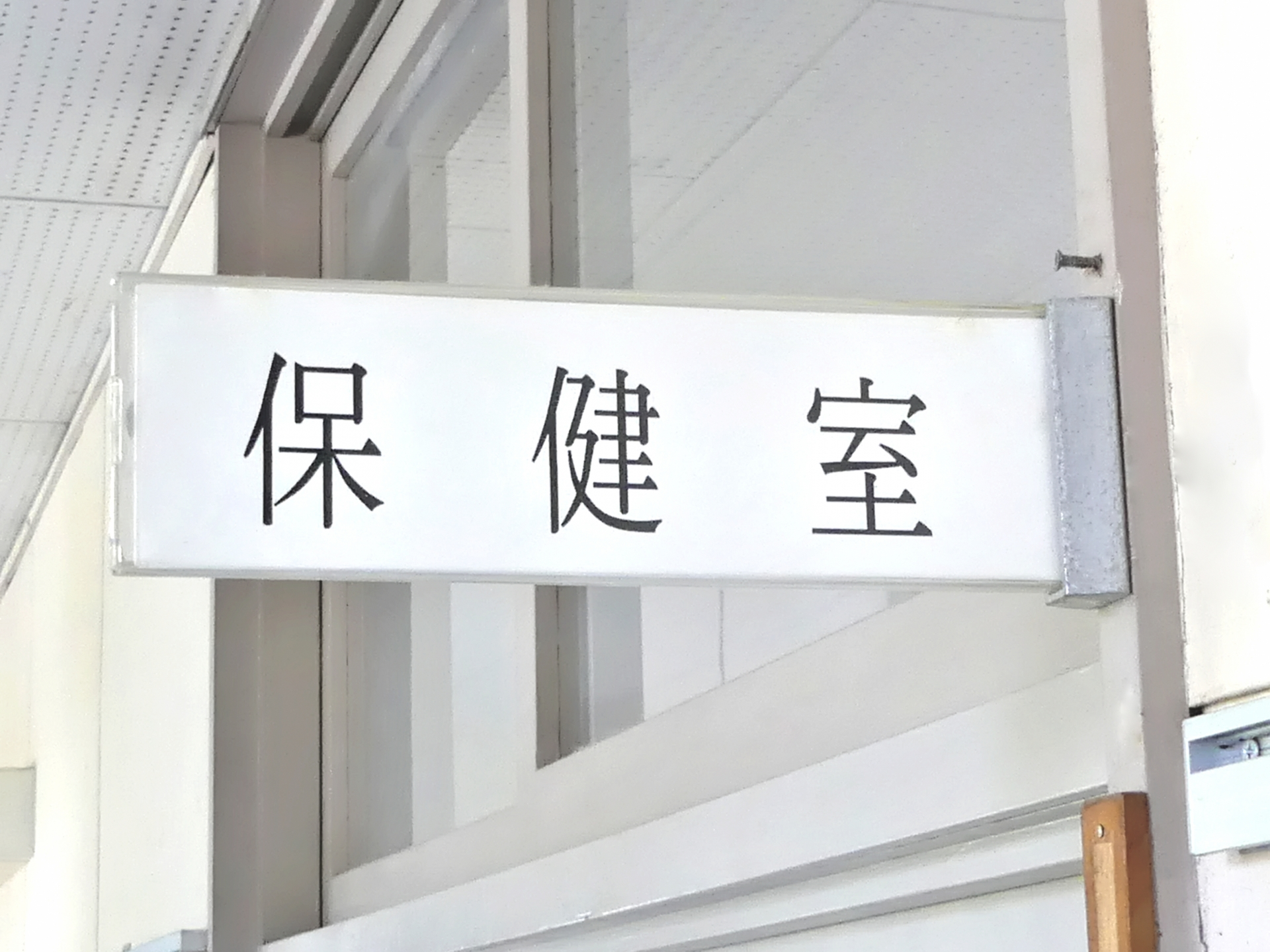目次
不登校から行けるようになったきっかけ

不登校から学校に行けるようになったお子さまには、どのようなどのきっかけがあったのでしょうか?
ここでは、不登校を経験したお子さまが学校に行けるようになったきっかけを6つ紹介します。ただし、これらはあくまで一例です。お子さまに同じきっかけを作ろうと焦る必要はありません。
①先生との出会い
担任の先生が変わるタイミングで、学校に行けるようになったケースがあります。新しい先生がお子さまの気持ちに寄り添い信頼関係ができると、学校という場所へのハードルが下がる場合があります。
「怖い場所」から「信頼できる先生がいる場所」へと認識が変われば、一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。
②友達とのつながり
仲のいい友達からの手紙や連絡が、お子さまの心を動かし再び学校へ行けるようになる例もあります。自分の様子を気にかけてくれる友達がいると「やっぱり友達っていいな」と思うお子さまもいるでしょう。
直接会うのは難しくても、メッセージのやり取りで友達とつながっていれば、何かのタイミングで「久しぶりに学校へ行ってみようかな」という気持ちにつながる可能性があります。
③趣味や好きなことの発見
不登校になって家にいると、絵を描く、音楽を聴く、ゲームをするなど自分の好きなことに没頭できる時間ができます。好きなことをしている時間は、心が癒されるもの。その時間が、お子さまの心にエネルギーを貯めていきます。
また、好きなことを通じて自信がつくケースもあるでしょう。例えば、イラストを描く技術が上がったり、ギターを上手く弾けるようになったりすると「自分にもできる」という実感が湧いてきます。
そして、好きなことに没頭して心が元気になると、外の世界にも目を向けてみようと前向きな気持ちが自然に湧いてきます。
④家族の対応の変化
家族が不登校を理解し、対応が変わっていくとお子さまの心の負担は軽くなっていきます。最初は「学校に行かなければ」とプレッシャーを感じていたかもしれません。しかし、家族が学校へ行けない状況を責めなくなると、お子さま自身も自分を責めるのをやめられます。
具体的には、毎朝「学校は?」と聞くのをやめる、学校の話題を無理に出さない、お子さまの好きなことを否定しない、といった姿勢です。また、お子さまが朝起きてきたときは、大げさに褒めるのではなく「おはよう」と普通に挨拶するだけで十分かもしれません。特別扱いせず、家族が「学校に行かない状態」を受け入れるとお子さまは安心できるでしょう。
家族の対応が変わるのは、家庭が安心できる場所になるということです。その安心感は、不登校のお子さまが外の世界に踏み出すための土台になります。
⑤時間の経過
特別なきっかけがあったわけではなく、ただ時間が経過して学校に行けるようになるケースもあります。お子さまの成長過程において、考え方や気持ちの変化が積み重なり「そろそろ学校に行ってみようかな」といった気持ちが自然に湧いてくる場合もあるでしょう。
時間の経過とともに、お子さまの心の中では少しずつ変化が起きています。不登校になった最初のころは、部屋から出られなかったかもしれません。しかし、半年後にはリビングで家族と過ごせるようになり、やがて外出できる日が来るでしょう。
ただし、時間が経てば必ず行けるようになるわけではありません。その間、家庭が安心できる場所であり続けることが大切です。
⑥進路を意識
お子さまが中学3年生の場合、進路を考える時期がきっかけになるケースもあります。「高校に行きたい」「将来こんなことがしたい」などの目標ができると気持ちは変化していくものです。
未来を考えられるようになったお子さまは、自分の進路を意識して動き出す場合があります。
不登校から行けるようになったきっかけに共通するポイント

不登校から学校に行けるようになったきっかけはさまざまで、実はそこには共通するポイントがあります。ここからは、不登校から学校に行けるようになった多くのケースに共通するポイントを解説します。
安心安全な場所がある
学校に行けるようになるには、心から安心できる場所が必要です。安心できる場所とは、自分を否定されない場所です。それは家庭であったり、カウンセリングルームであったりお子さまによって違うかもしれません。
「学校に行けない自分」を責められず、ありのままを受け入れてもらえる。そうした環境で、お子さまは少しずつ回復していきます。安心できる場所は、外の世界に踏み出すための土台になります。
成功体験の積み重ね
学校に行けるようになったお子さまの多くは、小さな成功体験を積み重ねています。いきなり学校に行けるようになったわけではありません。朝起きられるようになった、食事を家族と食べられるようになった、外出できるようになったなど、日常生活での小さな変化も成功体験です。
成功体験は、自己効力感を高めます。「自分にもできるかもしれない」という気持ちが、次の一歩を踏み出す原動力になるでしょう。
自己肯定感の回復
不登校になると、多くのお子さまは自己肯定感が著しく低下します。「学校に行けない自分は価値がない」と思い込んでしまうのです。しかし、家族や周囲の人からの理解やサポートを得て自己肯定感が回復していくと、少しずつ新しいことにチャレンジする勇気が湧いてきます。
不登校から行けるようになったきっかけづくりに必要なこと

不登校から行けるようになったきっかけや共通点を理解できても、実際に保護者様は何をすればいいのでしょうか?きっかけを作るといっても、無理に何かをさせるという意味ではありません。お子さまが自然に前を向けるような環境を整えるということです。
ここでは、保護者様ができることについてお伝えします。
焦らず待つ
最も大切なのは、焦らず待つ姿勢です。「いつになったら学校に行けるのだろう」といった不安は、保護者様なら誰もが抱きます。しかし、焦りがお子さまに伝わってしまうとそれはプレッシャーになってしまいます。
焦らず待つといっても、何もしないわけではありません。お子さまの回復を信じて、適切な距離を保ちながら見守るということです。不登校になったお子さまの心のエネルギーが回復するには時間がかかるでしょう。数週間で変化が見えないからといって、焦る必要はありません。
また、学校にいけるようになるきっかけはお子さまによって違います。しばらく休んだらまた学校に行く気力が戻る子もいれば、1年以上かかる子もいるもの。ほかの子と比べて焦っても意味がありません。
変化を認める
お子さまの小さな変化を見逃さず、認めてあげるのも大切です。朝起きて部屋から出てきた、顔を洗ったなど、今までみられなかった小さな変化に気づきましょう。
ただし、大げさに褒める必要はありません。気づいて認めるだけで十分です。変化を認めるのは、お子さまの努力を認めることにつながります。学校に行けなくても、お子さまは毎日何かしら頑張っています。その頑張りを認めてあげましょう。
選択肢を広げる
学校に行くことだけが正解ではありません。フリースクール、オンライン学習、通信制高校など、学びの場は学校だけではありません。学校以外にもさまざまな選択肢があるので、お子さまに情報を提供するのは大切です。
「学校に行けなくても道はある」という安心感が、かえって「学校に行ってみようかな」といった気持ちにつながる場合もあります。また、学校でも選択肢は広げられます。例えば、別室登校や午前中だけ登校するなど柔軟な形を学校側と相談するのもいいでしょう。
別室登校や教室復帰までのステップについては、こちらの記事でくわしく解説しています。ぜひ、参考にしてください。
- こちらもチェック
-

別室登校とは?過ごし方や教室復帰までのステップをわかりやすく解説します
お子さまが「学校には行けるけれど、教室には入れない」と感じているとき、どう対応すればよいか悩んでしまう保護者様は多いのではないでしょうか。 そのような状況の中で、選択肢として挙がるのが「別室登校」です...
続きを見る
不登校から行けるようになるきっかけが見つからないとき

ここまで、学校に行けるようになったきっかけや保護者様ができることをお伝えしました。しかし、「どれも当てはまらない」「試したけどダメだった」と感じる保護者様もいるかもしれません。
きっかけはすぐには見つかりませんし、不登校からの回復に時間がかかる場合もあります。ですので、「いつになったら学校へ行けるようになるのか」といった不安は一旦手放してください。
また、きっかけが見つからないときこそ、保護者様自身のケアも大切です。お子さまの不登校で心が疲れていると、小さな変化を見逃してしまう場合があります。保護者様が心身ともに健康でいることが、お子さまを支える力になります。
きっかけは、予期せぬところから訪れる場合も。「これが良かったのか」と、あとから気づくときもあれば、いくつかの要素が重なって突然訪れる場合もあるでしょう。なかなか変化が見えなくても、お子さまの心は少しずつ動いているものです。焦らず、諦めず、お子さまのペースを信じて見守っていきませんか?
そして、悩みを一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも検討してください。専門知識のあるカウンセラーへの相談で保護者様の気持ちが整理される場合もあります。また、適切な関わり方を知ることでお子さまとの関係に新たな気づきが得られるかもしれません。
きっかけが見つからず心が疲れてしまったときは、こちらの記事も併せてご覧ください。心が軽くなるヒントをお伝えしています。
- こちらもチェック
-

不登校の子どもの親が限界を感じたときの対処法|心が軽くなる5つのヒント
不登校のお子さまへの対応に、心身ともに限界を感じていませんか。そんなふうに感じるのは、これまでお子さまのために懸命に向き合ってきた証しでもあります。 「もう無理かもしれない」と限界を感じるときは、心の...
続きを見る
最後に | 「不登校こころの相談室」ができること

不登校から学校に行けるようになったきっかけは、先生との出会い、友達とのつながり、家族の対応の変化など、一人ひとり異なります。保護者様ができるのは、焦らず待つ、小さな変化を認める、そして選択肢を広げることです。きっかけは必ず訪れます。ただし、そのタイミングはお子さまそれぞれで予測できません。
そのため、「きっかけを待つ間、どう過ごせばいいの?」「不登校の我が子の変化を見逃していない?」そんな疑問や不安を感じている保護者様は多いのではないでしょう。
「不登校こころの相談室」では、オンラインで全国どこからでも、お子さまの状態に応じた具体的なサポートを提供しています。きっかけを見逃さないための関わり方、今必要な働きかけについて、経験豊富なカウンセラーがアドバイスします。
まずは無料のAI診断で、お子さまの現在地を確認してみませんか?いくつかの質問に答えるだけで、お子さまが今どの段階にいるのか、どのような関わりが適しているかが見えてきます。診断結果をもとに、お子さまに合ったカウンセラーのご紹介も可能です。きっかけは突然訪れる場合もあれば、少しずつ準備が整って訪れることもあります。その準備を「不登校こころの相談室」と一緒に進めていきましょう!