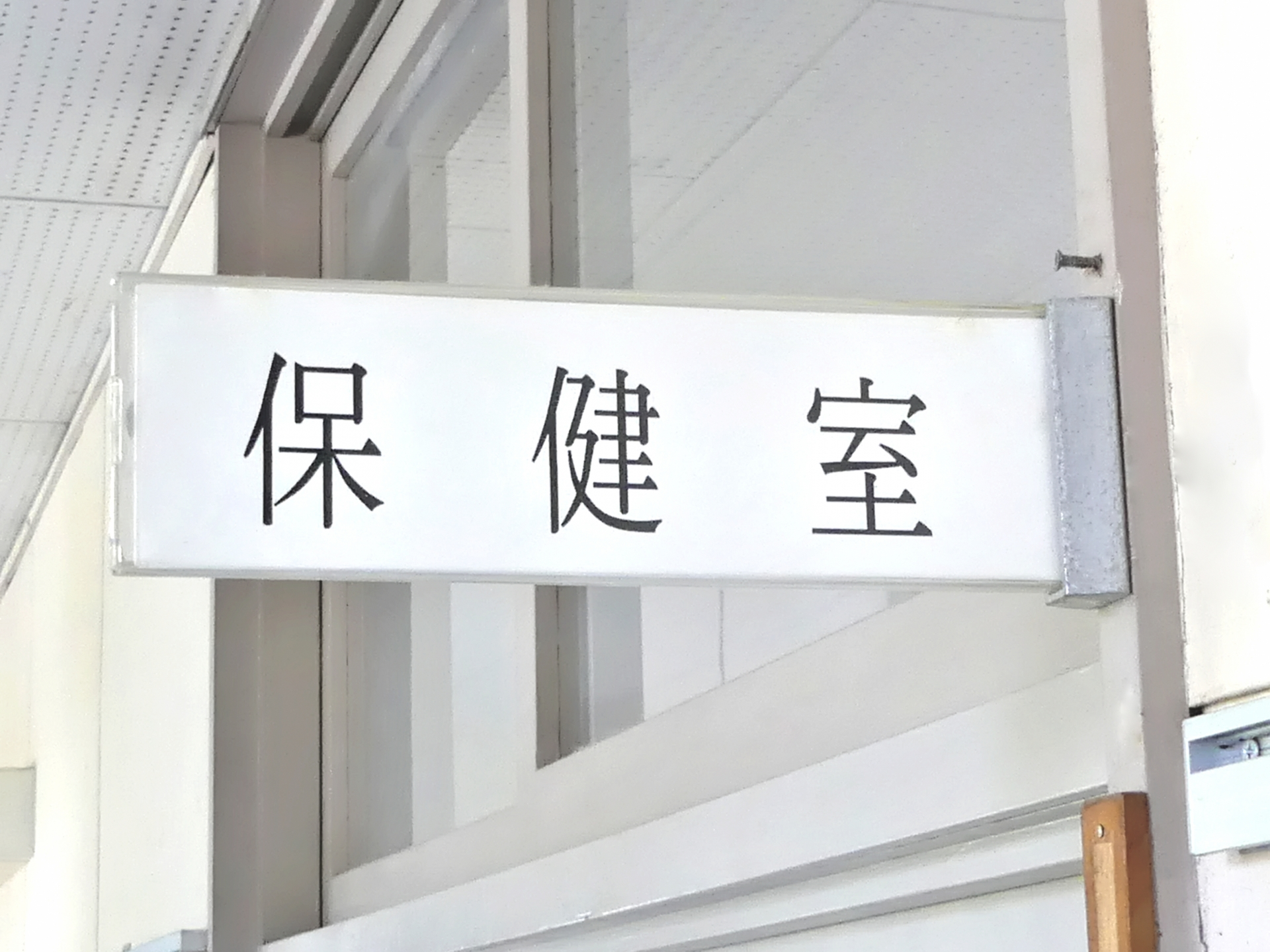目次
不登校の子どもがゲームばかりする3つの理由

お子さまがゲームばかりしていると「うちの子はゲーム依存なのかも…」「怠けているだけなのでは?」と考えてしまう保護者様は多いかもしれません。
しかし、不登校の子どもがゲームに夢中になるのは、決して甘えや怠けではありません。お子さまなりの理由があって、ゲームという手段を選んでいるのです。
ここからは、なぜ不登校になるとゲームばかりするのか主な理由を3つに分けて詳しく解説します。
①現実逃避としてのゲームの役割
不登校の子どもにとって、ゲームは現実のつらさから逃れられる場所です。不登校のお子さまの多くは、以下のような気持ちを抱えています。
- 「学校に行けない自分はダメな人間だ」という自己否定感
- 「みんなに遅れをとってしまった」という焦燥感
- 学校での嫌な出来事や人間関係の悩み
- 将来への漠然とした不安感
ゲームの世界に入ると、一時的にでもこうした苦しさを忘れられます。学校のことを考えると胸が苦しくなったり、不安で眠れなくなったりする子どもにとって、ゲームは心の痛みを和らげてくれる薬のような存在かもしれません。
また、現実では「失敗ばかりしている自分」でも、ゲームの中では「活躍できる自分」になれます。現実の世界で自信を失ってしまった子どもが、ゲームの中で自分の価値を確認しているのでしょう。
ゲームばかりして現実逃避していると批判的に見るのではなく、「今はそれだけ心が疲れているんだな」「ゲームが心の支えになっているんだな」と理解してあげる姿勢が大切です。現実逃避は決して悪いことではなく、心を守るための自然な反応なのです。
②ゲームの世界で得られる満足感
現実の世界で挫折感や無力感を抱えている不登校の子どもにとって、ゲームは達成感や満足感を得られる場所でもあります。ゲームで得られる満足感には、主に以下のような種類があります。
- レベルアップや目標を達成できる
- オンラインでほかのプレイヤーから認められる
- やればやるほど強くなる
現実では友達がいなくて孤独を感じている子どもも、ゲームの中では仲間とのつながりを感じられるのです。
また、ゲームには明確な目標設定があり、努力すれば必ず結果が出るといった特徴があります。現実の世界では「頑張ってもうまくいかない」「努力しても報われない」と感じている子どもにとって、ゲームの仕組みはとても魅力的に感じられるでしょう。
③時間を埋める手段としてのゲーム
不登校になると、今まで学校で過ごしていた時間が空いてしまいます。朝から夕方まで、何をして過ごせばよいのかわからず、途方に暮れてしまう子どもも少なくありません。ゲームが時間を埋める手段となる理由は以下の通りです。
- 学校にいた時間をどう過ごせばいいのかわからない
- 友達が学校にいる間の寂しさをまぎらわせる
- 不登校の状況への後ろめたさを軽減
友達が学校に行っている時間帯は、同年代の子どもと遊んだり話したりする機会がありません。一人で家にいると寂しさや孤独感が募ってしまうため、ゲームがその寂しさをまぎらわせてくれる相手になっているのです。
このように、不登校の子どもがゲームばかりするのは、それぞれに深い理由があります。単純に「ゲームが好きだから」「楽しいから」といった理由だけではないと理解することが、適切な対応への第一歩といえるでしょう。
ゲームばかりの不登校子どもへの適切な対応方法

お子さまがゲームばかりしている状況を見ていると「何とかしなければ」と焦ってしまう気持ちはよくわかります。しかし、その気持ちから急激な対応をしてしまうと、かえって状況を悪化させてしまうケースも。
ゲームを完全に悪者扱いするのではなく、上手に付き合いながら、少しずつお子さまの世界を広げていくことが重要です。
ここでは、不登校でゲームばかりしているお子さまに対して、保護者様ができる具体的な対応方法をお伝えします。
ゲームを無理に取り上げるのは逆効果
「ゲームさえなくなれば…」と考えて、ゲーム機を隠したり取り上げたりしたくなる保護者様もいるのではないでしょうか?しかし、無理にゲームを取り上げてしまうと、多くの場合逆効果になってしまいます。
ゲームを取り上げて起こりうる問題には、以下のようなものがあります。
- 安らぎの場所を奪われ、さらに追い詰められる
- 信頼関係が壊れ、コミュニケーションが取れなくなる
- 暴言や暴力など、攻撃的な行動に出る可能性がある
不登校の子どもにとって、ゲームは単なる娯楽ではありません。心を守るための大切な手段であり、生きる支えとなっている場合もあるのです。それを急に奪われると、お子さまは「最後の居場所まで奪われた」と感じてしまいます。
無理やりゲームを取り上げても、根本的な不登校の原因は解決されません。学校での人間関係の問題、勉強への不安、将来への心配などが残ったままでは、ゲームがなくなっても別の問題が生じてしまいます。
段階的なゲーム時間のコントロール
ゲームを完全に禁止するのではなく、お子さまと一緒に時間をコントロールしていく方法を考えてみませんか?段階的にゲーム時間をコントロールする方法には、以下のようなアプローチがあります。
- お子さまとの話し合い:親が一方的なルール決めるのではなく、一緒に考える
- 現実的な目標設定:いきなり大幅な制限ではなく、小さな変化から
- 代替活動の準備:ゲーム時間を減らす分、ほかの楽しみを用意する
- 生活リズムの調整:食事や睡眠時間を基準にした時間管理
まずは、お子さまと「なぜゲーム時間を調整したいのか」について話し合ってみてください。「ゲームが悪い」という前提ではなく「もう少しほかのことも楽しめたらいいね」と、前向きな提案として伝えるのも大切です。
具体的には「夕食の時間だけはゲームをお休みして、家族で一緒に食べよう」「お風呂に入る時間を決めて、そこだけは区切りをつけよう」といった、生活の基本的な部分から始めるのもいいのではないでしょうか。
ゲーム以外の興味を引く活動の提案
ゲーム時間を減らすためには、お子さまが「やってみたい」と思えることを見つけるといいでしょう。たとえば、料理や映画鑑賞など家族で一緒にできる活動がいいかもしれません。
大切なのは、「楽しい」「やってよかった」と感じられる体験の積み重ねです。ゲーム以外にも楽しい日常があると実感できれば、自然にゲーム時間は減っていくものです。焦らず、お子さまのペースにあわせて、一緒に新しい楽しみを見つけていってください。
ゲームばかりの状態から抜け出すための長期的な支援

ゲームばかりしている状況を改善するには、短期的な対応だけでなく、長期的な視点での支援が不可欠です。ゲーム時間を減らすことだけに焦点を当てるのではなく、不登校の根本的な原因を理解しなければお子さまの心は回復しません。
ここでは、ゲームばかりの状態から抜け出すために必要な長期的な支援について解説します。
根本的な不登校の原因への取り組み
ゲームばかりしている状況を改善するには、なぜお子さまが不登校になったのか、その根本原因に向き合う必要があります。なぜなら、ゲームは症状であり、本当の問題は別のところにあるケースがほとんどだからです。
不登校の主な原因として、以下のような要因が考えられるでしょう。
- 学校での人間関係の問題
- 学習面での不安
- 家庭環境
不登校が続くと「自分はダメな人間だ」といった気持ちが強くなりがちです。お子さまの素敵なところや頑張っている様子を認めて、自信を取り戻していけるようなかかわり方を意識するといいでしょう。
親子関係の再構築と信頼回復
不登校とゲームの問題が長期化すると、どうしていいのかわからずストレスを溜め込んでしまう保護者様も少なくありません。「なぜゲームばかりするの?」「いつになったら学校に行くの?」といった言葉が増えるとお子さまはますます心を閉ざしてしまいます。
ゲームばかりしているお子さまに対して批判的な言葉を控え、なぜゲームから離れられないのかを理解する姿勢が大切。親子関係を再構築するためには、以下のような姿勢を心がけてください。
- 否定的な言葉を避ける
- お子さまの気持ちに共感する
- 小さな変化を認める
- 一緒に過ごす時間を作る
また、保護者様自身のメンタルケアも忘れてはいけません。お子さまの問題に悩み続けていると、保護者様も疲れ果ててしまいます。専門家に相談するなど、自分自身の心のケアも大切にしてください。
不登校とゲームにどう向き合えばよいのでしょうか?

お子さまが不登校でゲームばかりしている様子を見ると、保護者様は「このままで大丈夫なのだろうか」と強い不安や焦りを抱いてしまうものです。ですが、ゲームは単なる遊びではなく、現実逃避や安心感の確保、時間を埋める手段として機能していることもあります。
背景にある心の状態を理解することで、頭ごなしに否定するのではなく、お子さまの気持ちに寄り添った対応ができるようになるでしょう。
一方で、ゲームに没頭してしまう状況の裏には、不登校の根本的な要因が隠れていることも少なくありません。こうした課題には、専門的な視点と長期的な支援が必要になる場合があります。
「不登校こころの相談室」では、不登校やゲーム依存傾向に悩むご家庭を対象に、臨床心理士や公認心理師によるオンラインカウンセリングを提供しています。お子さまの心理状態を深く理解しながら、ゲームとの健全な付き合い方から不登校の根本的な解決まで、一緒に道筋を探していきます。
また、「いきなりカウンセリングに申し込むのは不安」という方には、数分で答えられるAI診断をおすすめします。チェック形式で気軽に取り組めるため、お子さまの状況や保護者様の気持ちを整理する手がかりとなり、その結果をもとに最適なカウンセラーをご案内することも可能です。
不安を抱え込む前に、まずはAI診断から安心して始めてみてください。