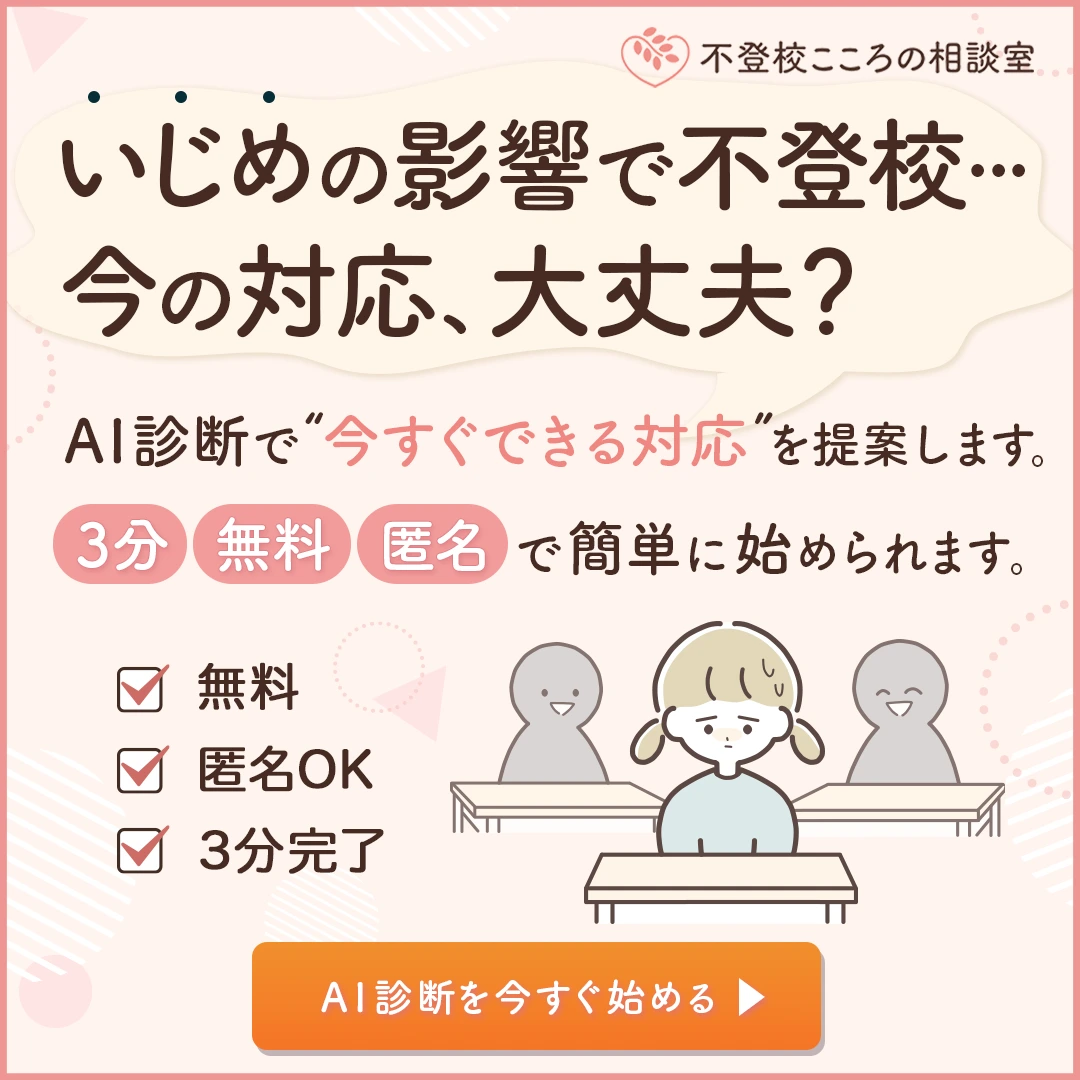目次
高校生のいじめの原因

中学生に比べて、自立心や進路への意識が高まる高校生。
しかしその分、人間関係も複雑になり、さまざまな原因でいじめが起きてしまいやすい時期でもあります。
ここでは、高校生ならではのいじめの原因について3つの視点から解説します。
成績や進路へのプレッシャー
高校生になると、定期テストや模試の結果が進路に直結する場面が増えていきます。
そのため、成績や進学先をめぐって、周囲との比較や競争が激しくなることが、いじめの一因となることがあるのです。
たとえば、目立って優秀なお子さまが嫉妬の対象になったり、逆に成績が思わしくないことをからかわれたりするケースがあります。
こうした場面では、「学力=人間の価値」といった誤った考え方が背景にあることも少なくありません。
進路への不安や焦りが強まるなかで、他者を攻撃することで自分の立場を保とうとする行動が、いじめにつながることがあるのです。
SNS上のトラブル
現代の高校生にとって、SNSは日常的なコミュニケーション手段となっています。
今や、スマートフォンを所持することが「普通」な風潮さえありますよね。
しかし、スマートフォンは便利さの一方で、いじめの温床にもなり得るリスクがあるものです。
たとえば、友人とのグループチャットから突然外されたり、SNS上で悪口が拡散されたりすることがあります。
「既読無視」「スタンプだけの返信」といったやりとりでも相手に不安や孤独感を与えることがあり、これがいじめのきっかけになることも珍しくありません。
対面での会話ではないからこそ、意図や真意が伝わりにくいこともあり、それがトラブルの元となります。
こうしたツールを活用したやりとりや、SNSの利用は、保護者様世代が体験してこなかったものですよね。
そのため、いじめが起きていても実態に気づきにくかったり、そもそもSNSがお子さまにとってどのような存在なのか、どれくらい日常の一部になっているものなのか、理解が難しかったりする部分があるでしょう。
SNS上でのいじめは、学校外の時間も続くものです。精神的なダメージが長引きやすく、周囲の大人が気づきにくい点でも注意が必要です。
上下関係やグループの複雑な関係
高校では、部活動や学校行事などを通じて先輩・後輩との関係が生まれます。
このような上下関係のなかで、立場を利用したいじめが起こることがあります。
また、同学年内でもグループの力関係や「ボス的存在」によって、人間関係が固定化しやすいのが高校生の特徴です。
とくに女子生徒はグループを形成しやすい傾向にあり、目に見えない序列のようなものが存在することもあります。
グループの暗黙のルールに従わなかっただけで無視されたり、違う友人と行動したことが理由で仲間外れにされたりすることもあるのです。
このような関係性の中では、「自分の居場所を守るために誰かを排除する」といった行動が生まれやすくなってしまいます。
集団の中でその力が強まると、それがいじめへと発展してしまうのです。
なお、いじめの原因については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

いじめが起こる原因は?文部科学省の指針や原因別の対処法を解説します
近年、いじめが大きな問題となっています。 いじめの原因はさまざまであり、原因を特定することが難しいケースも珍しくありません。 しかし、いじめが起こりやすい背景や原因を少しでも知っておくことで、家庭や学...
続きを見る
高校生のいじめに気づくサイン

高校生になると、感情を表に出すことを避けたり、「自分の問題は自分で解決しよう」としたりする傾向が強くなります。
そのため、いじめにあっていても大人が気づきにくいケースも少なくありません。
ここでは、いじめのサインとして保護者様に気にかけていただきたい4つの変化を紹介します。
口数が減る
以前よりも会話が減った、お子さまから話しかけてこなくなったという変化があれば、注意が必要です。
これは、心に負担を抱えていると人と話すこと自体が億劫になったり、気力が湧かなかったりするためです。
日常の何気ない質問に対しても短い返事が増えたり、「別に」「普通」といったあいまいな言葉が多くなったりした場合、内面に悩みを抱えていることが予想されます。
高校生のお子さま本人にとっては「これ以上踏み込まれたくない」という防衛反応であることも考えられます。
このようなお子さまの沈黙や会話の減少は、いじめに限らず心理的なストレスの重要なサインといえるでしょう。
無気力になる
高校生のお子さまが、元々興味を持っていた趣味に手をつけなくなったり、何をしても楽しそうに見えなかったりするなど、無気力な様子が見られる場合もあります。
たとえば、休日に友人と出かけていたお子さまが家に閉じこもるようになったり、以前は熱心だった部活動への関心を失っていたりするような変化が、これに当てはまります。
学校生活の中でつらいことがあると、「どうせ何をしても無駄」と感じてしまい、やる気を失ってしまうことがあるのです。
気力の低下が見られるときは、無理に励ますよりも、そっと見守りながら変化の背景を探ることが大切です。
遅刻や欠席が増える
体調不良を訴えて休みがちになる、朝なかなか起きてこない、準備が遅くなるといった行動の裏にも、学校に行きづらい理由が隠れていることがあります。
朝になると急に「頭が痛い」「お腹が痛い」と訴えるようになったり、登校時間になると動きが鈍くなるようなときは、身体症状ではなく心理的ストレスが原因になっている可能性もあります。
また、いじめを受けている場合、学校そのものが怖い場所になっていることもあるのです。
出席状況の変化は、家庭でも比較的気づきやすいサインのひとつです。
頻度や傾向に変化が見られたら、さりげなく理由を尋ねてみるとよいでしょう。
携帯やSNSの使い方が変化する
スマートフォンやSNSは高校生の生活に欠かせないツールですが、使い方に急な変化があった場合は要注意です。
とくに、SNSを避けるようになったり、逆に画面を手放さなくなったりする場合は、ストレスを抱えているサインかもしれません。
具体的には、「通知が鳴るたびに顔色が変わる」「投稿や返信を極端に気にする」などの行動が見られることがあります。
SNS上での悪口や無視、グループからの排除といったいじめは非常に傷つきやすく、かつ大人が気づきにくいのが特徴です。
保護者様から見て、スマートフォンの扱い方に「なんとなくおかしいな」と感じる変化があれば、さりげなく声をかけてみることが大切です。
高校生がいじめを相談できない理由

いじめを受けていても、それを誰にも打ち明けられずに苦しんでいる高校生は少なくありません。
その背景には、思春期特有の心の成長や、対人関係に対する敏感さが関係しています。
ここでは、高校生がいじめを相談しづらいと感じる主な理由を3つ紹介します。
親への遠慮
高校生になると、自分の問題は自分で解決しようとする傾向が強まります。
これは、自立心が成長していると安心できる一方で、「親に心配をかけたくない」という気持ちからつらいことを隠してしまうこともあるため、注意が必要です。
たとえば、保護者様が仕事や家庭のことで忙しそうにしていると、「こんなことで相談するのは申し訳ない」と感じてしまい、言い出せなくなることがあります。
同時に、高校生になると「ちゃんとやれていると思われたい」という意識が強くなるのも重なり、いじめの事実を伏せてしまうのです。
お子さまが何も話さないからといって、何も起きていないとは限りません。
無理に聞き出すのではなく、日頃から話しやすい雰囲気を作ることが大切です。
自己否定や諦めの気持ち
いじめが長く続くと、「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまうことがあります。
その結果、相談するよりも、「耐えるしかない」「どうせ変わらない」と諦めてしまう心理に陥ることがあります。
なかには「自分さえ我慢すればいい」と考えて、苦しい状況を受け入れてしまうお子さまもいます。
このような自己否定の状態では、自分の気持ちを言葉にすることすら難しくなることもあるのです。
早い段階でお子さまの小さな変化に気づき、「それはあなたのせいじゃないよ」と伝えてあげることが、回復へのきっかけになることもあります。
弱さを見せたくないというプライド
高校生は子どもから大人への移行期にあり、自分の弱さを認めることに強い抵抗を感じる時期でもあります。
そのため、いじめを「恥ずかしいこと」「負けだ」と捉えてしまい、誰にも言えなくなるケースがあります。
とくに男子生徒のなかには、「男のくせに情けない」と思い込んでしまうお子さまもいます。女子生徒の場合も、「こんなことを話したらバカにされる」と感じてしまうことがあります。
こうした「プライド」が、相談という行動のハードルを上げてしまうのです。
思春期のお子さまが素直な気持ちを打ち明けるには、大きな勇気が必要です。
だからこそ、日頃から「話してくれてありがとう」と言える関係づくりが大切です。
高校生ができるいじめへの対応

いじめに悩んだとき、まず大切なのは「自分を守る」ための行動を考えることです。
周囲に助けを求めることは、決して弱さではなく、問題を前に進めるための大きな一歩です。
ここでは、高校生自身ができるいじめへの対応方法について、3つの視点からご紹介します。
信頼できる人に相談する
いじめの問題にひとりで向き合い続けるのは、非常に大きな負担になります。
まずは、信頼できる人に思いを打ち明けることが大切です。
相談相手は、保護者様や先生以外にも存在します。
スクールカウンセラー、部活動の顧問、友人、さらには外部の相談窓口など、少しでも安心して話せる相手を探してみましょう。
「相談=解決しなければならないこと」と考えすぎず、まずは誰かに話すことで心が軽くなることもあります。
証拠を残す
いじめの内容を客観的に示すためには、証拠を残すことが重要です。
状況を記録しておくことで、学校や第三者に相談する際に説得力が増し、対応につながりやすくなります。
たとえば、LINEのやりとりやSNSの投稿をスクリーンショットで保存したり、起こった出来事を日時とともにメモしておいたりする方法があります。
身体や持ち物への被害がある場合には、写真で記録しておくことも有効です。
証拠を集めることはただの準備ではなく、自分自身を守るための手段でもあります。無理のない範囲で行動に移してみましょう。
進路を見直す
いじめが原因で学校生活を続けることが難しくなった場合、転校や通信制高校、フリースクールなど、進路を見直すことも選択肢のひとつです。
つらいと感じる環境に身を置き続けることで、心身の健康を損なってしまうこともあります。お子さまの心を守るためにも、ときには大きな決断が必要かもしれません。
現在の環境にこだわらず、新たな道を模索することで心が落ち着くこともあります。
進路変更には勇気が必要ですが、「逃げること」は決して悪いことではありません。
むしろ、自分に合った環境を選ぶことは、未来を前向きに切り開くための決断といえるでしょう。
まずは情報を集め、信頼できる大人と一緒に選択肢を整理していくことが大切です。
焦らず、少しずつ方向を考えていくことで、新しい一歩が見えてくるかもしれません。
なお、こちらの記事では、いじめが起きたときの対処法をさらに詳しく解説しています。相談先も紹介しているため、あわせてご覧ください。
- こちらもチェック
-

いじめが起きたときの対処法は?困ったときの相談先を幅広く紹介します
いじめは絶対にあってはならないことであり、被害を受けたお子さまに多くの影響を及ぼすものです。 保護者様は、我が子がいじめの被害に遭わないことを切に願っていることでしょう。 そのような中で、万...
続きを見る
親ができるいじめへの対応

お子さまがいじめにあっていると知ったとき、保護者様自身も大きなショックを受けることでしょう。
しかし、そんなときこそ、安心できる存在としてお子さまを支える姿勢が求められます。
ここでは、保護者様にできる具体的な対応を3つの視点からご紹介します。
子どもが安心できる環境を整える
お子さまがつらい状況にあるとき、最も大切なのは「家が安心できる場所」であることです。
家庭で責められたり、無理に問い詰められたりすることで、さらに心を閉ざしてしまうことがあります。
まずは、話したがらないお子さまの態度を否定せず、いつでも味方でいることを伝えましょう。「話したくなったときは、いつでも聞くよ」と伝えるだけでも、お子さまの安心感につながります。
学校と連携する
いじめの問題に対応するためには、家庭だけでなく学校との連携が必要です。
ただし、本人の同意を得ずに学校へ動くと、かえって信頼関係を損なうことがあるため慎重に対応することが大切です。
まずはお子さまと一緒に、どのような対応が望ましいかを話し合い、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーと連携しましょう。
面談の際には、記録を元に事実を冷静に伝えることが、建設的な話し合いにつながります。
学校の対応に不安がある場合には、教育委員会や第三者機関に相談することも検討するとよいでしょう。
今後について親子で考える
現在の学校環境が合っていないと感じる場合には、今後の進路について親子で話し合うことも大切です。
いじめを受けているときには視野が狭くなり、「ここをやめたら終わり」と思い込んでしまいがちです。
そのようなときは、保護者様から「別の学校もあるよ」「今のままでなくてもいいんだよ」といった言葉をかけてもらうことで、お子さまの中に希望が生まれることもあります。
転校や通信制高校、フリースクールなど、さまざまな選択肢を一緒に調べてみるのもよいでしょう。
大きく環境を変えず、と考えるのであれば、まずは別室登校や保健室登校ができないか学校側にかけ合ってみるのも、一つの方法です。
大切なのは、どんな選択をしても「あなたを応援している」という気持ちを伝えることです。
いじめによる傷を癒す方法としてカウンセリングはとても有効です。以下の記事でくわしくを解説していますので参考にしてください。
- こちらもチェック
-

いじめにカウンセリングは必要?効果や選び方をわかりやすく解説します
いじめは、被害者の心を深く傷つける行為です。 いじめによって受けた心の傷は、後遺症となってその後の人生にも影響を与えることがあります。 いじめによる傷を癒すことができるのが、カウンセリングです。 いじ...
続きを見る
高校生のいじめに悩んだときは「不登校こころの相談室」へ

高校生のいじめは、本人の心に大きな負担を与えるだけでなく、進路や将来にも深く関わってくる深刻な問題です。
保護者様にとっても、どのように対応すればよいのか悩む場面が多いのではないでしょうか。
いじめの問題に直面したとき、家庭だけで抱え込まず、外部の支援を利用することも大切な選択です。
「不登校こころの相談室」では、いじめや不登校などの悩みについて、国家資格を持つカウンセラーがオンラインで丁寧にサポートしています。
どんな小さな不安でも、相談することで見えてくる解決策があるかもしれません。
お子さまが安心して毎日を過ごせるように、ぜひ一度ご利用を検討してみてくださいね。