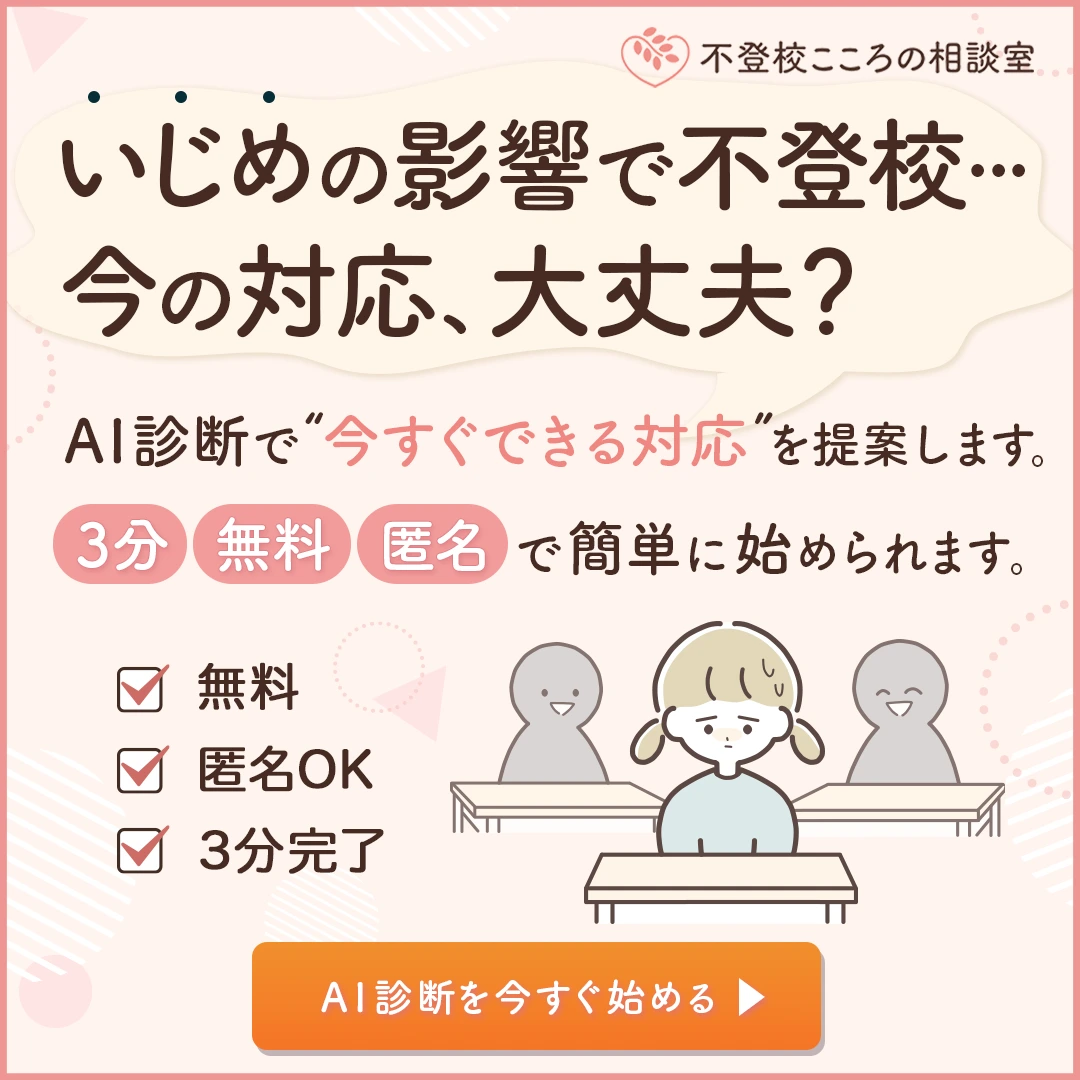目次
いじめの後遺症とは?

いじめは一時的な問題ではなく、お子さまの心身に長期的な影響を与えることがあります。
具体的には、次の3つにわけることができます。
- 心理的な影響
- 身体的な影響
- 社会的な影響
一つずつ詳しく解説します。
心理的な影響
いじめがお子さまに与える心理的な影響は非常に大きいものです。
いじめを受けている間、お子さまは「自分は価値がない」「周りから嫌われている」といった否定的な感情を抱えることが多く、この感情はお子さまの心に長く残ります。
実際、日本財団の調査によると、18~22歳の若者が自殺を検討したり自殺未遂をしようとした原因の半数を占めるのは、「いじめ」であることが明らかとなっています。
(参考:日本財団 第3回自殺意識調査)
いじめは、自己肯定感の低下を引き起こし、引きこもりにつながるケースも珍しくありません。
また、うつ病や不安障害といった深刻な心の病気に発展することもあります。
心の病気は早期の改善が難しく、場合によっては一生付き合っていくこともあるものです。
いじめは、お子さまの心に深刻な傷跡を残し、長期にわたって苦しめる恐れがあります。
保護者様は、いじめがお子さまの心に与える影響を理解し、サポートすることが大切です。
身体的な影響
いじめによって身体に異変や不調が起こることもあります。
身体的な影響は、直接的な暴力だけでなく、精神的なストレスが原因で引き起こされることが多いものです。
いじめによる精神的なストレスは自律神経の乱れを引き起こし、さまざまな身体症状として表れます。お子さまが訴える不調は、いじめのサインである可能性を示唆しています。
たとえば、学校に行く前になると腹痛や頭痛を訴える、夜眠れない、食欲がないといった症状が挙げられます。
実際に、いじめを苦に体調を崩し、学校を休むようになったというお子さまは少なくありません。
精神的な痛みが身体にも影響を及ぼすことは、珍しくありません。
いじめによる身体的な症状を見逃さず、お子さまが感じる体調不良の背景に心理的な問題がないかをしっかりと確認することが大切です。
社会的な影響
いじめは、お子さまの社会生活にも大きな影響を与えます。
たとえば、対人関係を築くのが難しい、不登校、引きこもりなどが挙げられます。
いじめによってお子さまは他人を信用できなくなり、対人関係を築くことが難しくなることがあるのです。
引きこもりの背景には、こうした社会的な不安が大きく関係しており、社会的に孤立することで引きこもりが加速するケースもあります。
いじめは、その後の人間関係にまで影響を及ぼすものです。
引きこもりを防ぐためには、早期に社会的なサポートを行い、孤立感を和らげることが重要です。
- こちらもチェック
-

いじめの後遺症は大人になっても残る?症状・人生への影響と回復の道
いじめは、被害者の心身に大きな苦痛をもたらす行為です。 いじめの被害者は、いじめられているその瞬間だけではなく、長期にわたって悩んだり苦しんだりすることがあります。これが、「いじめの後遺症」です。 で...
続きを見る
いじめによって引きこもりが起こる理由

いじめは、引きこもりの一因となることがあります。
いじめによって傷ついたお子さまが、学校という社会的な環境から逃げ出したいと思うのは自然なことでしょう。
いじめによって、お子さまは自分に自信を失い、他人との関係を築くことに対して恐怖を感じるようになります。
そして、学校や友達との関係が壊れてしまうと、お子さまは居場所を失い、孤立感を深めてしまいます。
「またいじめられるかもしれない」という不安から、外に出るのを恐れることもあるかもしれません。
このような状態が続くと、学校生活そのものに対して無力感を抱いて引きこもったり、引きこもりが加速したりする可能性があります。
いじめの影響でお子さまの心理状態が悪化すると、外の世界と繋がることが難しくなり、引きこもりが起こる可能性があります。
保護者様はいじめに気づいた時点でその影響を軽視せず、お子さまが安心して学校生活を送れるよう、早期に対策を立てることを心がけましょう。
いじめによって引きこもりになるときのサイン

いじめが原因でお子さまが引きこもりになってしまう前に、いくつかのサインが表れることがあります。
これらのサインを早期に察知することが、お子さまの心身の回復を早め、引きこもりを防ぐことにつながります。
代表的なサインは、次の5つです。
- 頻繁に体調不良を訴える
- 遅刻や早退が増える
- 無気力・無関心になる
- 会話が減る
- 身なりに無頓着になる
一つずつ詳しく解説します。
頻繁に体調不良を訴える
お子さまが頻繁に体調不良を訴えるようになると、心の不調が身体に表れているサインである可能性があります。
特に、いじめを受けているお子さまは、精神的なストレスから身体的な症状を発症することがよくあります。
たとえば、朝起きられない、学校に行くのが辛いという理由で腹痛や頭痛を訴えることがあるのです。
このような症状は「心身症」とも呼ばれるものです。
心身症とは、身体的には特に問題がなくても、精神的な不安や緊張が原因で表れる症状を指します。
お子さまが体調不良を訴え、学校に行くことを避けるようになった場合、いじめが影響している可能性を考えてみましょう。
症状が続く場合は、学校と連携を取りながら、医師やカウンセラーに相談することが求められます。
お子さまが体調不良を繰り返すと、次第に学校を休むことが習慣化してしまう可能性が高まります。
また、外出を避ける傾向が強くなるため、早期の対応が大切です。
遅刻や早退が増える
お子さまの遅刻や早退が増えた場合も、いじめが原因で引きこもりになるサインかもしれません。
学校に行くことが精神的な苦痛になっている場合、お子さまは無意識のうちに学校を避ける行動を取るようになります。
たとえば、遅刻や早退を繰り返すことで学校にいる時間を短くしようとしたり、いじめの加害者と顔を合わせる時間を避けようとしたりすることがあります。
また、登校時間になってもなかなか家を出ようとしない、という場合も注意が必要です。
遅刻や早退が増えた場合は、お子さまの様子を注意深く見守り、高圧的な態度ではなく、優しく話を聞くように心がけましょう。
無気力・無関心になる
お子さまが以前まで興味を持っていたことに対して、無気力になったり、無関心になったりした場合も、いじめが原因で引きこもりになるサインである可能性があります。
いじめによって心が疲弊してしまうと、何をする気も起きなくなり、以前好きだったことにも興味を示さなくなることがあります。
これは、お子さまが心を守るために、感情を抑え込んでいる状態とも言えます。
たとえば、以前は熱心に取り組んでいた部活動や習い事に全く参加しなくなる、趣味の話をしなくなる、好きなゲームやテレビ番組にも興味を示さなくなるなどの変化がみられることがあります。
また、一日中ぼんやりしている、何もせずに過ごしている時間が増えた、という場合も注意が必要です。
無気力な状態が続く場合は、お子さまの心に何らかの問題が起きている可能性を考慮する必要があります。
無理に何かをさせようとするのではなく、ゆっくりと休ませ、心身の回復を優先しましょう。
会話が減る
お子さまとの会話が以前よりも減った場合も、いじめが原因で引きこもりになるサインかもしれません。
いじめについて話したくない、保護者様に心配をかけたくない、話しても理解してもらえないと思っているなどの理由から、お子さまは会話を避けるようになることがあります。
これは、お子さまが孤立感を深めている状態とも言えます。
たとえば、返事が極端に少なくなる、質問に答えなくなる、自室に閉じこもる時間が増える、目を合わせようとしないなどの変化が見られることがあります。
また、以前はよく話していたのに、最近は「うん」「別に」など短い返事しかしない、という場合も注意が必要です。
会話が減った場合は、お子さまの気持ちに寄り添い、「何か困っていることはない?」「話を聞かせてほしい」など優しく声をかけ、じっくり話を聞くように心がけましょう。
無理に聞き出そうとすると、かえって心を閉ざしてしまう可能性があります。
身なりに無頓着になる
お子さまが以前よりも身なりに無頓着になった場合も、いじめが原因で引きこもりになるサインである可能性があります。
いじめによって自己肯定感が低下すると、外見への関心が薄れたり、身だしなみを整えることへの意欲を失ったりすることがあります。
これは、お子さまが自分自身を大切に思えなくなっている状態とも言えます。
具体的には、以前は気にしていた服装や髪型に全く気を遣わなくなる、服装が乱れている、清潔感が失われるといった変化が起こることがあります。
特に思春期であれば、日頃から流行に敏感で身なりを気にしているというお子さまも多いですよね。
このようなお子さまが身なりを気にしなくなったときは、変化に気づきやすいでしょう。
また、外出を極端に嫌がるようになる、鏡を見ることを避けるようになる、という場合も注意が必要です。
身なりへの関心が薄れていると同時に、外出へのエネルギーがなくなっている状態だと言えるでしょう。
身なりに変化が見られる場合は、お子さまの心の状態を心配し、注意深く見守るようにしましょう。
ただし、保護者様に直接指摘されると腹立たしさや恥ずかしさを感じるお子さまもいます。
お子さまのケアにあたる際は、「何か困っていることはない?」「最近、疲れているみたいだけど、大丈夫?」など、優しく声をかけることから始めましょう。
いじめが原因で引きこもりになったときの対処法

では、お子さまがいじめによって引きこもりになったときや、引きこもりになりそうなサインが見られたとき、保護者様にできることは何でしょうか。
いじめや引きこもりは、早期発見・対応が鍵となります。
保護者様としても、異変が起きた我が子にできるだけ早い段階で対処してあげたいと思いますよね。
ここでは、いじめが原因で引きこもりになったときの対処法について、6つ紹介します。
- 子どもの気持ちを優先する
- 安心できる居場所を作る
- 登校や外出を強要しない
- 学校や専門機関に相談する
- 子どものペースで外の世界とのつながりを作る
- 親自身のケアを忘れない
子どもの気持ちを優先する
お子さまがいじめによって引きこもりになったときは、お子さまの気持ちを最優先に考え、無理強いしないことが大切です。
お子さまは、いじめによって心に深い傷を負い、心身ともに疲弊している状態です。
無理に学校に行かせようとしたり外に出させようとしたりすると、かえって状況が悪化する可能性があります。
まずは、お子さまの気持ちを受け止め、「つらいね」「よく頑張っているね」など共感の言葉を伝えましょう。
お子さまの言葉に耳を傾け、否定したり批判したりせずにありのままを受け止めることが大切です。
お子さまの気持ちを理解し、寄り添うことが、回復への第一歩となります。
お子さまが安心して話せる雰囲気を作り、心の内を打ち明けられるようにサポートしましょう。
安心できる居場所を作る
保護者様は、お子さまが安心して過ごせる居場所を作るよう心がけましょう。
家庭が安心できる場所でなければ、お子さまは心を休めることができません。
お子さまの話をじっくり聞き、否定したり批判したりせずに受け止められるとよいですね。
お子さまがリラックスして好きなことができる環境を整えることも大切です。
たとえば、お子さまが好きな音楽を聴いたりゲームをしたりする時間を尊重できるとよいでしょう。
スマートフォンやゲームに過度にのめり込んでしまうお子さまとは、ある程度のルールを設定する必要がありますが、過干渉は逆効果です。
お子さまを信頼し、一人の人間として尊重する姿勢が大切なのです。
お子さまが引きこもってしまったときは、家庭がお子さまにとって安全基地となることが求められます。
家族との温かいつながりを感じられるように、積極的にコミュニケーションを取るように心がけましょう。
登校や外出を強要しない
登校や外出を強要することは避けましょう。
お子さまにとって学校や外の世界は、いじめの記憶と結びついているため、大きなストレスを感じる場所です。
無理に登校や外出を強要すると、恐怖心や不安感を増幅させてしまう可能性があります。
まずは、家庭内で安心して過ごせるようにサポートし、お子さまのペースに合わせて少しずつ外の世界との繋がりを作っていくことが大切です。
たとえば、最初は近所の散歩から始めて徐々に距離を伸ばしていく、あるいは、オンラインゲームなどで友達と交流する機会を作るなど、お子さまが抵抗なくできることから始めるのがおすすめです。
焦らず、お子さまのペースを尊重することが、結果として回復への近道となります。
保護者様はお子さまの気持ちに寄り添い、辛抱強く見守ることが大切です。
学校や専門機関に相談する
引きこもり中のお子さまや家庭の状況に応じて、学校や専門機関に相談することも検討しましょう。
学校には、担任の先生やスクールカウンセラーといった相談相手がいるため、いじめの状況や現在の状態を伝えて連携し、対応を考えていくことが大切です。
また、児童相談所や地域の相談窓口、精神科医や臨床心理士などの専門家にも相談することで、適切なアドバイスや支援を受けることができます。
具体的には、学校との連携ではいじめの事実確認や再発防止について話し合ったり、専門機関への相談では、お子さまの心のケアや今後の対応についてアドバイスを受けたりすることができます。
お子さま、保護者様ともに、一人で抱え込まず周りの力を借りることが大切です。
適切な支援を受けることで、お子さまの回復をサポートすることができます。
子どものペースで外の世界とのつながりを作る
お子さまのペースに合わせて、少しずつ外の世界との繋がりを作っていくことが大切です。
引きこもりの状態からいきなり学校復帰を目指すのではなく、お子さまが安心して外の世界と触れ合えるように、段階的なステップを踏んでいくことが重要です。
たとえば、前述の散歩といった外出はもちろん、趣味や習い事を始めてみるのもよいでしょう。
いじめで不登校や引きこもりになったからといって、活動を制限する必要はありません。
学校ではない場所であれば外出できると言うのならば、積極的にチャレンジしましょう。
自宅に引きこもり、社会とのつながりが完全に遮断される方が、後々の対応も難しくなります。
学習意欲のあるお子さまであれば、さまざまなお子さまに理解のあるフリースクールや教育支援センターの利用もおすすめです。
焦らずお子さまのペースを尊重し、外の世界とのかかわりの中で成功体験を積み重ねていくことが重要です。
親自身のケアを忘れない
お子さまを支えるためには、保護者様ご自身も心身ともに健康であることが必要不可欠です。
お子さまのいじめや引きこもりの問題は、保護者様にとっても大きな精神的負担となります。
保護者様の心のケアにも関心を持ち、後回しにしないよう心がけましょう。
家庭の状況や悩みの内容を考えると、誰にでも話せるようなことではないと思ってしまうのは自然なことです。
しかし、一人で抱え込まず、家族や信頼できる人に相談したり地域の相談窓口や親の会などを利用したりすることを検討してみるのも手です。
また、十分な休息を取り、趣味やリラックスできる時間を持つようにできるとよいですね。
お子さまが大変な状況の中で、そのような時間を設けることに負い目を感じてしまうことがあるかもしれません。
しかし、保護者様が疲弊して家庭全体が暗い雰囲気になってしまっては、お子さまの回復の妨げになることもあります。
「誰かに話を聞いてほしいけど、誰に相談したらいいかわからない」というときは、地域で親の会などが開催されていないか、調べてみましょう。
同じような経験をした人とつながることができる上、サポートに関する情報交換や心の支えを得ることができます。
また、精神科や心療内科といった医療機関では、専門的な視点からアドバイスを受けることが可能です。
そのような場に出向くこと自体が負担に感じられる場合、「不登校こころの相談室」のようなオンラインカウンセリングを利用するのもおすすめです。
自宅からの相談であれば、よりリラックスした状態で臨めることでしょう。
保護者様が自分を大切にすることが、結果としてお子さまの支援にもつながります。
無理をしすぎず、周りのサポートを受けながら、お子さまと一緒に乗り越えていきましょう。
下の記事では、いじめによる心の傷を癒す方法として、カウンセリングの効果を詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてくださいね。
- こちらもチェック
-

いじめにカウンセリングは必要?効果や選び方をわかりやすく解説します
いじめは、被害者の心を深く傷つける行為です。 いじめによって受けた心の傷は、後遺症となってその後の人生にも影響を与えることがあります。 いじめによる傷を癒すことができるのが、カウンセリングです。 いじ...
続きを見る
いじめや引きこもりに直面したとき、保護者様にできる最初の一歩とは?

いじめの後遺症によって引きこもりが起こることは珍しくありません。
そして、引きこもりが長期化すると、お子さまの将来や社会生活に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。だからこそ、保護者様が早い段階で適切に対処できるかどうかが重要です。
いじめや引きこもりは、お子さまに大きな負担を与えるだけでなく、支える保護者様自身にも強いストレスをもたらします。
だからこそ「保護者様が自分を大切にすること」が、お子さまを支えるための土台になります。
「不登校こころの相談室」では、いじめや引きこもりに特化した心理カウンセラーがオンラインで寄り添い、お子さまと保護者様の両方を支えています。
対面に抵抗がある方でも、自宅から安心してご利用いただけるのが大きな特徴です。
とはいえ、「いきなりカウンセリングは不安」と感じる方も多いでしょう。
その場合は、まずは AI診断 を試してみてください。数分で答えられるチェック形式で、お子さまの状況を整理し、必要に応じて最適なカウンセラーをご案内できます。
不安や迷いを一人で抱え込む必要はありません。
まずはAI診断から小さな一歩を踏み出してみませんか?それが、お子さまの未来を守り、回復につなげる確かなきっかけになるはずです。